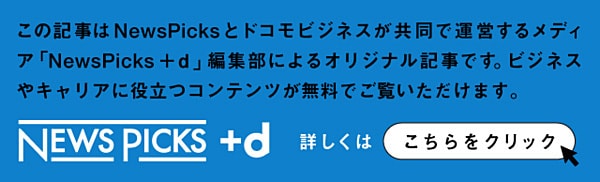【危機管理における正しい対応とは】
企業経営において、危機は必ず訪れます。
それは突然で、予想もしないタイミングで起こることが少なくありません。その際、どのように対応するかによって、企業の信用、そして未来は大きく左右されます。
危機管理とは、単にリスクを排除することではありません。重要なのは、危機が発生した際に、冷静に、的確に、そして誠実に対応できるかどうかです。
今回は総論として、過去の事例を通じて、危機に直面したときに企業が守るべき危機管理の基本を「7つの視点」から解説します。
社会批判が法的責任を上回る時代
日本社会において特に難しいのは、発生した事象の法的責任の有無や軽重にかかわらず、世論による激しい批判が企業価値を大きく損なうことがある点です。
2000年代以降、その傾向は一層、顕著になってきました。たとえば、2006年のシンドラー社製エレベーター事故や、2007年に発覚した不二家の期限切れ原料使用問題は、その典型です。
いずれの事案も、法的責任が明確ではない段階であっても、メディア対応の誤りや初動の混乱により、企業が社会から徹底的に糾弾され、経営が行き詰まりました。これらの事例は、危機管理の視点から学ぶべき教訓を多く含んでいます。
現在でも、同様の対応ミスが見られる企業は少なくありません。だからこそ、他社の失敗から学び、日ごろから危機に備えるトレーニングを重ねておく必要があります。

1)危機管理の出発点は、日常にひそむ「見えないリスク」と
どう向き合うか
リスクは、表面化して初めて発生するものではありません。常に企業の内部に潜在していて、その存在をどれだけ早く察知できるかが重要です。
近年では品質不正、環境問題、情報漏洩、ハラスメントなど、社会的関心の高い分野での不祥事が相次いでいます。
これらは、たとえ法的責任を問われない軽微な不備であっても、社会的には重大な問題とみなされ、厳しい批判の対象になります。「自社には問題がない」という思い込みこそが最大のリスクです。
潜在的なリスクに向き合い、情報開示の方針を事前に明確にしておくことが不可欠です。特に、人的被害や隠蔽と受け取られかねない事象については、迷わず迅速に開示するという判断基準を定めておくべきです。
2)危機対応の第一歩は「事実の把握」から
危機発生時に最優先すべきことは、正確な事実関係と因果関係の把握です。ここでの初動を誤ると、対応が後手に回り、かえって混乱を拡大させてしまいます。
たとえば不二家の事例では、誤解を招く内部文書の流出と、それに対する対応の遅れが、局所的な問題を「企業ぐるみの隠蔽」として受け止められる事態を招きました。
これは、早期に事実確認を行い、社内体制や対応状況を明確に説明していれば、防げた可能性が高い事例です。
外部から情報開示を求められた際に焦って断片的な情報を出すのではなく、冷静に、裏付けのある内容を伝える準備をする必要があります。
記者会見のタイミング
3)第三者委員会の設置は、冷静さを取り戻すための手段
有事の際、時間的猶予を確保し、冷静な調査と説明を行うために有効なのが、第三者委員会の設置です。第三者による客観的な検証は、企業の言い分に対する信頼性を高め、社会からの納得を得る手段にもなります。
しかし、第三者委員会も「設置すればよい」というものではありません。近年では、一部の委員が、実態調査よりも世論誘導を優先し、断定的な言葉で企業を断罪するケースも見られます。
こうした劇場型の報告書は、問題の本質を見誤らせ、再発防止よりも「企業叩き」に偏ってしまい、かえって企業価値を棄損させる結果につながりかねません。
第三者委員会の本来の目的は、信頼回復と再出発の支援です。そのためには、業界事情に精通し、冷静かつ独立した視点を持つ人材を選ぶことが不可欠です。

4)記者会見は「沈静化」と「炎上」の分岐点
危機対応において、記者会見は極めて重要な局面です。ここで求められるのは、「できる限り早く」「できる限りすべてを」「正確に」伝えることです。
初動での情報開示が不十分であると、メディアは「隠している」と受け取り、「追い記事」が繰り返されることで批判が増幅されていきます。
逆に、最初の記者会見で誠実にすべてを伝えれば、メディアも追及材料を失い、問題は比較的早く沈静化する可能性があります。
会見の時間帯にも配慮が必要です。午前中に行えば、夕刊中心の報道となり、相対的に露出は抑えられます。午後の会見では、夜のニュース番組や翌朝の新聞で取り上げられ、影響が長引く傾向があります。
インサイダー取引事件で立件された村上ファンド元代表の記者会見(2006年6月)では、午前11時の時間帯が意図的に選ばれ、報道の波を一定程度コントロールすることに成功しました。このように、記者会見のタイミングひとつで社会の印象は大きく変わるのです。
最終的なカギは経営者の覚悟
5)責任を「個人」に押し付けると組織全体が沈む
危機対応において、責任を個人に押し付けることは絶対に避けなければなりません。どんな問題も、組織の課題として受け止めるべきです。
2008年の野村証券のインサイダー事件や、不二家の対応ミスの事例でも、初期の段階で「個人の過失」として済ませようとしたことが、かえって組織全体への不信感を招きました。
組織として問題を引き受け、迅速な原因分析と再発防止策を講じていれば、被害の拡大を防げたはずです。
6)信頼を守る企業に共通する「誠実な向き合い方」
危機対応とは、社会に対して「企業の価値観」を示す機会でもあります。
企業に完璧さを求める人は多くありません。問題を認め、謝罪し、改善に向けて真摯に取り組む姿勢を見せることが、信頼を取り戻す最短の道です。法的責任だけでなく、社会的責任を果たす姿勢が問われるのです。

7)最後に企業を守るのは「経営者の覚悟」
危機対応の最終的なカギは、経営者の覚悟です。経営者が逃げ腰になれば、組織全体の士気が下がり、信頼回復は遠のきます。
日ごろからリスク感度を高め、万一の際には自ら前面に立って説明責任を果たす――この姿勢こそが、社員や社会に対する最大の信頼構築につながります。
「問題を早期に感知し、正直に報告する」文化を社内に根づかせることが、強い危機管理体制を育むのです。
危機のときこそ「企業の本質」が問われる
危機管理の成功は、偶然の産物ではありません。平時の備え、冷静な初動、誠実な説明、社会との対話、経営者の覚悟――その日々の積み重ねが、企業の危機対応力を形づくります。
危機のときこそ、企業の本質が問われます。社会からの信頼を得続けるために、日常の中にこそ危機管理の精神を根づかせていく必要があるのです。
次回以降のコラムでは、実際の事例をさらに掘り下げ、「危機対応のリアル」に迫っていきます。
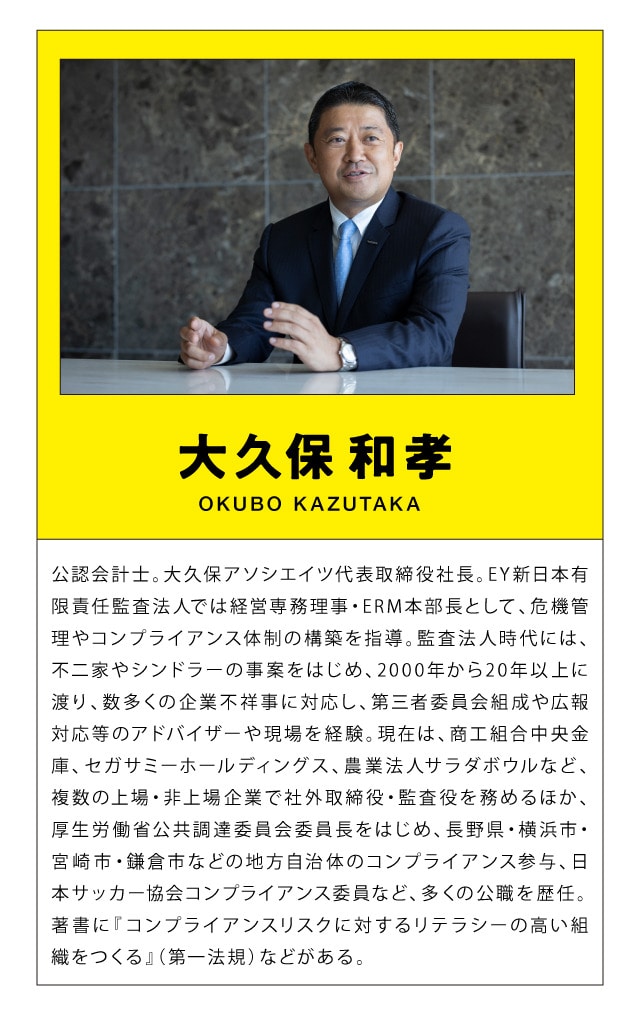
この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。
文:大久保和孝
編集:鈴木毅(POWER NEWS)
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
タイトルバナー:gettyimages








 JP
JP