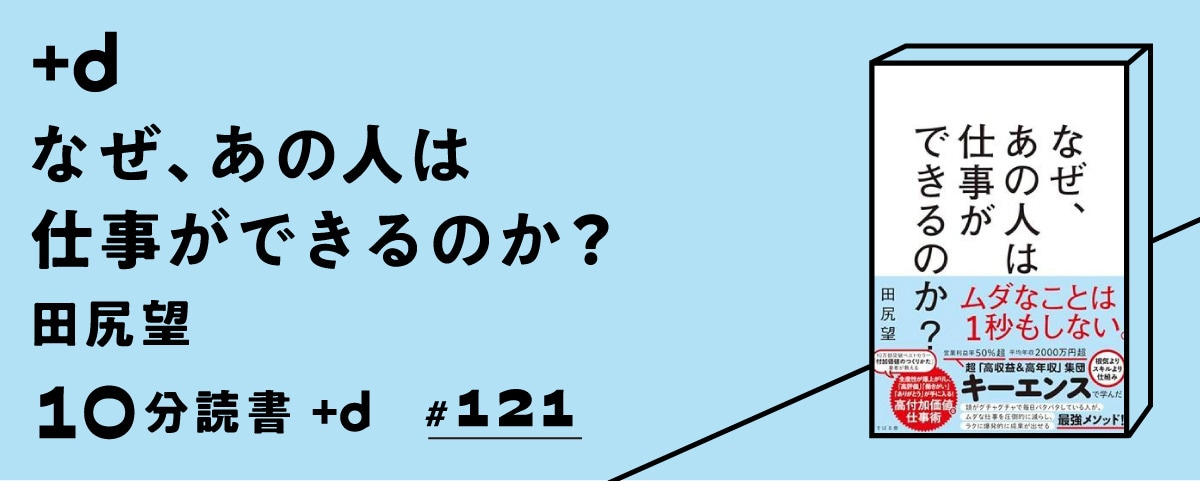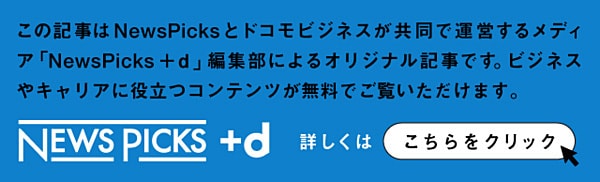■前回からご覧になりたい方はこちら
【読書】三日坊主を卒業。自分の“脳力”を底上げする習慣術
本書は10万部を突破した『付加価値のつくりかた』や『再現性の塊』などで知られる田尻望氏による一冊だ。
田尻氏はキーエンス出身で、現在は経営コンサルティング事業を手掛け、クライアント企業において、月1億円、年間10億円超レベルの利益改善を次々に成し遂げているという。
そんな著者が、「仕組み化」というキーワードのもと、「仕事ができる人」の秘密を教えてくれる。
田尻氏によると、キーエンスではあらゆる業務が「仕組み化」され、それらがすべて「仕事から生み出される付加価値を高める」という目的のもとにつくられていたそうだ。
読み終えた翌日から、自分が身を置いている「仕組み」に意識を向けられるようになるだろう。そして、あっという間に「仕事ができる人」に変身できるはずだ。
成果を出す人は仕事を「仕組み化」している
成果の大小は「仕組み」で決まる
思うように仕事の成果が出ないとき、その原因はたいてい「自分」ではなく「仕組み」にある。成果の出る仕組みの中にいれば成果は出るし、出ない仕組みの中にいれば成果は出ないという、ただそれだけのことだ。
例えば、営業職の仕事は、1件でもアポを増やして成約に結びつけていくことである。多くの成約を獲得するためには、商談の時間を十分に確保しなければならないが、報告書作成や会議に時間が奪われてしまう……。これは成果の出ない仕組みの一つだ。
仕事をどんどん「仕組み化」することで、成果に結びつかない時間を削減し、それによって生まれた時間を付加価値の高い仕事に回す。これが本書のテーマだ。
「仕組み化」=「効率化」+「高付加価値化」
「仕組み化」は「効率化」と「高付加価値化」という2つのステップから構成されている。簡単に言うと、作業時間を減らすのが「効率化」、仕事の価値を高めるのが「高付加価値化」だ。まず効率化、その後に高付加価値化の順で取り組むのがキモである。
高付加価値な仕事ができるようになると、成果につながる「価値ある仕事」に集中できて、周囲から評価されるビジネスパーソンになれる。
「効率化」を実現する3つの方法
「効率化」に有効な方法は3つある。
1つめは「フォーマットの統一」だ。文書やメール文、資料などのフォーマットを作成して、今後の作業時間を短縮する。
2つめは「見える化」だ。例えば、テレアポ先のリストをあらかじめ作っておくことで、ちょっとした空き時間に架電できて、短い時間で成果が出しやすくなる。
3つめは「言葉の統一」だ。「売上」「商品の価値」「利点」「機能」「特徴」「ニーズ」といった曖昧な言葉を明確に定義して共有するほか、取り組みの振り返りをする際は「数値化、変化、基準値」を揃えて語るといった工夫により、再現性を高められる。

「効率化」の基本
「効率化」の3つのステップ
「仕組み化」の第一段階である「効率化」は3つのステップから成る。
ステップ1:自分の行っている仕事を書き出してみる
ステップ2:時間を使っている順に並べ替える
ステップ3:上から順に「やめられないか」「まとめられないか」「回数を減らせないか」「自動化できないか」の4段階で対応する
3つのステップを踏むことで、より少ない時間で最大の利益を生む活動ができるようになるだろう。次項より、営業職を例に、具体的な手順を解説する。
ステップ1:自分の仕事を書き出す
ステップ1では、自分の仕事を書き出していく。
まずは1日の業務を分単位で洗い出そう。
今回はとある営業パーソンの業務として、顧客訪問、新規顧客開拓、提案書・見積もりの作成、内部ミーティング、レポート作成、自己学習・トレーニング、その他という7つが、それぞれの所要時間とともに挙げられたとする。
1日の業務とその所要時間を書き出したら、1カ月の作業時間を算出する。例えば自己学習・トレーニングに1日90分使っていたとすると、1カ月(20日)あたりの時間は1800分となる。
ステップ2:「時間を使っている順」に並べ替える
ステップ2では、書き出した作業を、1カ月あたりの「時間を使っている順」に並べ替える。例えば、以下のようにする。
1位「提案書・見積書の作成」合計3600分
2位「顧客訪問」合計2300分
3位「レポート作成」合計2100分
ここで重要な視点となるのが、成果に直結する業務か否かだ。この例だと、2位の顧客訪問は営業職のキモとなる業務であるため、今後増やしていくべきだろう。となると、真っ先に効率化すべきタスクは、1位の「提案書・見積書の作成」である。
ステップ3:4つの視点で整理・検討する
ステップ3では、効率化すべきタスクについて「やめられないか」「まとめられないか」「回数を減らせないか」「自動化できないか」の4つの視点で検討していく。
提案書作成の他、メールやレポート作成、リードリストの更新にかかる時間は、フォーマット化したり、リスト作成の工程を簡素化したりすることで短縮できるだろう。

【必読ポイント】 「高付加価値化」の基本
仕事の「高付加価値化」とは何か
先述の通り、「仕組み化」は「効率化」と「高付加価値化」の2つのステップから構成されている。ここからは、「高付加価値化」について解説したい。
仕事の「高付加価値化」とは、端的に言えば「時間単位当たりにおける自社の『粗利益の最大活動』」だ。
営業職の場合、顧客単価を上げること、リピート契約を獲得すること、横展開できるターゲティングをすること、紹介者をたくさん募ることなどが該当する。
「高付加価値化」の例として、1つあたり30万円の商材を扱っている営業パーソンについて考えてみよう。この人が年間3000万円の案件を契約できたとすれば、1つ30万円の案件の100倍の価値がある営業活動をしたということになる。
30万円の案件も3000万円の案件も「信頼を築き、ニーズを聴き、価値を示し、買うという意思決定をしてもらう」というプロセスは同じだ。
ただ、30万円分の契約が2回の商談で締結できるとすると、3000万円分の契約は、より多くの意思決定者が関わるため、まとまるまでに5~6回の商談が必要となるだろう。
ここで「高付加価値化=時間単位当たりにおける自社の『粗利益の最大活動』」という定義を思い出してほしい。
30万円の契約と3000万円の契約を「1回ずつの商談ごとに生む粗利益」に換算すると、30万円の契約は商談1回当たりの価値が15万円であるのに対し、3000万円の契約は500万円と、大きな差が生じていることがわかる。
このように、自分の活動を「時間単位当たりにおける自社の『粗利益の最大活動』」と考えることで、高付加価値化の意識が醸成されていくはずだ。
「挑戦」と「安定的な成果」を両立する時間の使い方
30万円から3000万円というレベルで単価を上げようとすると、顧客ターゲットを変える必要が出てくる。先ほどの例でいうと、「年商1億円未満の企業」から「年商10~50億円の市場へのチャレンジ」が必要だろう。
ここで注意したいのは、チャレンジに100%の時間を投じると、上手くいかなかったときに成果を著しく落としてしまいかねないことだ。そのような事態を避けるためには、既存案件に業務時間の70%を、チャレンジ案件に30%をあてるとよいだろう。
このとき、既存案件にかける時間を効率化して、70%の時間内で100%このとき、既存案件にかける時間を効率化して、70%の時間内で100%の成果を出すことを目標にしよう。そうすれば、残った30%の時間を心置きなく挑戦に投資できる。
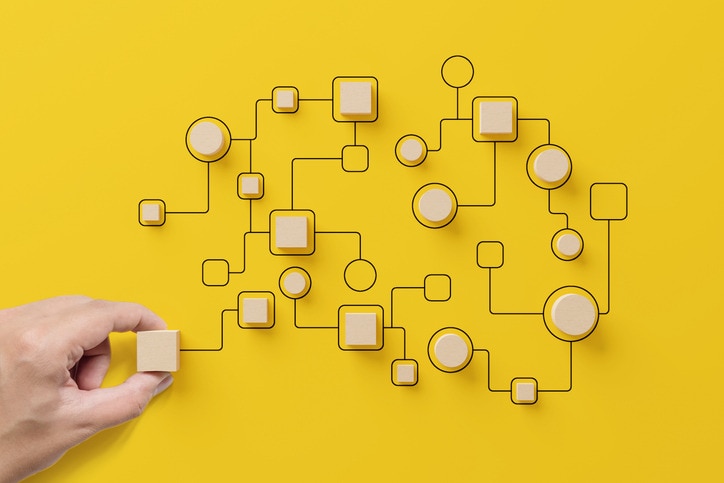
「仕事の高付加価値化」の実践例
仕事のスキルを磨く
ここでは、なかなかアポがとれず、訪問回数と成約数が伸び悩んでいるBtoB営業のAさんを例に挙げ、仕事を「高付加価値化」する手順を見ていこう。なおAさんは、「効率化」により、資料作成や報告にかけていた時間をある程度、減らした段階だとする。
まず取り組みたいのは、仕事のスキルを磨くことだ。訪問回数と成約数が伸び悩んでいる理由が「仕事のスキルが足りないこと」なら、まず基礎を身につける必要がある。
時間の使い方を改善する
Aさんが営業スキルを身につけたと仮定して、次に取り組みたいのは、時間の使い方を工夫することだ。
Aさんの現状を見ると、電話営業の時間が1.5時間しかなく、実際に電話をかけている時間は1時間だけだとする。
これだと、アポが取れたとしても1日1件だろう。このペースが続いたら、1カ月あたりのアポの数は20件にとどまる。1件の受注を取るためには2~3件のアポが必要だと仮定すると、成約率が100%だったとしても、1カ月あたりの受注件数は7件だ。
この状況を改善する方法として、電話営業と外回り営業の日を分けてはどうだろう。
現在は電話営業と外回り営業を同じ日に行い、それぞれに1.5時間ずつかけているが、1日集中して3時間の電話営業を行えば5件のアポが取れると仮定すると、1カ月あたりのアポイント数は50件となる。これは現在の2.5倍の成果だ。
ターゲットを見直す
とはいえ、営業スキルが十分でなければ、3時間の電話営業で5件のアポを取るのは難しいかもしれない。
アポ率を上げたいなら「買ってくれる会社は、どんな会社なのだろう?」「興味を持ってくれる経営者や担当者は、どんな人なのだろう?」と考える時間を取る必要がある。
この2つの問いについて考えるうちに、過去の取引で非常に喜んでくれたお客様と、そうでもなかったお客様の違いを思い出すかもしれない。
そうすれば、その商品を喜んでくれそうなお客様像がクリアに見えてくる。同時にトークスクリプトの磨き込みも行い、喜んでくれそうなお客様に対して丁寧にアプローチすれば、アポ獲得率は大いに向上するだろう。
顧客リスト作成・精査にかける時間を減らす
Aさんは、顧客リストの作成と精査に毎日30分をかけているとしよう。結論から言うと、この作業は週に1回で十分だ。そうすれば、2時間×4週で、1カ月あたり8時間空く。1日8時間労働なら、営業日が1日増える計算だ。
また、営業成績が伸び悩んでいるときは、ターゲットがズレている可能性がある。営業成績のいい先輩に相談してみると、より受注確度の高いターゲットが見つかるかもしれない。ChatGPTに相談するのも良い手だ。

移動のムダをなくす
最後に注目したいのは、移動時間だ。
Aさんの場合、外回り営業1.5時間のうち、移動と休憩に1時間、事前のアポイント無し訪問に30分かけているとする。
Googleマップを使って移動を効率化する、突撃訪問はやめて事前にアポイントを取る、エリアごとにまとめて電話営業をし、訪問時間帯を固めるなどの工夫により、ムダをなくそう。
「付加価値アップ」につながらない時間は、できる限り短縮しよう。ムダな時間は減らし、顧客訪問やそれにつながることに時間を割く、という意識が大切だ。
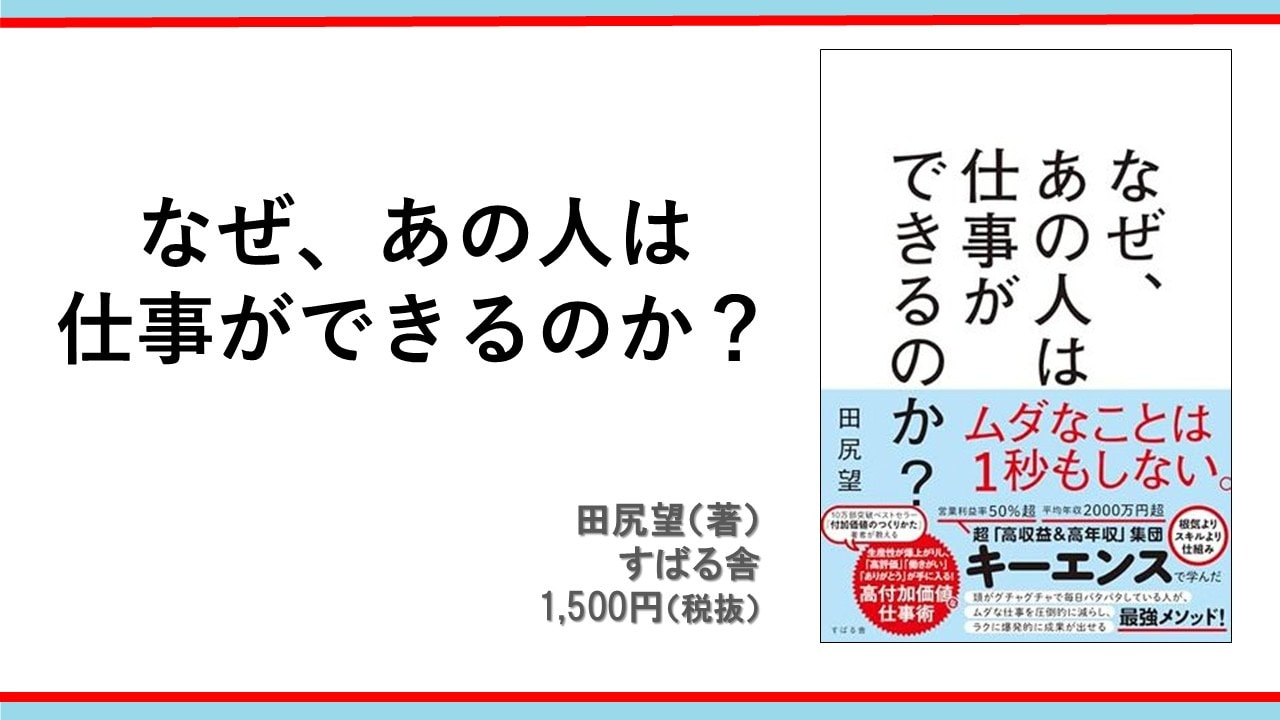
この記事はNTTドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。
提供:フライヤー
編集:斉藤和美
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)








 JP
JP