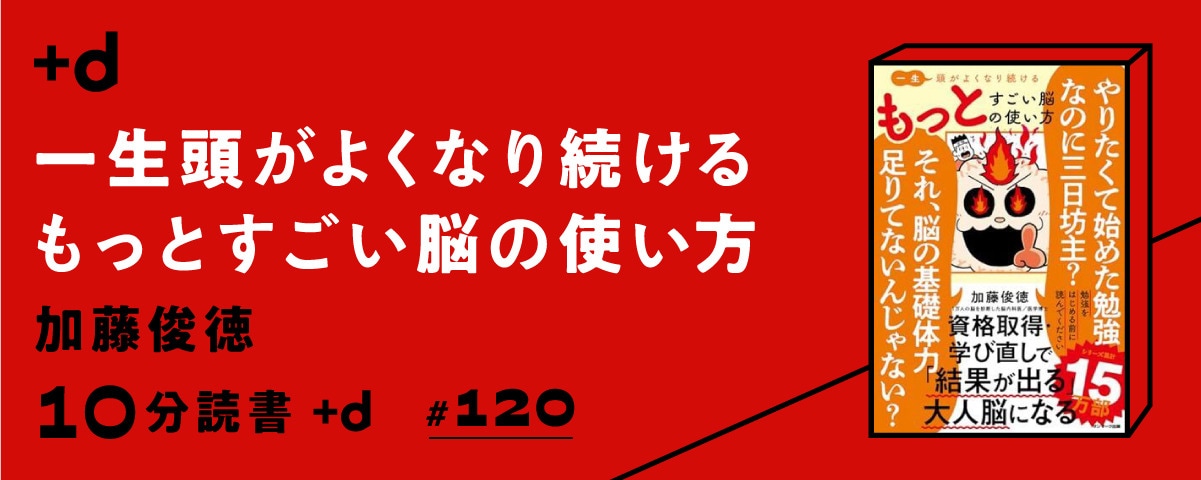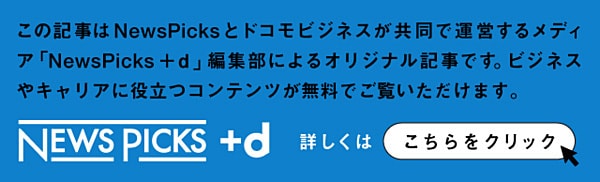脳内科医として1万人以上の脳を診断・治療してきた著者、加藤俊徳氏は「あなたが何歳でも、脳は必ず自分の力で変えることができます」と断言する。
そして独自の「脳番地」の考え方に従い、“大人脳”にとって効率のよい勉強法や計画の立て方を教えてくれる。
人生は長い。「もういい年齢だから」と諦めていた人も、本書を読んで「一生頭がよくなり続ける もっとすごい脳の使い方」を実践してみてはどうだろう。
勉強を始める前に知っておきたいこと
「脳番地」の基礎知識
どんなに運動能力が高い人でも、フルマラソンを一度も練習しないで走ろうとはしないだろう。本番に備えて準備運動をし、基礎体力をしっかりつけるはずだ。脳も同じで、新しく勉強などを始める前には準備運動が必要である。
まず知っておいてほしいのは、脳内には8つの「脳番地」があり、それぞれの脳番地が異なる役割を担っているということだ。
具体的には、視覚系脳番地、聴覚系脳番地、思考系脳番地、理解系脳番地、記憶系脳番地、運動系脳番地、感情系脳番地、伝達系脳番地の8つである。
毎日同じような日々を過ごしていると、使う脳番地が偏ってしまいがちだ。脳番地への理解を深めるとともに、普段あまり使っていない脳番地を意識的に動かして、脳の基礎体力を底上げしよう。
脳内で起こる「発火」
あなたは今、公園のベンチに座ってぼーっとしているとしよう。その間も、脳内ではいくつかの脳番地が稼働し、毎秒1~5回の電気信号が送り出されている。
そこで公園に桜が咲き始めていることに気づけば、電気信号は毎秒50~100回程度にまで増える。久しぶりに会う親友が偶然現れでもしたら、電気信号は毎秒500回以上になるだろう。
このように電気信号が活発になった状態を「発火」という。
インパクトの強い情報が脳に入力されると強い発火が起こる。「もっとすごい脳」を手に入れるためには、発火をコントロールして、脳の働きをよくすることが非常に重要だ。

情報を記憶に強く留めるには?
普段から使用頻度の高い脳番地同士は連携が強く、車が高速道路を走るようにスイスイと情報を伝達できる。
一方、あまり使われていない脳番地の情報伝達スピードは、使用頻度によって、流れのいい二車線の一般道路のようだったり、ノロノロ運転の狭い一方通行道路のようだったりする。
発火は脳の連携プレーにも強く関係する。
目や耳を通して脳に情報がインプットされると、視覚系や聴覚系の脳番地が発火する「ニューロナルファイアリング」(以下、ファイアリング)が起こる。
その後、「ネットワークファイアリング」によって、インプットされた情報が理解系や思考系の脳番地に届けられる。
つまり脳内では、脳番地のファイアリングが起こり、ネットワークファイアリングによって情報が伝達され、また次の脳番地でファイアリングが起こる……というサイクルが繰り返されているのだ。
最初の情報入力のインパクトが強いほど、ファイアリングが強くなり、ネットワークファイアリングから次のファイアリングへの伝播もしやすくなって、記憶に定着する。
注意したいのは、使用頻度の低い脳番地ではファイアリングが起こりにくくなっていることだ。
結果として、ネットワークファイアリングも起こりづらくなり、せっかくインプットされた情報を活かし切れない。
そうならないよう、まずは各脳番地の特性とファイアリングが起こる条件を把握しよう。
8つの脳番地をファイアリングさせる方法
ここでは、8つの脳番地の概要を解説する。
視覚系脳番地は、目で見た情報を脳に集める役割を担う。視覚系のファイアリングを強くしたいなら、物事をゆっくり注意深く見たり、波や雲など流動的に形が変わるものを見たりするのがよい。
聴覚系脳番地は、耳で聞いた情報を脳に集める働きをする。聴覚系の働きをよくするには、話し声や街の音、音楽など、多種多様な音を聞くのが効果的だ。
思考系脳番地は脳の社長のような役割を担う、守備範囲の広い脳番地だ。何かに注意を向ける、物事を選択する、応用する、処理する、価値判断を決めるときなどに働く。
思考系をファイアリングさせて強化する方法の一つは、時間を“見える化する”ことだ。特に、1日単位、1週間単位など、短い期間でスケジュールを立てると、他の脳番地に命令を出しやすくなる。
理解系脳番地は、目や耳から入ってきた情報を理解したり、わからないことを推測しようとしたりするときに働く。
トレーニングとしては、ニュース記事やテレビのコメンテーターに「それって、本当?」などと茶々を入れて、自分なりに事実を検証することが有効だ。
記憶系脳番地は、ものを覚えたり思い出したりするときに働く脳番地だ。刺激やインパクトの強い情報に触れることで、強いファイアリングを起こせる。
運動系脳番地は、体を動かすこと全般に関わる脳番地だ。他の脳番地をファイアリングさせるトリガーでもあるため、運動をおろそかにすると、脳全体のファイアリング能力が低下してしまう。毎日10分多く歩く習慣をつけよう。
感情系脳番地は、喜怒哀楽を表現する役割を担う。この脳番地をファイアリングさせるには、日記に自分の感情を書き留めるのがおすすめだ。美しい景色や音楽、感動する映画、質のよいものや大好きなものに触れるのもよい。
伝達系脳番地は、アウトプットをする働きがある。メールや日記を書くだけでもファイアリングするが、声に出して誰かに伝える対話のほうが、よりファイアリングの程度が強くなる。

【必読ポイント!】
勉強のポイントは「小刻み」「1テーマ」「余韻」
「記憶力」より「検索力」
加齢とともに「ここまで出てきているのに思い出せない」ことが増えるものだ。実はこの現象は記憶力の低下によって起こっているのではない。記憶を引っ張り出してくる「検索力」の低下が原因だ。
引っ越し後の片づけをイメージするとわかりやすいだろう。
新居でダンボールを開けようとしても、何がどこに入っているのかわからず、時間も労力もかけて全部の箱を開けるしかない……ということがあるはずだ。
「ここまで出てきているのに思い出せない」とき、脳の長期記憶倉庫の中では同じ現象が起こっている。
検索力が低いと、せっかく勉強しても、必要なときに知識を引っ張り出せない。長期記憶に知識を入れっぱなしにせず、定期的に引っ張り出して整理し、いつでも取り出しやすいように保管しておくことが大事だ。
脳の記憶のシステム
ここでは脳の記憶のシステムを整理しよう。
勉強をしているときに働いているのは「ワーキングメモリ」だ。
ワーキングメモリとは、作業に必要な情報を一時的に記憶する脳内の時空間のようなもの。これからかける電話番号を暗記したとしても、10分も経つと全く記憶に残っていないのは、ワーキングメモリの特徴によるものだ。
ワーキングメモリで集約された情報は短期記憶へと送られる。そして、記憶の番人である海馬が「この情報は重要だ」と判断すると、長期記憶へと送られ、記憶に定着する。
ただし、長期記憶に送られたからといって、いつまでも記憶に留めておけるわけではない。
忘れたくない情報は、何度も長期記憶の中から引っ張り出して、改めて内容を整理したり、新しい情報を付け足したりする必要がある。
この作業により、長期記憶の中にフォルダが作られ、情報を引き出しやすくなる。
20分の「小刻み学習」を繰り返す
ここからは、脳の記憶のシステムを踏まえて、大人脳にとって効率のいい勉強法のポイントを3つ紹介する。
1つ目のポイントは、1回の勉強時間を20分程度に抑えた「小刻み学習」を繰り返すことだ。飽きっぽい脳にとって、長時間の勉強より、時間を短く区切った学習のほうがはるかに効率的である。
調子がいい日も、いったん20分で区切りをつけて脳をリフレッシュさせよう。5分弱の休憩をとってまた20分の勉強に戻ることで、脳を疲弊させることなく効率的に動かせる。

学習するテーマは1つだけ
2つ目のポイントは、一気に複数のテーマを並行して学ぶのではなく、1つに絞ってそれに集中することだ。
カフェで勉強しようと思ったとき、「もしかしたら時間が余るかもしれないから」と、余分なテキストまで持参していないだろうか。大人脳を効率よく使いたいなら、持ち出すテキストは1冊に絞ろう。
複数のテキストを持ち出したあなたは、カフェに着いたとき、「何から取り掛かろうか」と考えるだろう。この思考には大量のエネルギーを要する。
また、複数のテキストを持っていると、しばらく勉強した後、気分転換のために別のテキストに手を出してしまうことがある。これは脳を混乱させる行動だ。
パソコンに資料を保存するときをイメージしてほしい。パソコンで資料を作ったら、後で探しやすいように、適切なフォルダの中に成果物を格納するだろう。
複数のテキストをつまみ食いするのは、いわば、フォルダに無関係な情報を紛れ込ませてしまうようなものだ。勉強した内容を長期記憶に定着させ、記憶から取り出しやすくしたいなら、その時間に勉強するテーマは1つに絞ろう。
脳の「余韻」をうまく使う
3つ目のポイントは、学んだことを脳内でクルクル回す「余韻学習」の時間を含めてスケジューリングすることだ。
前提として、脳のファイアリングには短期反応・中期反応・長期反応の3種類がある。
脳番地の連携プレーがうまくいっているときは、入力による最初のファイアリング/短期反応(最初の発火)→ネットワークファイアリング→中期反応(2度目の発火)→ネットワークファイアリング→長期反応(3度目の発火)という順番でファイアリングが起こる。
記憶への定着を強化したいなら、3度目のファイアリングである長期反応の「余韻」をうまく利用するとよい。
たとえば、勉強時間を30分とれるなら、20分間の「小刻み学習」をし、残りの10分間はウォーキングをする。この10分のウォーキングが「余韻学習」だ。
ウォーキングで運動系脳番地を刺激して脳全体を活性化させつつ、勉強した内容を振り返りながら歩けば、脳への定着率が格段にアップする。
脳を効率的に動かす勉強計画
スケジュールは100日単位で
勉強しようと決めたら、計画を立てて、時間軸を明確にすることから始めよう。これにより、8つの脳番地は自分の役割を理解し、目標達成に向けて動き出す。
まず取り組むべきは、自分の持ち時間を明確にすることだ。ここで「ざっくり」はNGである。スケジュールがざっくりだと、脳は動いてくれないからだ。
試験日が決まっている場合は、勉強に使える時間を正確に把握しよう。土日が休みの社会人であれば、「平日の勉強時間×日数+土日の勉強時間×日数=総勉強可能時間」を割り出すことが、合格への第一歩だ。
また、脳が働きやすいスケジュールのポイントは、具体的にイメージしやすい「100日」の単位で区切ることだ。4カ月=約120日の持ち時間があるなら、100日+20日のように区切るとよい。

年間勉強スケジュールの立て方
試験当日までの持ち時間が1年間ある場合、大人脳にとって効率的な勉強スケジュールは以下の通りである。
- 勉強スタート時に模擬テストを実施して、テストの出題形式と自分の理解度を把握する。
- 最初の65日は、勉強する内容と脳の親密度を高める。テキストをパラパラと眺めて、興味を持てた箇所から少しずつ読み進めていく。
- 最初の100日で、テキストの全範囲を履修する。
- 2回目の模擬テストを実施し、次の100日で、分野やテーマごとに勉強する内容を区切る「カテゴリー学習」をする。
- 3回目の模擬テストを実施し、最後の100日で合格に必要な点数を確実に取れるようにする。
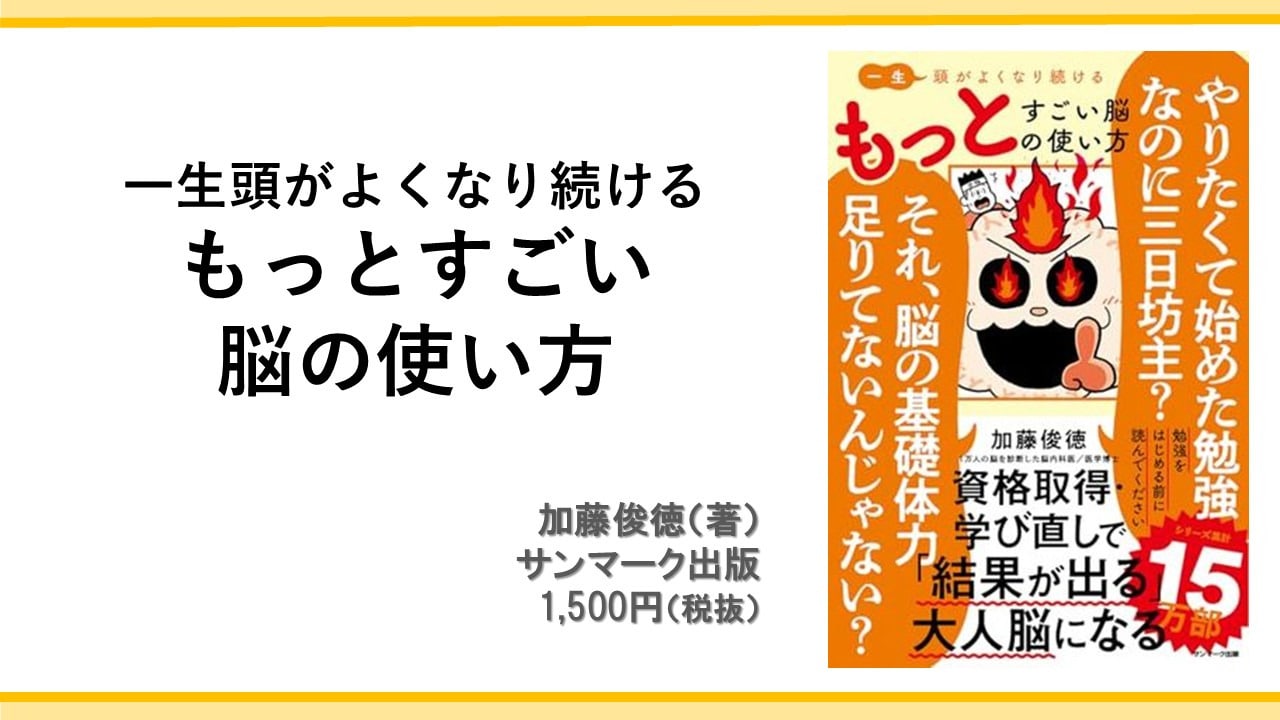
この記事はNTTドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。
提供:フライヤー
編集:斉藤和美
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)








 JP
JP