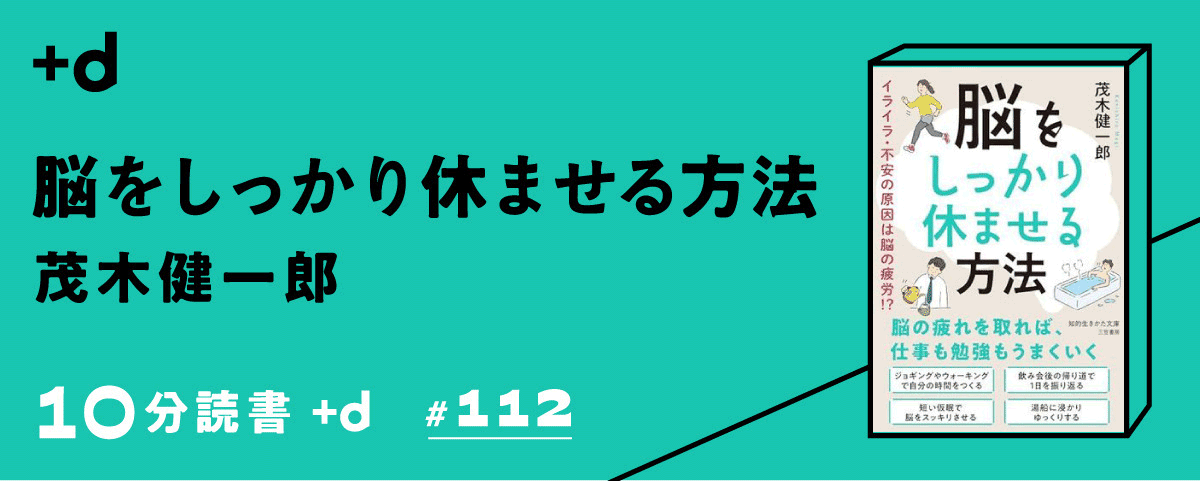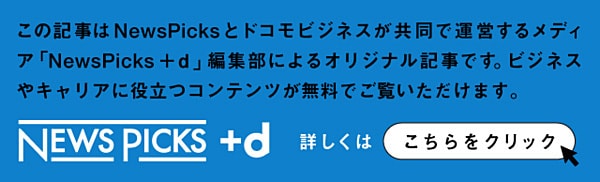休日に家でのんびりしたのに、仕事の疲れが取れない──。このように感じている人は多いだろう。実はその疲れは、脳の疲れからきているのかもしれない。
本書は、文筆家やタレントとしても広く活躍する脳科学者の著者が、脳の疲れを解消する方法を科学的な視点で解説した一冊である。身体を休める重要性は誰もが知るところであり、多くの人は、身体を休めさえすれば私たちは元気になると考えている。
しかし、疲れを完全にリセットするためには脳を休ませなければならず、そのためには別のアプローチが必要だと著者は語る。
このところ疲れて仕事のパフォーマンスが悪いという人は、ぜひ本書のメソッドを実践してほしい。脳を休ませることで得られる効果を、身をもって実感するはずだ。
【必読ポイント】 脳を休めれば創造性が上がる
「ぼんやり」がひらめきを生む
「なんだか疲れが溜まってきたな……」と感じて、休日に家でゴロゴロしたり温泉に浸かったりしたのに、それでも疲れが取れない、という経験はないだろうか。
その原因は「脳の疲れが取れていない」からかもしれない。いくら身体を休めても、脳がしっかり休まっていないと脳に疲労が蓄積し、身体全体や仕事のパフォーマンスに悪影響を与えてしまう。
最新の脳科学では、「ぼんやり」と過ごして脳を休めることで、クリエイティブなひらめきが生まれることがわかってきた。ボーッとして脳を休めている間に、一度集約された情報や記憶が整理されるのだ。
重要なのは、集中とリラックスのバランスだ。机に向かって一生懸命考えているだけではアイデアは出てこない。集中したあとで脳がリラックスしアイドリングしているときにこそ、ひらめきが生まれるのだ。
一流のクリエイターは脳を休めている
歌手の松任谷由実さんや作曲家の秋元康さんなど、一流のクリエイターは総じて「脳の休ませ方」がうまい。毎日多忙なはずなのに、まるで「夏休みの宿題が終わった小学生」のような余裕のある雰囲気をまとっている。
実は、脳を休ませることと創造性には密接した関係がある。
彼らはすべての時間を創作に捧げているのではなく、現場から離れてボーッとする時間を意識的に設けている。脳を休ませてエネルギーを回復する隙間時間をつくることで、後世に残るような名曲を生み出しているのだ。
一方、ただがむしゃらに働いているビジネスパーソンは脳の休め方を知らない。こういった働きぶりは短時間の集中はできても、長い時間、高密度の仕事をすることはできない。つまり、なかなか仕事のクオリティを上げられないということだ。
がむしゃらだけでは結果が出ない。それを知っている一流のクリエイターは、あえて脳を休ませる時間をつくるのだ。

休憩中はスマホに触らない
ひらめきは、無意識のなかにあるドットとドットが結びついたときに生まれるが、このドットをつなごうとする脳活動を「マインド・ワンダリング(Mind Wandering)」と呼ぶ。
マインド・ワンダリングとは、目の前の課題から離れ、ぼんやりとさまざまなことに思いを巡らせている状態である。この活動によって脳は休まり、結果的にひらめきが生まれやすくなる。
とはいえ、テレビやスマホ、パソコンに囲まれながら「何もしない時間」をつくるのは容易ではない。ちょっとした休憩時間にも、ついスマホに手が伸びてしまう人は多いだろう。
まずは、お昼休みなどの休憩中にスマホに触らないことから始めてみよう。それも難しいという人は、椅子に座って何も考えずに10分間目をつむるだけでいい。それでも十分、脳を休ませることができるはずだ。
脳を鍛えてストレスに強くなる
テンションを上げて脳を守る
強いストレスが長く続くと、コルチゾールというストレスホルモンが大量に分泌されて脳の器官「海馬」が委縮する。すると物覚えが悪くなり、アルツハイマー病や認知症になる可能性もあることが最新の脳研究で明らかになった。
ストレスの対処にはさまざまな手法があるが、著者が脳科学の見地から勧めるのは「テンション・コントロール」だ。
これは、何かしらの出来事に対して「自らテンションを上げていく」ことである。たとえば、試験の前日は「明日は試験だ! 頑張らなくちゃ!」とあえてテンションを上げてみる。
テンション・コントロールができる人のほうが、脳を活性化させ、いい成績を収めることができるのだ。
「ごっこ遊び」がストレス耐性を高める
ストレスは悩みの種だが、完全にゼロにすればよいというわけでもない。ストレスがまったくかからない生活は、毎日が単調になって脳機能が衰えてしまうからだ。ストレスのダメージをなくすのではなく、ストレス耐性を鍛え、高めていくことを意識しよう。
ストレス耐性アップにお勧めなのが「ごっこ遊び」だ。
「大人になってごっこ遊びなんて……」と思うかもしれないが、これは「役割を演じる」とも言い換えられる。
たとえば友達とキャンプに行ったら「テントを張る人」「買い出しに行く人」「料理をつくる人」など多くの役割が生じるが、そこで自分の役割を素早く見つけてしっかりこなす。
仕事でも同様に、自分の役割を理解してそれを精一杯演じてみよう。適度にストレスがかかり、自身のストレス耐性を高めてくれるはずだ。

「句読点」を意識する
仕事や勉強をダラダラ続けていては、脳は休まらない。重要なのは、終わった瞬間に脳を切り替えて気分転換をすることだ。
この素早い切り替えは、脳の「句読点」となる。句読点のない文章は読みにくいのと同様に、脳も句読点があってはじめて休まるのである。
切り替え上手になるためには「自分がコントロールできること、できないことを区別する」という方法がお勧めだ。
これは「好きな人に好かれるための努力はできても、自分を好いてくれるかどうかは相手次第」というのと同じである。
自分がコントロールできることはベストを尽くし、そうでないことについてはあきらめる。この「仕分け」ができれば脳はうまく休まり、ストレスも軽減されるだろう。
とはいえ「上司がいつ怒るかわからない」というような、コントロールも予測もできない状況にはストレスが溜まる。
こういったとき「上司が怒るのは自分のせいだ」と思い込むのはよくない。それを回避するためには、自分のなかに相手の「内部モデル」をつくって、相手の考えや振る舞いを推測してみるといい。
内部モデルとは「上司の○○さんはこんな人」と、自分のなかにつくる相手の人物像だ。それを基準に「なんでこの人はこう振る舞うのか」と推測してみよう。
相手のやり方についてある程度理解できるようになれば、親近感がわき、対処の仕方もわかってくるだろう。
脳を休めてパフォーマンスを高める
デフォルト・モード・ネットワークを働かせよう
疲れたと感じるとき、実は身体ではなく脳が疲れているときが多い。脳は疲れると「身体が疲れている」と錯覚させ、強制的に身体を休ませようとするからである。
脳を休ませるためには「デフォルト・モード・ネットワーク」という脳の活動がカギとなる。
脳内の「感情」「運動」「記憶」などをつなぐ役割をもつデフォルト・モード・ネットワークだが、おもしろいことに、何も考えずにボーッとしているときにだけ活性化する。
つまり、ボーッとすることが脳の休息やメンテナンスにつながるのだ。
著者はデフォルト・モード・ネットワークを働かせる方法として、「歩行禅」「お風呂に入る」「ジョギング」の3つを勧めている。
「歩行禅」とは「歩く瞑想」とも呼ばれ、Googleでは研修に採用されている。歩くことは脳のメンテナンスに多大な効果があると言われており、とくに朝日を浴びながら30分ほど散歩をすると、うつ予防やストレス軽減などのメリットもある。
さらに、睡眠も重要だ。睡眠はデフォルト・モード・ネットワークの活動の調整に不可欠で、睡眠が足りないとデフォルト・モード・ネットワークの回路の結びつきが弱くなることがわかっている。
デフォルト・モード・ネットワークを働かせるには、質が高く、深い睡眠が必要だ。浅い眠りでは身体は休めても、脳まで休めることができない。理想的なのは、入眠後すぐに深い眠りに入り、起床時間まで目が覚めないような睡眠だ。

「脳の焼きなまし法」で成果を上げる
金属工学で鋼材に用いられる熱処理に「焼きなまし法」というものがある。これは加熱した金属材料を少しずつ冷やし、金属をやわらかくする作業のことだ。
脳を休めることは、焼きなまし法に似ている。
鋼材を加熱するのは「脳がフルで頑張ること」、鋼材を冷却するのは「脳を休ませること」である。つまり大事なのは、脳を休める前に目一杯脳を使うことだ。「脳の焼きなまし法」をすることで、パフォーマンスをフルで発揮することができるだろう。
仮に、次の日に大事なプレゼンが控えていたとする。前日に行うリハーサルでは、本気モードで思い切りプレゼンをするのである。気づいた点や改善点が出てきたら、そこで一旦脳を休ませる。
脳を急速に熱した後は、冷ましてあげるのだ。これにより脳がアップデートされ、より良いプレゼンに進化する。
<実践>脳の休め方
離れて、着替えて、切り替える
今の時代、がむしゃらで一生懸命な頑張りは評価されない。代わりに求められるのは、高いパフォーマンスを瞬間的に発揮して成果を出すことだ。そのためには脳を徹底的に休める時間をつくり、エネルギーを溜めこんでおくことが欠かせない。
効果的に脳を休めるための方法として、著者はまず「現場を離れる」ことを勧める。仕事や勉強が終わったら、その場所を物理的に離れることで、脳の思考を切り替えることができるからだ。
「着替えをする」ことも有効だ。仕事終わりに制服や作業着から着替えたり、スーツのジャケットを脱いでネクタイを外したりすることで、脳に切り替えのシグナルが送られる。著者はこれを「脳内コスプレ法」と呼んでいる。
「一人時間」をつくる
家族や友人とのひとときは楽しい反面、脳を疲れさせる。周囲や会話に気を配る必要があるからだ。脳を休ませるためには一人になり、自分の気持ちを整理する時間を意識的に確保したい。
「自分時間」をつくるために実践してほしいのが、「おひとりさまごはん」だ。
何を食べるかを自分自身で決め、一人で味わって食事をするのだ。脳内伝達物質のドーパミンが分泌され、脳への栄養補給にもなる。ついスマホに手が伸びそうになるが、グッと我慢してボーッと過ごしてみよう。
気ままな一人旅も脳を休ませるために効果的だ。誰からも邪魔されずマイペースに旅をすると、脳内でセロトニンが分泌されてリラックスする。脳を休ませるには「一人時間」が欠かせない。

他人に流されない軸を持つ
大きな成功を収めたビジネスパーソンや歴史に名を残す偉人は、「自分はこうあるべきだ」という信念を持ち、それに従って行動している。
「自分はいつも他人に流されながら生きている……」と感じている人は、些細なことでいいから、過去の成功体験を思い出してほしい。そこから自分の強みや自分らしさ、「ありたい姿」を引き出そう。
そして、それを基に自分の価値観を設定し、それに従って生きるのだ。
自分の軸を持って生きることは、脳を休ませることに関係していると著者は考える。自分を見つめ直し、考え方を整理している時間そのものが、脳を休ませている時間だからである。
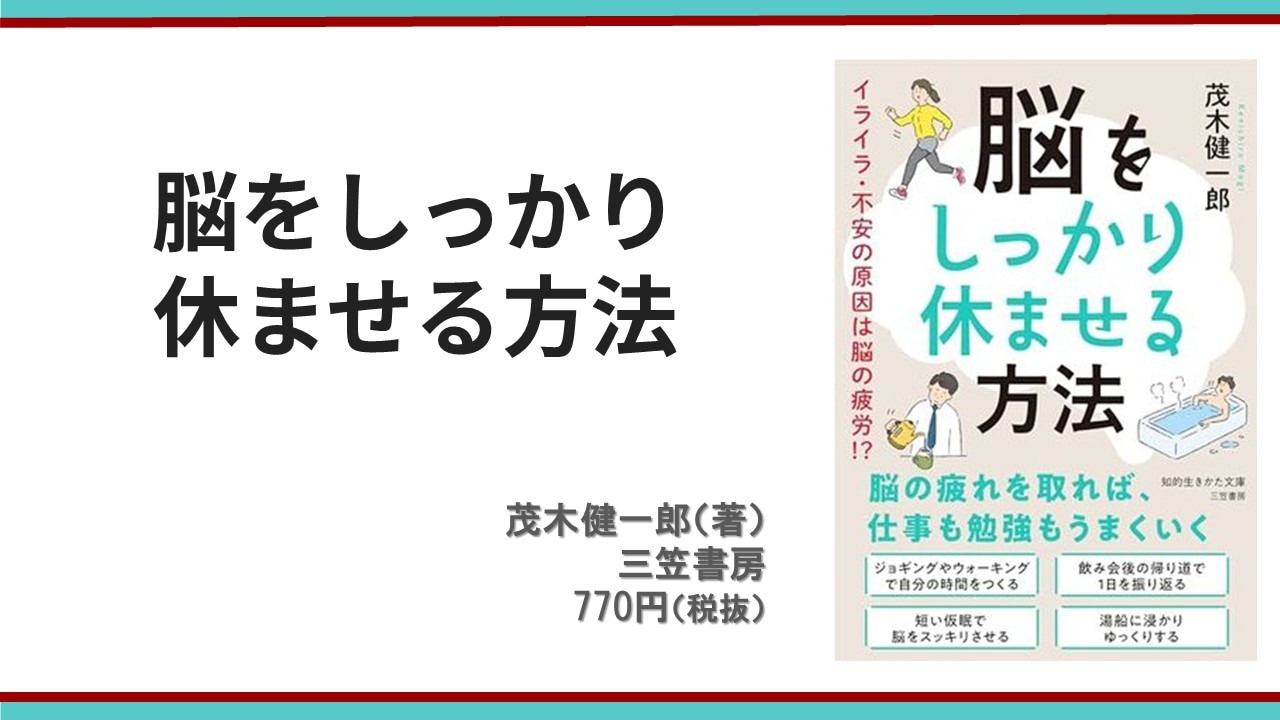
(知的生きかた文庫 も 22-4) : 茂木 健一郎: 本
この記事はNTTドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。
提供:フライヤー
編集:斉藤和美
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)








 JP
JP