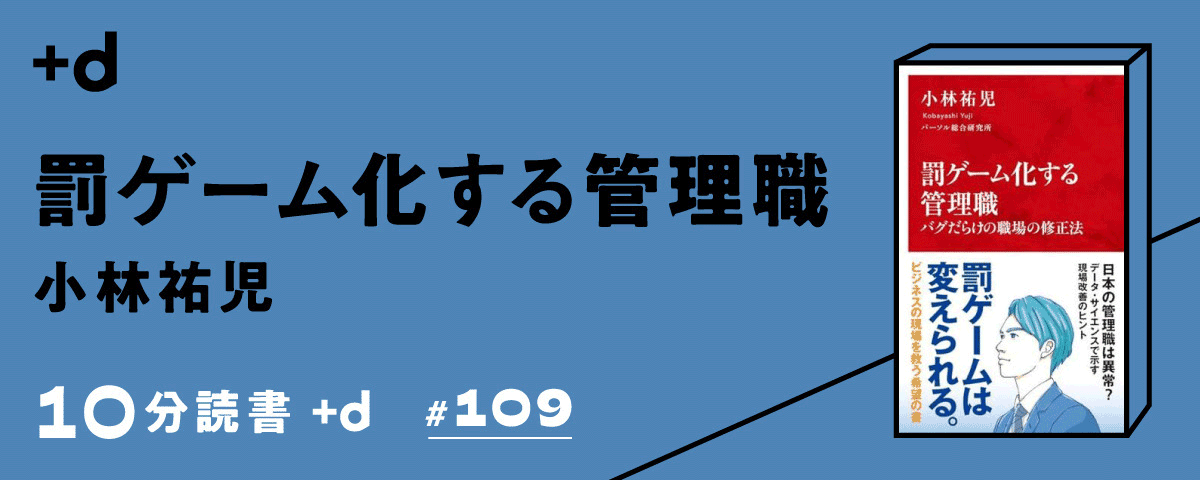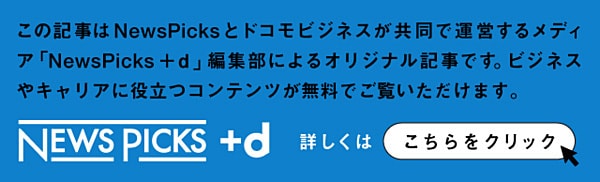「毎日へとへとになるまで働いている」「連日、深夜まで残業」……こうした声を聞いたとき、あなたはどんなビジネスパーソンを想像するだろう。多くの人は、仕事を押し付けられた若い社員を思い浮かべるのではないだろうか。
しかし、本書のタイトルを見ればわかる通り、これらはいま管理職に起きていることだ。そして、そんな上司をすぐそばで見ているメンバー層は管理職になりたがらない。これを著者の小林祐児氏は「管理職の罰ゲーム化」と呼んでいる。
本書では、「罰ゲーム化」を修正する4つのアプローチが明確に提示される。いままさに悩み苦しんでいる管理職、「管理職にはなりたくない」と怯えるメンバー、そして「管理職研修を実施すれば改善するだろう」と楽観的に捉えている経営者や人事部門をはじめ、多くのビジネスパーソンに読んでほしい一冊だ。
管理職の「罰ゲーム化」
誰もやりたくない管理職
今、管理職として働くことは「罰ゲーム」と化しつつある。
「朝から晩まで会議ばかりで、夜からしか自分の仕事ができない」
「メンタルヘルスの不調で、常に部下が欠けている状態で働いている」
……こうした課題が次から次へと湧いてきて、管理職の心身をすり減らす。メンバーはそんな上司を横目で見て、管理職に就くことにますます魅力を感じなくなる――。
この問題は深刻だ。管理職ポストの後継者不足、イノベーション不足、部下育成不足、管理者本人のストレス、自殺という悲劇に至るまで、管理職の「罰ゲーム化」の影響はもはや経営・組織の問題の域を超え、「社会課題」と呼ぶべき事態になっている。
低下する管理職の魅力
パーソル総合研究所の国際調査によると、日本における「管理職になりたいメンバー層の割合」は21.4%と、14カ国のうち断トツの最下位となっている。同じく管理職意欲の男女比率を見ても、女性の意欲の低さは断トツ最下位だ。
年代ごとの管理職意欲に目を向けると、日本の異常さがさらに際立つ。日本だけ40代で一気に管理職意欲が下がるのだ。つまり、他国では何歳になっても管理職を目指し続ける人が多い一方で、日本では、40代までに管理職になれなかった人は「諦める」のである。
時系列でも確認してみよう。日本生産性本部の調査を見ると、平成最後の10年間のデータにおいて、昇進について「どうでもよい」という回答だけが男女ともに高まっている。
同様に、博報堂生活総合研究所の調査データでは、「会社の中で出世したい」という設問に肯定的な回答をする人は1998年の19.1%から徐々に低下し、2022年には13.2%だ。
これらのデータを総合すると、日本では、管理職への出世に魅力を感じる人が少なく、この20~30年ほどでその傾向がより顕著になっているといえるだろう。
管理職の罰ゲーム化が進めば、次世代のリーダーは育ちにくくなる。HR総研の企業調査では、どの企業規模でも、直面している課題の断トツは「次世代リーダー育成」だ。
さらにここ数年、優秀な若手が安定した大手企業から去り、スタートアップ企業に流れる傾向にある。
20年も会社に奉仕した挙げ句に大した給与も貰えずに苦労ばかりする大手企業より、同年代の仲間たちと切磋琢磨できるスタートアップ企業のほうが魅力的に思えるのも無理はない。

命を削る管理職たち
「日本では一般職よりも管理職のほうが死亡率が高い」──。
英国の疫学・公衆衛生専門誌は2019年、この衝撃的な結果を発表した。欧米では一般的に、管理職や専門職の死亡率は他の職種に比べて低くなる。経済的な余裕のある管理職や専門職は、健康に時間やお金を投資できるからだろう。
一方、日本では全く逆の結果が示されたのだ。「一般職よりも管理職のほうが死亡率が高い」傾向は1990年代後半から強くなり、特に「自殺」による死亡が増えたと言われている。
管理職の「罰ゲーム化」という現象は、「苦労するね」「大変だね」程度で示されるものではなく、人生を丸ごと狂わせるレベルのダメージを生むのだ。
ここで強調したいのは、管理職の悲惨な状況は、環境問題や貧困問題のような社会的イシューとしての「わかりやすさ」や「共感されやすさ」を帯びていないということだ。
多くの管理職は、組織の序列では上位に位置しているし、賃金も多いため、管理職の負荷は強い関心や共感を得られにくいのだ。
一方の管理職も、そうした状況に沈黙している。プライドが邪魔をする、組合員でないから労働組合には相談できない、家族や部下を守るため……様々な理由により、声を上げることなく孤独に戦い続けているのである。
【必読ポイント】
「罰ゲーム化」を修正する4つの方法
陥りがちな改善の「罠」
管理職の「罰ゲーム化」を修正する方法を紹介する前に、企業が陥りがちな罠、つまり間違った対処法を見ていこう。
それは「管理職の負荷が高いのは、管理職自身のマネジメント・スキルが足りないからだ」という発想だ。
この発想のもと、経営者や人事部門は「マネジャーたちにスキルを身につけさせよ」「やる気を出させよ」「エンゲージメントを高めよ」と、研修トレーニングのメニューを見直したり追加したりする。これを著者は、マネジメント課題の「筋トレ発想」と呼ぶ。
リーダーシップへの期待偏重による「筋トレ発想」が組織全体に広がると、研修は増え、管理職の負担は増すばかりだ。そして昇進のハードルはますます上がり、メンバー層は誰も管理職になりたがらない。まさに逆効果なのである。

フォロワーシップ・アプローチ
続いて、管理職の「罰ゲーム化」を修正するための4つのアプローチを紹介する。
1つ目の「フォロワーシップ・アプローチ」とは、管理職の部下、つまりフォロワーであるメンバー層へのトレーニングを増やすアプローチだ。
トレーニングの対象は、ITスキルのようなオペレーショナルなスキルではなく、対人関係やコミュニケーションといった、管理職の頭を悩ませていた「ピープル・マネジメント」の領域だ。
たとえば、企業側が管理職に「部下へのフィードバックが大事だ」と指導し、管理職がフィードバックに努めても、メンバーにフィードバックを受ける気が無ければ何も改善しない。
管理職が「自分のフィードバックの仕方が悪いのだ」と自身を責め、ストレスを溜めるだけだ。そのような事態に陥らないよう、まずはメンバーに対して、フィードバックを適切に受け取るトレーニングを受けさせる必要がある。
ポイントは、メンバー層のトレーニングを通して、両者を「同じ土俵に立たせる」ことだ。キャッチボールで両プレイヤーのスキルや呼吸、テンポを「揃える」ことが大切なように、両者のトレーニングを通して、管理職と部下の目線や情報を合わせていく。
「フォロワーシップ・アプローチ」の取り組み方は、4つのステップでまとめられる。
ステップ1では、トレーニングの「偏り」を認識する。実施している管理職向け研修やトレーニングを書き出し、対人コミュニケーションに関わるものを数えよう。
ステップ2では、メンバー層へ育成内容を「見える化」する。ここではまず「管理職に対してどういった研修を行っているか」をメンバー層に共有しよう。
対象者だけが知っていればいいという「管理職トレーニングのブラックボックス化」が、同じ土俵でのコミュニケーションを遠ざけている。

ステップ3では、メンバー層へ簡素化したトレーニングを提供する。軽く、コストをかけずに、管理職と同様の内容を伝えよう。社員会や定例会議といった場を活用してもいいかもしれない。
ステップ4では、メンバー層に同様の内容を教える。きちんと時間をとり、管理職向けのトレーニングとは別のトレーニングを設計しよう。
「フォロワーシップ・アプローチ」のポイントは、「知っていることを・知っている」状態をつくることだ。つまり、管理職とメンバー層に同様の内容を教えるだけではなく、「教えているということを、教える」ことが重要になる。
ワークシェアリング・アプローチ
2つ目は「ワークシェアリング・アプローチ」だ。管理職の役割を変更したり共有したりすることで、全体の役割や業務量を調整していく。
ワークシェアリング・アプローチは3つの軸から成る。
1つ目の軸は「ベース施策」だ。これは現状把握(管理職の労働時間・役割の把握)→組織構造・フラット化の見直し(部下人数の変更・ポスト増設)→働き方改革のアップデート(効率化・生産性向上・アウトソーシング)の順に進める。
2つ目の軸は「デリゲーション施策」だ。下位管理職への公的な権限付与、承認プロセスの省略、タテの分業の明確化がここに該当する。
3つ目の軸は「エンパワーメント施策」だ。メンバー層へのインフォーマルな役割分担・育成機会の付与と、それを可能にする管理職研修を行う。
ネットワーク・アプローチ
3つ目は「ネットワーク・アプローチ」だ。管理職同士のネットワークを構築し、社内に相談し合える相手がいる状態をつくる。
「ネットワーク・アプローチ」は3つのタイプに分けられる。
1つ目は、管理職同士の横のつながりを創る「水平型」のネットワーク施策だ。
マネジャー合宿や部横断のマネジメント・ワークショップ、管理職研修後の懇談・懇親会などが挙げられる。
会社の規模が大きいと、マネジャーという共通点だけでは自発的に集まらないので、「女性マネジャー」「部下育成に悩むマネジャー」「営業部署の管理職」などとブレイクダウンするといいだろう。
2つ目は、管理職同士の縦のつながりを創る「垂直型」のネットワーク施策だ。
上位管理職とのつながりが深くなると、昇進意欲の向上やコミュニケーションの円滑化が期待できる。役員によるメンタリング、経営者のかばん持ち、人の紹介・ランチ会や懇親会の開催などが代表例だ。
3つ目は、社外とのつながりを創る「越境型」のネットワーク施策だ。NPOのサポート支援活動や社外研修、大学院での学びのサポート、外部カウンセリングへの接続、社外副業の解禁、他社との相互出向、他流試合型の研修やトレーニングなどが挙げられる。
キャリア・アプローチ
4つ目の「キャリア・アプローチ」は、会社の昇進構造や選抜の在り方を変更するものだ。このアプローチには、2つのポイントがある。
1つ目は、次世代リーダーの候補層を早期に絞り込み、特別な育成やトレーニングを計画的に実施していく「健全なえこひいき」である。優秀な若手に会社からの期待を自覚させ、離職防止につなげよう。
2つ目は「非候補管理職のスペシャリスト化」だ。次世代リーダー候補者以外に関しては、ジョブ・ローテーションの範囲を狭め、専門領域の管理職としてのキャリアへとシフトさせる。

「非・マネジメント職」という消極的なポジションではなく「一定範囲のマネジメントができるスペシャリスト」として育成し、職務別・領域別の研修・訓練を充実させるのがポイントだ。
これなら、特定領域のスペシャリストとしての意識が育ち、転職市場でも評価される人材になれる。
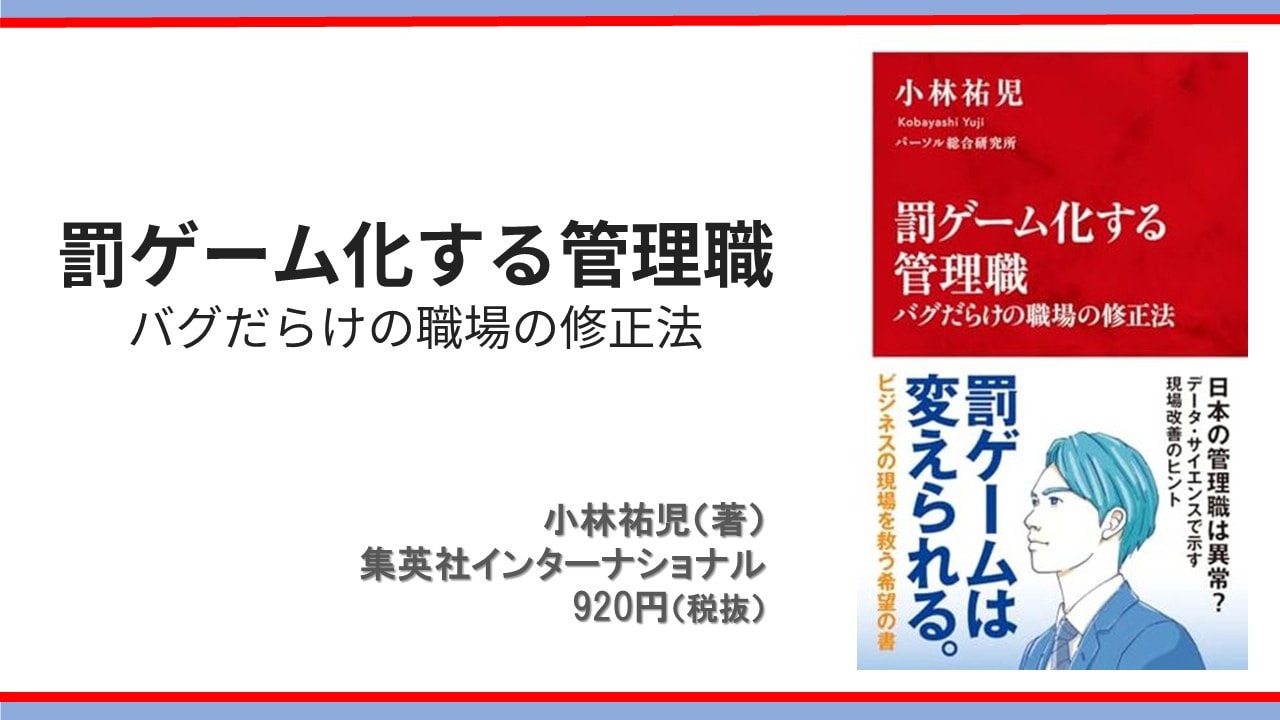
(インターナショナル新書) | 小林 祐児 |本 | 通販 | Amazon
この記事はNTTドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。
編集:NewsPicks +d編集部








 JP
JP