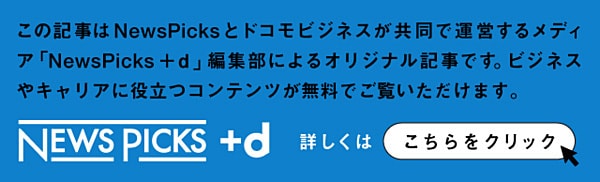これまでの連載では、よりよいチームにするうえで効果的な、「自分自身のコミュニケーションを見直す」「相手をアクノレッジメントする」「相手の話を聞く」「相手に問いかける」というテーマを、それぞれ深掘りしてお伝えしてきました。
しかし、メンバーの行動を促進するためには、ときに相手に要望したり、提案したり、ときにネガティブな状況にある人に伝えるべきことを表現する必要もあります。
この回では「提案」「要望」「アサーティブネス」という手法に触れながら、メンバーたちの目標に向けた行動を促進するためのかかわり方をご紹介します。
行動の選択肢を広げるための「提案」
部下にとって上司からの「提案」は、自ら考えて自ら行動するための選択肢を広げるヒントになります。一方で、それが「上司から押しつけられたもの」と感じると、素直に受けとりにくいものですし、相手に考える余地を与えないような提供のされ方では、受け手は拒否反応を起こします。
「提案」はあくまで、相手が新たな視点を持ち、行動の選択肢を広げるために行います。そのためには「提案のタイミング」が大切です。
「どうしたらいいでしょうか?」と相手から質問を受けたとき、私たちはつい、「こうすればいいのでは?」とすぐに提案してしまうことがあります。それは決して適切なタイミングだとはいえません。

まずは相手の考えを言語化するために、さまざまな角度から「問いを投げかける」 のが先です。そのうえで、新しい視点が必要だと感じられたとき、また、彼らがそれを強く求めたときこそが「提案」のタイミングです。
また、タイミングのほかにも、提案を伝えるときに気をつけるべきことがあります。ここでは、5つ紹介します。
【1】Yes/No の選択権は相手にある
あなたの提案に対して、それを受けとったあと、それを採用するか否か、行動するかしないかという選択権は常に相手にあります。相手に選択権を与えていない場合、それは「提案」ではなく、「指示・命令」になります。
【2】許可をとってから提案する
提案を求めるか、求めないかの選択権は相手にあります。
「ひとつ提案してもいいですか?」
このひと言で、相手は「聞く耳」を持ちます。一方で、相手は「もう少し自分で考えたい」、もしくは「もっと問いかけてほしい」と望んでいる可能性もあります。その場合は、その要望に沿う必要があります。
【3】提案は1回に1つと決める
一度に多くのことを意識することは、誰しも困難を伴うものです。相手に選択肢を数多く提供しようとするあまり、かえって混乱を生み出すことのないよう、「提案は1回につき1つ」がよいでしょう。
【4】内容はコンパクトかつ、イメージしやすく伝える
抽象的な表現や、回りくどい表現、あるいは長々と続く提案は、受けとる相手にとっては何をどうしていいのかイメージしにくいものです。提案はコンパクトに、そしてイメージしやすく伝えるのが効果的です。
【5】正論ではなく、ストーリーで伝える
自分の提案に自信があればあるほど、人は力が入り、「ふつうはこうするものだ」「これがあたりまえ」といった正論的な伝え方になりがちです。そして、「確かにそうかもしれませんが、私は……」など、相手の拒否反応を生み出しがちです。
相手の可能性をひらく「要望」
上司からの「要望」は、部下の飛躍的な成長に役立ちます。人は自分の思考や行動に対して、無意識のうちに「私のできることはここまで」といった枠を設けてしまいがちです。たとえば、「この書類を仕上げるのに1週間かかる」と思っている人に、「3日で仕上げてほしい」とリクエストする。それによって、相手がそれまでとらなかった手順を試みるかもしれませんし、他人の援助を求めるかもしれません。
このように、これまであまり試したことのない、相手の可能性をひらき、無意識に作っている枠の外に相手を連れていくためにも、上司はリスクを超えて相手に要望することが求められます。
 (写真:mapo / gettyimages)
(写真:mapo / gettyimages)
ここでいう要望とは、「こうしなさい」という命令形ではありません。「私はあなたに〇〇してほしい」と“Iメッセージ”(「私」を主語にして意思を伝える技法)で伝えるのが要望です。「受け入れられないかもしれない」「相手から別の要望がくるかもしれない」といったリスクを抱えながら行う行為です。そこには、お互いの信頼関係や、理解度などが映し出されてきます。
それだけに、相手に届くような、理解を得られるような伝え方を身につける必要があります。次に、要望の効果的な伝え方と注意点を見ていきます。
【1】ストレートに短く伝える
自分の要望を断られたくないがために、長い前置きや、遠回しな表現をすることは避けます。かえって相手を混乱させたり、不快にさせたりする原因になっていることがあります。人は、何を望まれているかはっきりとわかったほうが、判断しやすいものです。
【2】相手に対する期待感を込めて伝える
要望はそもそも相手への期待感があるからこそ行うものです。期待がかなった先の姿をイメージして伝えるのがポイントです。命令口調やこびるような言い方では、相手のモチベーションは上がらないでしょう。
【3】「要望」と「アクノレッジメント」はセットで使う
特に、相手に行動の改善や修正を要望する場合、「ここがダメだからこうしてほしい。ここを直してほしい」という伝え方では、相手もあまり前向きな気持ちになれません。できていることへのアクノレッジメントとセットにすると、相手のやる気を刺激することができ効果的です。
【4】必要であれば、何度でも繰り返す
一度要望しただけで、相手の行動ががらりと変わることはまれです。あなたが望んでいることの強さや深さを理解してもらうためにも、繰り返しメッセージを送り続ける必要があります。
ネガティブな相手にもうまく伝える
「アサーティブネス」
あなたは自分が思っていることや、言うべきことを、うまく他者に伝えられていますか?
- 部下が感情的になって、ネガティブな表現ばかりを使う
- 上司が高圧的に指示・命令を出してくる
- 社員が期日を守らなかったり、マナー違反をしたりする
リーダーは、このような相手の態度や状況であっても、それに影響されることなくコミュニケーションをとる必要があり、そのようなスキルを「アサーティブネス(assertiveness)」(相手を尊重しながら自分の意見や要望を伝える技法)といいます。
アサーティブネスについては、多様な人種のなかで、個人の自己主張が求められる北米の文化的な背景が、このスキルの進化を支えてきたといわれています。一方で日本では、伝統的に「相手のことを尊重する」習慣が大切にされてきたためか、「自己主張する」というと「わがまま」とか「自分勝手」ととらえられることがまだまだ多いようです。
しかし、自己主張しないことで人はときに、何かの可能性をあきらめたり、人のせいにしたりしてしまいますし、相手にとっても「本当に必要なこと」(ときには受け入れがたいようなことであっても)に気づかないままとなってしまいます。

もちろん、むやみやたらに自己主張をすればよいというわけではありません。
自己主張には① 攻撃的(アグレッシブ)、② 受け身的(パッシブ)、③ アサーティブの3つのスタイルがあると言われています。アサーティブではない場合、①か②のスタイルをとることになりますが、自分の主張ばかりを通していては、相手の意に沿わないことを強制したり、言い負かしたりすることにつながってしまい、信頼を失うことにもなりかねません。
たとえば、大きなプロジェクトの締め切りを3日後に控え、毎日、夜遅くまで仕事をしているとき、上司が、緊急のリポートを仕上げるように急に依頼してきました。あなたがとる態度は以下のうちどれに近いでしょうか。
① 攻撃的(アグレッシブ)
「私の状況がわからないんですか !? 他の人に頼んでください!」
このスタイルをとる人は、自分の主張を通すことに抵抗がなく、ときに感情的になりがちです。また、人のことよりも先に自分のことを考える傾向があり、自分の立場を守ることを優先しがちです。
② 受け身的(パッシブ)
「えっ……あ、はい。わかりました」
このスタイルをとる人は、自分の主張や感情はめったに表現しませんし、意見を聞かれてもはっきりとは答えません。人のことを優先して自分のやりたいことは後回しにするため、いつも周囲の都合のいいように動かされていると感じ、ストレスが高い傾向にあります。
③ アサーティブ
「いまは別のプロジェクトがあって手が回りません。ほかにできる方に依頼しましょうか」
このスタイルをとる人は、自分の伝えたいことと感情を切り離して理解しており、自分自身の主張や、必要であれば感情も率直に伝えます。物事には常にいくつかの選択肢があることを知っていて、そのなかから選ぶというスタンスをとることができる。結果に対しての責任は自分自身にあると考えている。常に自分と相手の両方にとって有益な手段を検討します。
今回は、「提案」「要望」「アサーティブネス」について紹介しました。
皆さんは、自分が望んでいることや考えていることを端的に伝えて、相手に望ましい行動を促す能力はどれくらい高いでしょうか?
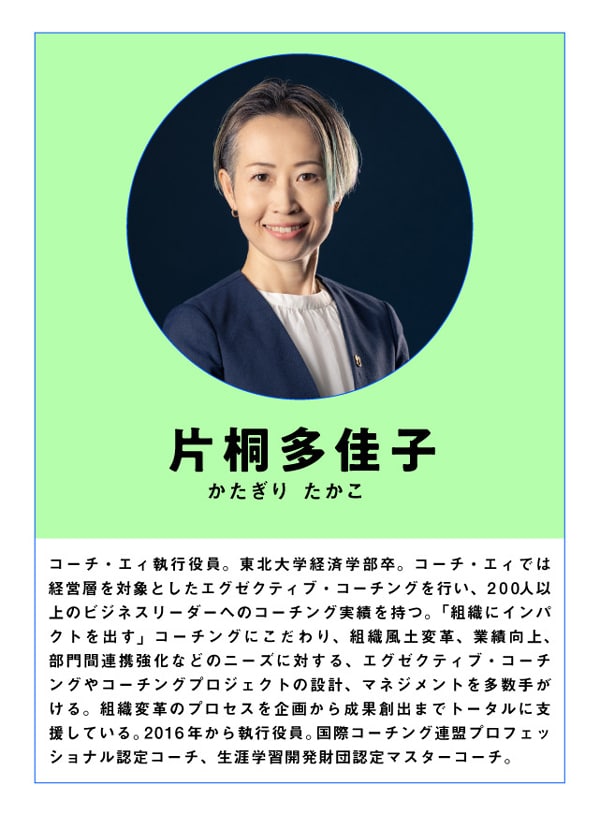
この記事はドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。
文:片桐多佳子
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:鈴木毅(POWER NEWS)








 JP
JP