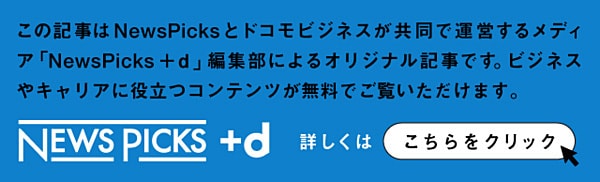今も色あせない「新選組」の魅力とは
日本史上、もっとも人気のある団体。それはきっと「新選組」ではないでしょうか。この組織については、これまで小説、マンガ、ゲーム、ドラマなどおびただしい作品がつくられ、今も発表されています。
その人気は衰えるどころか、むしろどんどん高まっているように感じます。
考えてみれば不思議なことです。「新選組」は幕末に現れた集団。もとは正規の行政組織ではなく大策士、清河八郎の「江戸市中の浪士を京都に送りこみ、治安維持に当たらせよう」という献策によって誕生した、一種のNPO団体でした。
現代でいえば、政情不安となり都の治安が悪化。警察だけでは秩序が維持できず「腕っぷしの強い者たちを集めて市中を巡回させようとした」という感じでしょうか。

「フラフラしている者に職を与え、同時に治安を守らせる」。うまくいけば一石二鳥の計画だったわけです。
清河の案に乗った幕府は江戸に募集をかけ浪士を集めます。当時はずいぶんと怪しげな人材もいましたが、緩いグループが組織され京都に送りこまれました。
しかしそこで清河が正体を表し、浪士集団を彼の私兵にしようとする。その際「清河に従わず京都に残留したグループが、新選組の基礎になった」というエピソードは有名です。
残留グループは京都守護職会津藩の「お預かり」となり、京都の治安維持活動に従事することになりました。ちなみに似た組織として、こちらは旗本の次男三男が集められた「京都見廻組」があります。
もとは非正規の浪士。行政から業務委託を受けているとはいえ、いわばフリーランスの団体だった新選組ですが、「池田屋事件」をきっかけに一気にその名を高めます。
やがて隊士たちは幕臣に取り立てられ、堂々たる正規の武士へとソーシャルクライミングを果たしていきました。
しかしその栄光もはかなく、歴史上では彼らは「負け組」。幕府の運命に殉じて滅びていくことになります。

エリート剣客集団のブラックな内部規律
もっとも「男には負けるとわかっていても戦わなければならない時がある」。時勢を見て風見鶏のように動くのではなく、節義に従い散っていったその運命こそが、人々にロマンを感じさせ、今も人気となっているのでしょう。
それになんといっても彼らにはキャラの立ったスターがいました。万夫不当の豪傑、近藤勇、薄命の天才剣士、沖田総司。そして「鬼の副長」の土方歳三。
彼らだけではなくマンガ『るろうに剣心』の主要キャラクターとなった斎藤一もいますし、浅田次郎さんの『壬生義士伝』の主人公になった吉村貫一郎のような、味のある隊士もいました。とにかくタレントが豊富で人気があるのも当然です。
入隊すれば、正規武士への道が開けるし、人気者にもなれる。ですが、筆者には圧倒的な確信があります。
エリート剣客集団で入隊には厳しい審査があったようですが、もし自分がなにかの間違いで所属してしまったとしたら? 「きっと命を全うすることはできなかった」という確信があります。

筆者のようなヘタレはまず間違いなく、どこかで粛清されてしまったことでしょう。
新選組とは、それほど厳しい規律を持つ集団。その「社則」(一般に「局中法度書」と呼ばれます)はシンプルですが、それだけにハードです。
第一 士道に背くこと
第二 局を脱すること
第三 勝手に金策すること
第四 勝手に訴訟をとりあつかうこと
この四カ条をやれば切腹(『新撰組顚末記』永倉新八)。
特に「士道に背くこと」が厳しい。要するに「ひきょうな振る舞いを見せたらNG」というわけで、現場でビビって「あいつは臆病だ」という評判が立つと、切腹。その切腹が怖くて退職しようとしても、それはそれで切腹。
当時は退職代行サービスなどもちろんありませんし、脱走しても追われる身となり、見つけ出されて殺されます。要するに所属したら、死ぬ以外脱退できないわけです。

現代でも、退職しようとしてもなかなか辞めさせてくれない会社もあるようですが、ブラックといえば、これほどブラックな職場はなかなかない。
事実、新選組では闘死や病死より、粛清されてしまった人のほうがはるかに多いのだそうです。実に40人もの隊士が、始末されてしまっている(『新選組 粛清の組織論』菊地明)。
もちろん定職につかずウロウロしていた、いわば烏合の衆を集めて発足した組織ですから、それを束ねていくためには厳しい規律が必要だったことでしょう。
まして新選組は「武闘派集団」。「日和ってるやついる? いねえよなぁ!!?」ということで、ビビった隊士が消されるのも無理はないのかもしれません。
ただ新選組では、隊士だけではなく幹部も粛清されてきました。初期には芹沢鴨の一派。そして結成以来の同志である山南敬助も粛清され、後には分派した御陵衛士のリーダー、伊東甲子太郎も暗殺されています。
要するにその歴史は、血塗られた内部抗争の歴史だったともいえます。そうしたハードな組織の中で生き延びていく自信は、筆者にはかけらもありません。
「業務でミスをすると切腹」「プライベートで不祥事があっても切腹」「退職を申し出ると切腹」。

まさに「こんな上司は嫌だ」と言いたくなりますが、こうした組織をつくりあげ、そして運営してきた人物。それが「鬼の副長」こと、土方歳三です。
「鬼の副長」土方歳三の実像とは
この人は武州多摩郡日野郷石田村の生まれ。現在の東京都日野市で、日野にある高幡不動尊は彼の家の菩提寺だったそうです。
家は代々の武士ではなく農家。しかし彼は少年のころから武士を志していました。
成長して天然理心流に入門し、非正規ながら士装も行うようになるのですが、「もともと武士出身ではなかったからこそ、ふつうの武士以上に、ピュアに武士道を追求した」とは、この人についてよく語られるイメージです。
そのイメージのルーツはおそらく司馬遼太郎氏の小説『燃えよ剣』でしょう。この小説では彼は剣技に優れ、野戦指揮官としても抜群の能力を発揮。
しかしなにより「組織のつくり手」、オルガナイザーとしての才能を持ち、新選組はそうした彼の「作品」だった。個人としては武士としての節義に生きて、滅びゆく幕府のために最後まで戦い続けたロマンティックな人物として描かれます。

この土方像は現在に至るまで決定的な影響を与えますが、同じ司馬遼太郎さんの小説でも連作集『新選組血風録』のほうでは、やや違う。陰のある「リアリスト」のニュアンスが出てきます。たとえば非主流派の目線として、
かれは、新選組が隊内の粛清をするとき、武士ならば考えられもしない奸計をもって実行することを知りぬいていた。これは近藤、土方が根からの武家そだちではないせいだと泰之進はみている。 (『新選組血風録』「油小路の決闘」)
といった言及も見られる。
そういえば、新選組の闘法として、常に3人一組で相手に向かう、というシステムが有名です。「一対一で戦う」といった“潔い姿勢”はそこにはありません。
土方が最後まで戦い続けたことについても、治安維持に従事した新選組は維新勢力の恨みを買っていて、近藤勇の運命が示しているように「投降しても絶対に許されないので、戦うしかなかった」とみることもできます。
「やっぱりブラックか! かんべんしてくれ!」と感じるところです。
では土方歳三は、ただの武士に憧れただけの人で「根は多摩地区のヤンキー」だったのかというと、そうとも言えないと思います。
「ホワイト武士道」で“勝つ”ことが正義
進退は潔く、多人数で相手を襲うようなひきょうな手を使わないといった「ホワイト武士道」は、実は伝統的な武士の美学ではありません。
実はこれは「戦い」がファンタジーとなった江戸時代に生まれ、幕末から明治にかけて西洋技術文明と対峙したときに「しかし俺たちには武士道と大和魂がある!」といったかたちで共有されるようになった、まさに「精神論」でした。

もともと武士とは、ぶっちゃけブラック。どんな手を使ってでも勝つことが正義。
これは歴史研究者の西股総生氏が指摘されていることですが、たとえば戦国武将の朝倉教景は、
「武士は犬ともいえ、畜生ともいえ、勝つことが本にて候」 (『戦国の軍隊』)
という言葉を残しているそうです。
ひきょうな手を使って犬と呼ばれようとも、勝つことがすべて。
逆にいえば、戦って勝つ者こそが武士。かたちだけ武士でも、勝てない者は武士ではないのです。
その意味では、目的遂行のためにどんな手でも使い、「刀は武士の魂」といった精神論にとらわれることなく、柔軟に西洋の組織や兵器を取り入れた土方こそが「ガチの武士」だったといえるでしょう。
もっともいざ自分が働くのであれば「どんな手を使ってでも勝て」(しかも女性にはモテモテで男性社員にはめっちゃ厳しい)という上司よりも、「きちんとコンプライアンスに従って働いてね」という上司の下で働きたい。
筆者のような者はそう感じてしまうのですが。
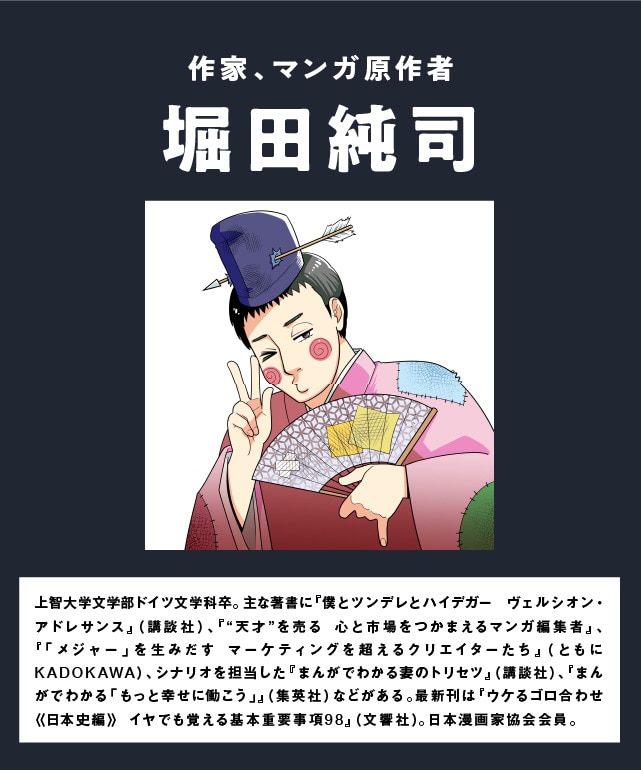
この記事はNTTドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。
執筆:堀田純司
イラスト:瀬川サユリ
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:奈良岡崇子








 JP
JP