 People/Career
People/Career
NTTコミュニケーションズ
ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部
池田 真実子

新規ビジネスの創出や社会実装を
目指す事業共創の場です
産業・地域DXプラットフォーマーとして
企業と地域が持続成長する社会を目指します
地域社会を支える皆さまと地域課題の解決や
地域経済のさらなる活性化に取り組みます
旬な話題やお役立ち資料などDXの課題を解決するヒントをお届けする記事サイト
課題やニーズに合ったサービスをご紹介し、
中堅中小企業のビジネスをサポート!
モバイル・ICTサービスをオンラインで
相談・申し込みができるバーチャルショップ

安斎長人さん
実の親が子どもを育てられない事情があるとき、親権を移すことなく、子どもを一時的に預かって育てる「養育里親」という制度がある。児童養護施設での集団生活よりも子どもの成育過程で重要な愛着形成がしやすいと期待され、厚生労働省が推進している制度だ。
当社は、自身のキャリアやライフプランをどう考えればいいかを学ぶ「キャリアデザイン研修」を行っており、それをきっかけに50代で里親になった社員がいる。NTTドコモビジネス 第五ビジネスソリューション部の安斎長人さんだ。
里子との新しい日々について話を伺った前回記事は大きな反響を呼んだが、その後、子どもとお別れの日を迎えることになった。安斎さんはその時、どんなことを感じたのか? 今回改めて思いを語っていただいた。
■前回の記事:
50代で里親に、仲間のサポートもあり喜びいっぱいの日々を送る
NTT Comの「キャリアデザイン研修」で新しい人生へこぎ出した安斎 長人さん
※NTTコミュニケーションズはNTTドコモビジネスに社名を変更しました
子どもを預かって約1年。養育にも慣れてきて、子どもとの距離感が日々近くなっていることを実感したころ、児童相談所から1本の電話があった。実親との再統合(実の親と子どもが再び一緒に暮らすこと)に向けたミーティングの依頼で、電話から半年後に引き渡しする目標となった。
ついにその日がやって来たのだ。何とも言えない気持ちになった。
子どもにとって「幸せな暮らし」って何だろう? 子どもを「安心して実の親に帰すために」何ができるだろう? 私たちにとっての「家族」って何だろう? 里子を養育した時間は、児童相談所を中心としたワンチームで、それぞれの立場で「子どもの幸せ」を真剣に考えた期間であった。人生の中でこんなにいろんな感情を持ったのは、初めてかもしれない。
お別れまでの私たち家族の気持ちを書いてみる。

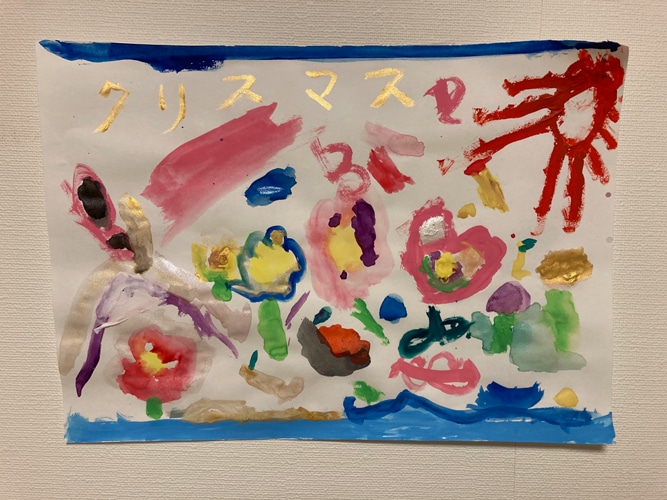
子どもがわが家に来たばかりのころに、「ママに会いたい。私って、誰の子ども?」と尋ねられ、思わず耳を疑った。3歳半という幼い子どもながらに、本音で話し掛けてくれたことを覚えている。私は、子どもと2人で泣いた。子どもには、思わず「ママのところに絶対帰れるから」と言ってしまったが、実親の元に子どもが帰ることができるのか、実際は何の根拠もなかった。親元に帰った場合は、子どもと私たちはその後原則会えないので複雑な気持ちになる。
複雑な心境から始まった子どもとの生活だったが、毎日楽しかった。幼稚園に子どもを迎えに行くのが私の日課。子どもは、寄り道をしたがって、なかなか真っ直ぐ帰宅させてくれなかった。お店に立ち寄ると「抱っこ抱っこ」とせがんでくる。子どもの要望は、とにかく全て受け入れた。子どもの心に寄り添うことで、私たちへの愛着が少しずつ形成されていったのかもしれない。私たちはいつしか、この子を親元に返しても本当に幸せになれるだろうか、という気持ちになっていた。
そんな中、子どもが来てから初めて実親と子どもの面会があった。面会は児童相談所で行う。私たちは、子どもの実親とは会えないので、面会の間は別の部屋で待機する。面会に送り出すとき、子どもはなかなか私たちの手を離してくれなかった。「行っておいで」と、声を掛けるが、行こうとしない。児童相談所の方にも促されて、子どもはようやく実親との面会に向かった。この姿は、わが家にはじめて来たときに、なかなか玄関から先に入らなかった子どもの様子と同じだと感じた。
この日は結局、子どもは一言も話さず、実親の話に相づちを打っただけだったらしい。その話を聞いて、私は驚いた。実親と再会したら、すぐに「お母さん、お父さん」と抱き合うのを想定していたからだ。この行動は、実親の愛を試しているのではないか、と思った。
この面会の後も、実親は何度も子どもに会いに来てくれた。会いに来なくなってしまう親もいるらしい。何度も子どもに会いに来てくれることはうれしいことだが、子どもとの別れを思うと複雑な気持ちになる。
親子の面会は15回行った。面会のたびに、子どもは心を乱して帰って来た。そして、私たちに愛を確かめるような行動をする。抱っこをせがむ回数や、お菓子を欲しがる回数が面会を重ねるごとに増え、激しくなったような気がした。面会前後の子どもの状態を児童相談所に報告するのも里親の重要な任務だ。子どもと向き合い、子どもの望むままにどんなことでもしたが、このときは養育がつらいと本気で思った。
再統合の話が出てから、子どもとの思い出づくりのために、たくさん旅行に行った。沖縄やディズニーランド、サンリオピューロランド。行く先々で、この子とはもうここには来ることはできないだろうなあと考えてしまい、涙が出てしまった。それでも、一日一日を楽しむしかないと、精いっぱい子どもと向き合った。


何度も面会を重ね、子どもが実親の元に初めてお泊りに行くことになった。待ち遠しかったらしく「あと何回寝るとママに会える?」と言われた。いつも以上にはじけている様子で、なかなか歯磨きしようとしない、寝ようとしない、外食をせがむ、食べたくないものは絶対食べない。そして、「私にはママが2人いる」「まるちゃん(妻)をママにしてあげる」などと言って、私たちをドキドキさせる。そんなことを言われたら、涙が出てくる。
3回目のお泊りのころには、初めての面会のときのような行きたくないというそぶりは見せず、私たちの手をすんなりと離すようになっていた。里親心としては、なんか寂しい。実親の元に戻るとき、子どもの実親への愛着の再形成が必要となるという。その初めの一歩が踏み出せた瞬間だったのかもしれない。

子どもの荷造り
お泊りの間は里親にとってつかの間の休息となるが、結局妻とは子どものことばかり話していた。子どもが帰ってくると何もできなくなるのでお泊りの間を利用して、少しずつ実親の元へ戻るときの荷造りをした。一緒に寝ていたぬいぐるみ、幼稚園で作成した作品、七五三アルバム、お気に入りの服などを詰めていく。何を持って行かせようか、妻と一緒にたくさん考えた。子どもが将来振り返ったときに、思い出になりそうなものを選んだ。
それから子どもと私たちの思い出を紙芝居にした。私たちの家に来て、幼稚園に行って友達と遊んで、一緒に生活した様子を絵に描いた。絵と一緒に、思い出の写真を切り抜いて貼った。実親との合作だ。将来、どんな気持ちで見てくれるのだろうか。これを見て、わが家にまた来たいと思ってくれたらうれしいなあ、なんて考えた。
実親の元に帰るまでの最後の3日間は、ゴールデンウイークの谷間だった。子どもは帰ることへの喜びの一方で、私たちとの生活を惜しんでいるような様子を見せた。実親の元に帰るとはいえ、子どもにも不安はあるはず。小さい子どもながらに頑張っていたのではないかと思う。そんな子どもを、心から守りたいと思った。
子どもとの最後のお別れの場所は児童相談所だった。実親の向かいの部屋に私たちはいて、子どもとの最後の時間を過ごした。子どもは、いつもよりテンションが高かったような気がする。即席で作った手書きビンゴをやったり、昔の写真を一緒に見たり、踊ったりした。子どもは、妻の頬に自分の顔をすり寄せてきた。それを見て、私たちはやっぱり家族なのだと思った。その後子どもは、私たちを振り返ることなく、実親の部屋に入って行った。里親の私たちから実親にバトンタッチした瞬間だった。
子どもがいない2人だけの生活に戻ると、子どもが居なくなってしまった寂りょう感や無事に送り出せた安堵(あんど)感、やり遂げた達成感など、これまでに味わったことがない感情がたくさん心をよぎった。残された子どもの荷物や写真の整理はとてもつらい。里親として分かっていたこととはいえ、すぐには心の整理がつかなかった。徐々に現実を受け入れていくしかない。
私たちは、子どもを養育している間にたくさんの方々から応援と励ましを頂いた。それが間接的に子どもを応援してもらうことになり、その結果養育ができたのだと思っている。だから、子どもは“社会の子”だと、私たちは常々思っている。
そして、今回の経験を生かして、里親制度を社会に正しく伝えていくことが大事だと思った。里親=養子縁組のイメージがあるが、実際の里親の目標は、「子どもと実親が再び一緒に暮らすこと」である。そして子どもと里親と実親の間に入って、調整をするのが、児童福祉司(ケースワーカー)だ。同じゴールに向かって、常に子ども視点に立って、里親と実親をまとめていかなければならない、大変な仕事だ。
社会的養護の必要な子どもたちには、実親はもちろんのこと、一人でも多くの特定の大人(例えば里親)との永続的な信頼関係づくりが重要だといわれる。人を頼ることを知らないで育った子どもは、社会に出ても誰も頼ることができないからだ。家庭の養育支援まで、里親の守備範囲を広げて、社会全体で見守っていく環境ができたらいいなと、私たちは願っている。
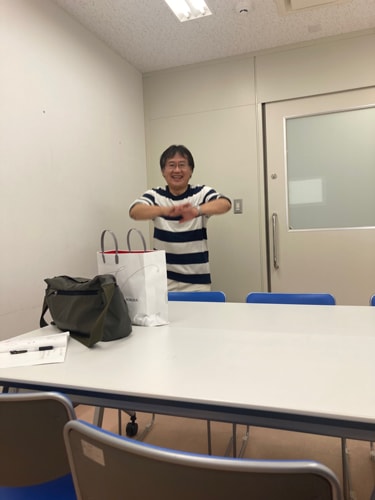


NTTドコモビジネス第五ビジネスソリューション部 ビジネスデザイン部門
安斎 長人
第五ビジネスソリューション部 ビジネスデザイン部門 第1グループでは、SIerと外資とネット/ISPのお客さまの収益拡大をミッションに、法人営業の提案支援業務を行っております。提案商材の関係部署のコーディネートをする提案マネジメント、提案内容のデザイン、お客さま打ち合わせのファシリテートなどが主な業務です。
 People/Career
People/Career
NTTコミュニケーションズ
ビジネスソリューション本部 第三ビジネスソリューション部
池田 真実子

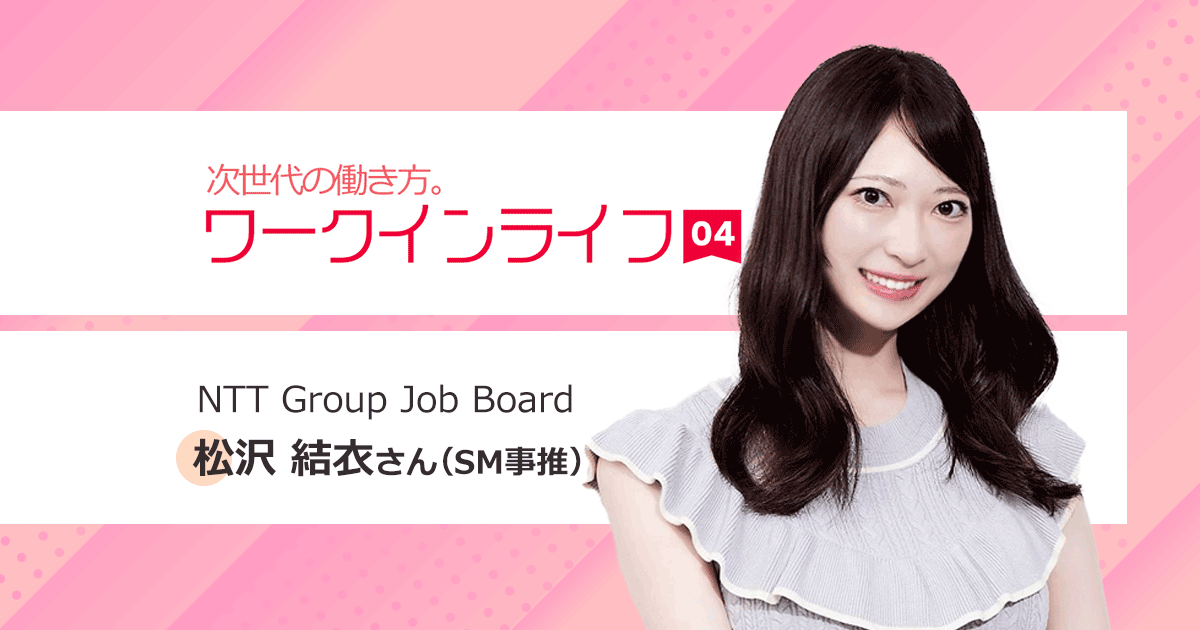 People/Career
People/Career
NTTコミュニケーションズ
ソリューション&マーケティング本部 事業推進部
松沢 結衣

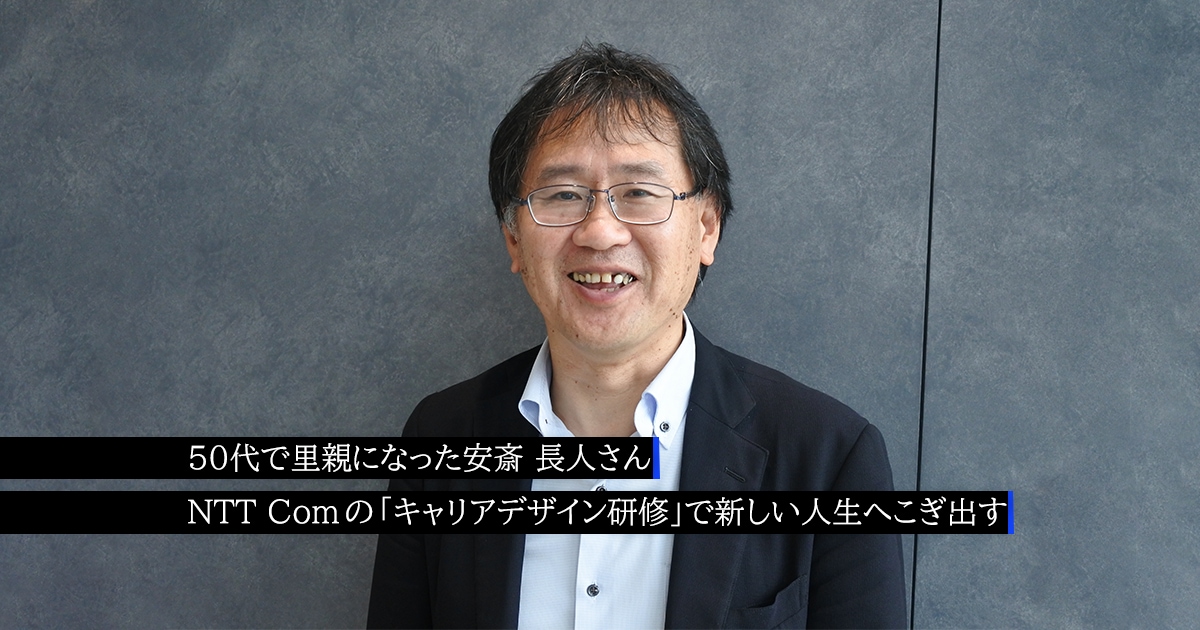 People/Career
People/Career
NTTドコモビジネス
第五ビジネスソリューション部 ビジネスデザイン部門
安斎 長人


 JP
JP
