交通費計算は通勤交通費と旅費交通費と何が違う?計算方法を解説

公開日:2023/7/25
会社の業務によっては、日々の通勤や出張時などに交通費が発生します。通勤時の交通費と旅費交通費とでは扱いが異なるため、注意が必要です。経理担当者としても違いを把握し、間違わずに処理しなければなりません。
本記事では、交通費計算について支給方法や限度額などについてわかりやすく解説します。交通費計算を楽にするための方法についてもふれていくため、交通費の扱いや計算方法について参考にしてみましょう。
目次
交通費とは
電車・飛行機・タクシーなどを移動に利用した際にかかる費用は交通費と呼ばれ、交通費には、通勤交通費と旅費交通費の2種類があります。
それぞれの違いについて詳しくみていきましょう。
通勤交通費
自宅から勤務地までの通勤時にかかる費用を指します。電車・バスなどの公共交通料金だけでなく、自家用車で通勤する際のガソリン代を含みます。
通勤交通費の支払いに法的な義務はありません。ただし、多くの企業で支払われており、企業側の福利厚生の一環と捉えられています。
支給するかどうか、支給する場合はルールなどの詳細を就業規則や雇用契約などで、あらかじめ定めておかなければなりません。
旅費交通費
出張などの際の移動交通費や出張手当、宿泊費などを指す勘定科目です。業務で出張に行く都度、旅費交通費の経費精算処理を行う企業も多いでしょう。
同じ宿泊を含む移動費でも、慰安旅行などは「福利厚生費」、研修旅行は「研修費」となります。目的に応じて会計処理が異なるため注意が必要です。
出張費との違い
出張費は勘定科目ではありません。業務に関する理由で遠隔地に赴くときにかかる費用全般を指し、次のものを含みます。
・出張手当
・宿泊費
・交通費
宿泊費と交通費は実費を元に算出します。出張手当とは、出張における食事等の諸費用に対する手当です。多くの企業では、出張旅費規程で定められており、給与ではないため非課税扱いとなります。
通勤交通費の計算方法
通勤交通費の計算方法は、交通手段により異なります。そのため、多くの会社では「公共交通機関」「自家用車・バイク」「併用」の3パターンで規定を設けています。
各計算方法について詳しくみていきましょう。
公共交通機関のみ
電車やバスなどの公共交通機関のみで通勤する場合は、1か月分の定期代を交通費として支給されることが少なくありません。会社によっては半年分の定期代を支給する場合もあります。
自家用車・バイクのみ使用
自家用車やバイク通勤を通勤手段として認めるかどうかは、就業規則で定めることが可能です。許可した場合の一般的な計算方法は次のとおりです。
自宅~会社間の往復距離×1か月の平均労働日数×1リットル当たりのガソリン代
1リットル当たりのガソリン代はあらかじめ定めておきます。ガソリン代は変動するため、社員にとって負担にならない額に設定しておきましょう。
なお、自家用車とバイクでは燃費が異なるため、ガソリン代を別に設定しても構いません。
公共交通機関と自家用車などの併用
公共交通機関と自家用車やバイクを併用する場合は、各通勤手段ごとに計算します。それぞれの通勤金額の合計額を支給しましょう。
駐車場代や高速代の取り扱い
会社に駐車場がない場合などは、駐車場代が必要となる場合があります。法人名義で駐車場を借りておけば、原則として個人の給与課税として扱われることはありません。
また、通勤に高速道路を利用することに合理性があると判断できる場合は、他の交通手当と合計し上限15万円まで非課税として認められます。
交通交通費の非課税限度額
交通費には非課税限度額が定められています。それぞれの場合についてみていきましょう。
公共交通機関のみ
非課税限度額は月額15万円と定められています。ただし、実際にそれほど遠いところから通勤する社員は少ないでしょう。多くの会社では、一定の通勤範囲を決めその限度内で支給しています。
通勤ルートは最も経済的かつ合理的な経路で計算します。また、回り道やグリーン車・特急などの利用料金は非課税扱いになりません。
自家用車・バイクのみ使用
自家用車やバイクで通勤する場合、非課税枠は片道の通勤距離により異なります。
| 片道の通勤距離 | 非課税限度額(月額) |
|---|---|
| 2キロメートル未満 | 全額課税 |
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100 |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
| 35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
| 45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
| 55キロメートル以上 | 31,600円 |
公共交通機関と自家用車などの併用
経済的かつ合理的であれば、公共交通機関と自家用車などの併用も可能です。非課税限度額は各非課税額の合計となります(最大15万円)。
交通費として適正なガソリン代について詳しくはこちらの記事から。
交通費を支給する際の考え方
ここからは、交通費を支給する際の考え方についてみていきましょう。例えば、手当と実費であれば、どちらの方が従業員から不満が出にくいかなども考慮する必要があります。
手当と実費を明確に
通勤手当であれば、定期代のみの範囲、最短経路であることが殆どです。例えば、バスと電車を併用する場合も考え方は変わりません。実費であれば20%増しなどの幅を持たせることも可能です。
客観的に把握できる規定を作成する
規定に関しては、会社ごとに作れるため、以下のような柔軟でシンプルな内容で問題ありません。
・最短距離10キロ以上であれば自家用車通勤を求める
・ガソリン単価は特定の日付でリサーチし改定する
定期代の支給タイミングをよく考える
定期代に関しては、3ヵ月に1度、1ヶ月に1度など従業員の申請内容に合わせる方法などがあります。一斉に支給する場合、トラブルが発生する場合があるため、トラブルが起きないように事前に柔軟な規定を作っておくことも大切です。
また、1ヶ月に1度の支給などであっても住居変更がなければ、手続きそのものは大きく変わりません。
通勤交通費の支給方法
規定をどのように作成すればよいか迷うこともあるでしょう。ここでは、規定作成方法についてみていきます。
企業に対して交通費の法的な支払い義務はありません。また、交通費支給に関した規則を就業規則に記入し、労働基準監督署に届けることで支払い義務が生じます。
支給に関する規定を定めておかないと、会社と社員の間でトラブルが生じることにもなりかねません。明確に定めておきましょう。
ちなみに、具体的な通勤交通費の支給方法は下記の通りです。小見出しにわけて通勤交通費の具体的な概要をわかりやすく解説します。
全額支給
全額支給は、その名の通り従業員が通勤にかかるすべての交通費を企業側が支給する通勤交通費の支給方法です。従業員は通勤にかかる交通費が無料になるため、従業員にとっては非常にメリットがある支給方法となります。
一方、企業にとっては負担が大きく、特に遠方から通う従業員は、その分通勤交通費が高くなるためデメリットとなるでしょう。基本的に、多くの企業では全額支給ではなく、後述する一律支給などそのほかの支給方法を採用しているところが多いです。
一律支給
一律支給は、従業員が通勤にかかる交通費にかかわらず、すべての従業員に一定額の費用を企業が負担する支給方法のことです。例えば、自宅から会社までの距離にかかわらず、1日あたり1,000円交通費が支給されるケースが一律支給となります。一律支給の場合、従業員は通勤にかかるすべての費用を受け取ることができないので、一律支給の超過分を自身で支払わなければなりません。そのため、全額支給よりも負担が増えます。
一方、企業は従業員の住まいなどに関係なくすべて一律で交通費を支給することができるので、交通費計算の必要がありません。また、全額支給に比べて企業が負担しなければならない費用が減るため、企業にメリットが多い通勤交通費の支給方法です。
規定内支給
規定内支給は、企業が定めた規定によって従業員に交通費が支給される方法のことです。一般的にこのような仕組みを交通費の規定内支給と呼んだり、一部支給といわれたりします。
規定内支給は法律で基準が定められているわけではないため、通勤交通費の支給方法は企業が定めた規定に委ねられます。例えば、1日に1,000円までというように、上限を決めて従業員に交通費を支給する企業も多いでしょう。規定内支給は企業の判断で支給内容が大きく変化するため、トラブルを防ぐために従業員へ事前に細かく説明することが重要となります。
通勤交通費の規定作成方法
ここからは、通勤交通費の規定作成方法についてみていきましょう。支給要件などの細かいルールが明確であれば、従業員からの不満を避けられます。
支給要件の決定
まず、支給要件を定めましょう。下記の3つの中から支給方法を選択します。
・全額支給
・一律支給
・規定内支給
金額について決めかねる場合、非課税限度額を支給額の1つの目安にしましょう。
支給内容の決定
支給内容とは、通勤時に利用するルートの決定方法について定めます。会社側が不要な支出を防ぐためにも、最短・最安のルートで申請するよう定めておきましょう。
申請方法の決定
申請方法を定めておきましょう。入社時や転居時、通勤経路が変更する場合に通勤経路の申請が必要となります。
申請用のフォームを作成し、申請方法を定めておくとスムーズに申請できます。
確認方法の決定
通勤経路が申請された時に、それが本当に最短経路かどうか会社側は確認しなければなりません。
どのように通勤経路を確認するのか、定めておきましょう。通勤経路が計算できるシステムを導入すると、確認が楽になります。また、万が一社員から通勤交通費に関する質問やクレームが来た場合でも固定の計算システムを利用し、すぐに説明できるため担当社員の負担が軽減されます。




 JP
JP












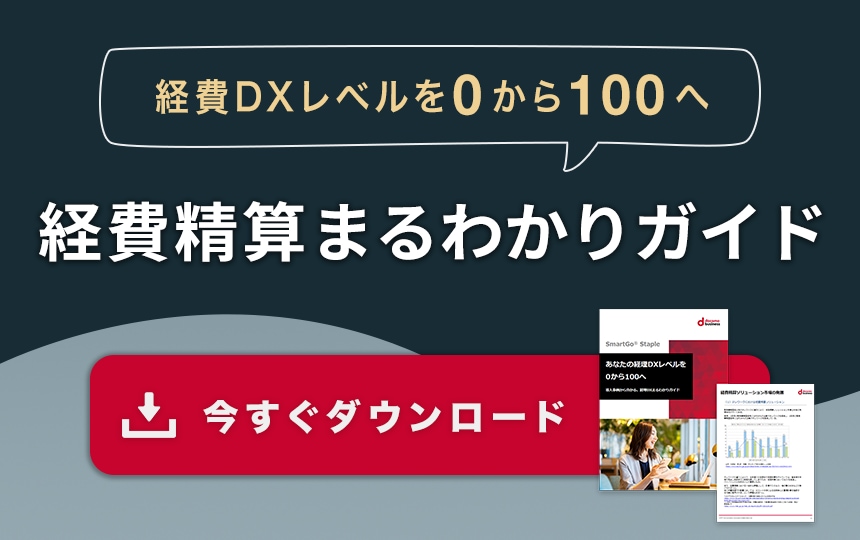
 経費や交通費の立替が多く、経費精算に稼働がかかる
経費や交通費の立替が多く、経費精算に稼働がかかる

 あわせて読みたいDXに関する記事
あわせて読みたいDXに関する記事





