
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK®
オフィスに縛られないハイブリッドワークを快適にしたい。働く場所に合わせてスピーディかつリーズナブルに最適なネットワークやゼロトラストのセキュリティ対策を導入したい。 いつでも、どこからでも、安心・安全・簡単にセキュリティと一体化した統合ネットワークサービスです。
関連コラム
”DX(デジタルトランスフォーメーション)”は、日本企業に共通した課題です。2018年に、経済産業省が「DXに取り組まない場合の経済損失リスク」を発表したことを契機として、DXに本腰を入れる企業が増えています。しかし、自社のみでDXを成功させることは不可能に近く、外部事業者の支援が必須といえる状況です。こうした実情を踏まえ、DXのために必要な支援事業者の分類と、それぞれの使い分けについて解説していきます。
1. DX支援事業者の分類と必要な人材
1. DX支援事業者の分類と必要な人材
DXプロジェクトでは、内外のプレイヤーがどのような役割を担うべきかを整理し、必要に応じて外部の支援事業者を選定していく作業が必要です。なぜなら、人的リソースに恵まれた一部の大企業以外は、社内リソースが不足するケースが多いからです。ただし、事業者はそれぞれ異なる強みを持つため、ステップによって事業者を使い分けていきたいところです。そこで、まずは支援事業者の種類と特徴を理解しておきましょう。

1-1. 主な支援事業者の分類
コンサルティングファーム
コンサルティングファームは「経営課題の抽出」「解決方法のとりまとめ」「部門間の調整」など、DXの上流フェーズ全般に強みを持っています。また、DXを成し遂げたあとの企業戦略や業務プロセスの再設計などを提案できる事業者も多いでしょう。コンサルティングファームが担う業務としては、「要件定義」「PMO業務」「BPR」「デジタル戦略立案」「中長期経営計画立案」「アクションプラン立案」などが挙げられます。
Sler
DXの前提となる「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」を含む、DXの実現化フェーズを担うことが多いです。具体的には、ITシステムの企画・設計・開発・改修を担当します。短期間に十分な人的リソースを確保しやすいほか、設計・開発・運用まで一貫したサポートを受けられる点がメリットです。特に、社内にエンジニアリングリソースを持たない企業の場合、SIerの選定がDXの成否を左右する可能性もあります。事前にできる限りの情報収集を行い、事業者ごとの強みや特徴を把握しておきたいところです。
クラウド製品ベンダー
SaaSなどクラウドベースのソリューション導入やカスタマイズを担います。DXの前段となるデジタイゼーションやデジタライゼーションでは、クラウド移行を伴うことも少なくありません。また、近年トレンドとなっている基幹システム(ERP)のクラウド化においては、他のクラウド製品との接続・統合が課題になることもあります。これらクラウド移行にまつわる種々の課題を解決するためには、クラウド製品ベンダーが持つ知見を取り入れることが大切です。
グループ企業、システム子会社
グループ企業やシステム子会社は、デジタイゼーションおよびデジタライゼーションが実現されたあとのシステム運用を担当することが多いでしょう。本体の業務担当者と同等レベルの業務知識を有し、さらにITに対する知見を持つことが強みです。また、DXの実現を見据えて、新しいシステム・業務プロセス双方に精通した「DX推進人材」を育成する際には、育成対象になることもあります。
1-2. DX推進人材の有無を確認する
DXの推進では、各ステップで特定のスキルを持った人材が必要になります。こうした人材は「DX推進人材」と呼ばれ、人材市場にもそれほど多くは存在していません。そこで、支援事業者に在籍している人的リソースを活用することも検討しましょう。下記は、各DX推進人材の役割や特徴を整理したものです。
プロデューサー
DXや、そこに至るまでのビジネスモデル立案・実現を主導する人材で、DXプロジェクトにおける統括役でもあります。具体的には、各事業部門や顧客、支援事業者などステークホルダーを結び付けつつ、デジタル化による企業変革を成し遂げる人材です。近年は「CDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)」という肩書を得て、企業のデジタル化をけん引することが多いでしょう。
ビジネスデザイナー
DXにおいて、デジタルビジネスの企画・立案・推進等を担う人材の総称です。一般的には、市場・顧客から得られる課題やニーズに応じてビジネスを発想し、提案・企画を行うといった役割を担います。市場・顧客の課題・ニーズをビジネスに結び付ける着想力や、着想を具体化させる企画力、企画に沿って社内外の合意形成を図る推進力などが求められます。
アーキテクト
DXやデジタルビジネスに必要なシステムを定義し、そこで活用すべき技術の選定とシステム設計を担当する人材です。アーキテクトはDXをシステム面から支える要職であり、デジタイゼーションやデジタライゼーションの上流工程でも必須の人材です。
先端IT人材(データサイエンティスト/AIエンジニアなど)
先端ITを駆使し、DXを支える人材です。DXには、データドリブン経営への移行が含まれることが多いため、データの専門家が必要になります。具体的には、統計学やデータ分析の専門家であるデータサイエンティストや、データを活用して新たな知見を発掘するAI開発を担うAIエンジニアが該当するでしょう。
UXデザイナー
DXにおいて、顧客体験の向上につながるようなビジネスデザインおよびシステムデザインを担う人材です。具体的には、製品やシステムの現状調査、改善案の立案、プロトタイプ構築、効果検証などを担当することが多いでしょう。UI設計やソフトウェア開発、デザインなど複数の分野に精通していることが求められます。
エンジニア/プログラマ
主にデジタイゼーションやデジタライゼーションにおいて、デジタルシステムの実装やインフラ構築等を担う人材です。「エンジニアリングリソース」の核となる存在ですが、近年はITエンジニア不足から質・量を担保することが難しくなっています。そのため、SIerなど外部の支援事業者のもつリソースを活用するケースが一般的です。
2. DXまでのステップ別の支援業者・必要な人材
一般的に、DXに至るまでには下記6つのステップが必要です。
- デジタイゼーションおよびデジタライゼーション
- DX戦略の策定
- DXに対応した業務プロセスの再設計
- デジタルプラットフォームの形成
- 開発体制の構築、プロジェクト推進
- DX人材の育成、確保
DXを実現するためには、ステップごとに最適な支援事業者を選定し、同時にDX推進人材をアサインしていく必要があります。
デジタイゼーション、デジタライゼーション
デジタイゼーションとは「アナログ・物理データのデジタルデータ化」のことです。デジタイゼーションでは業務プロセスの大半は変化させずに、効率化や自動化を進めることが多いでしょう。例えば、AI-OCRを活用した紙書類・証憑書類のデジタル化や打ち合わせ・商談のオンライン化、RPAによるルーティンワークの自動化などが挙げられます。デジタイゼーションは生産性や付加価値を増大させるための「下地作り」と考えて良いでしょう。
これに対してデジタライゼーションは、「個別の業務・製造プロセスのデジタル化」です。デジタル技術で業務プロセスやビジネスプロセスを変え、新しい価値を生み出すための試みと言えます。具体的には、「製造ラインにIoTやAIを配置して作業工程を代替させつつ、製造スピードと品質を高める」「CRMとMAを連携させて顧客ごとの行動傾向を分析しオンライン・オフライン双方のマーケティング精度を高める」といった施策が該当します。
デジタイゼーションとデジタライゼーションがある程度進捗したあとは、新しいビジネスモデルのデザインに着手し、本格的なDX戦略へとつなげていくことが多いでしょう。
デジタイゼーションとデジタライゼーションを担う事業者としては、「コンサルティングファーム」や「Sler」が挙げられます。コンサルティングファームがデジタル化戦略や業務プロセス改革を立案し、SIerがそれに基づいたシステム設計・構築を担うという流れが一般的です。また、このステップを担うDX推進人材としては、「ビジネスデザイナー」「エンジニア/プログラマ」「UXデザイナー」などが挙げられます。
DX戦略の策定
DX戦略の策定では、まず自社の核となる事業・文化などを定義し、社会と顧客にどのような価値を提供していくべきかを明確にします。具体的には、下記のようなステップを経ることが多いでしょう。
・DXの方向性を検討
変革の方向性を明確にし、変革によってどのような価値を提供すべきかを明確にします。また、変革を実現するための戦略やその効果、実現シナリオも定義します。
・As-Is/To-Be分析
「現状(As-Is)とあるべき姿(To-Be)」を比較して、その差異(ギャップ)を洗い出します。As-Isは三現主義を重視し、「現場・現実・現物」を具体的に把握することが大切です。社内アンケートや事業部門に対するヒアリングを重ねつつ、ボトムアップ型で情報を吸い上げていきましょう。また、To-Beは社内の意見だけを参考にするのではなく、同業他社・異業種の事例なども取り入れて作成したいところです。As-Is/To-Be分析がしっかりと機能すれば、おのずとギャップを埋めるための技術・ビジネスモデルが明確になっていくでしょう。
・具体的な施策の洗い出し
As-Is/To-Be分析の結果から、必要とされる技術・ビジネスモデルが明確になったあとは、これらを実現するための具体的な施策を洗い出します。ビジネスとシステムそれぞれに精通した人材をアサインしていってください。
DX戦略の策定は、「コンサルティングファーム」が担うことになるでしょう。また、必要なDX推進人材としては「プロデューサー」「ビジネスデザイナー」「アーキテクト」などが挙げられます。
業務プロセスの再設計(BPR)
システム・ビジネス両面からのアプローチが明確になったあとは、業務プロセスの再設計を行います。本来、DXとBPRは別の施策ですが、DXのためにはビジネスモデル変革やシステムの再構築が伴うため、これらに沿う形に業務プロセスを変えていく必要があるでしょう。一般的には、RPAやOCRによる自動化を前提とした業務プロセスの見直しなどが挙げられます。
業務プロセスの再設計は、業務負荷の上昇などの理由から、現場の抵抗にあうこともあります。そのため、事前にビジョンやあるべき姿を共有し、DXプロジェクトの一員であるという自覚を持ってもらうことも大切です。
業務プロセスの再設計(BPR)はコンサルティングファームが中心となって推進されることが多く、人材としては「プロデューサー」「ビジネスデザイナー」「アーキテクト」「UXデザイナー」などが該当します。
デジタルプラットフォームの形成
DXを支えるためには、デジタルプラットフォームの形成が欠かせません。具体的には、データ統合基盤やマルチクラウド環境の構築などが挙げられるでしょう。デジタルプラットフォームの形成は「人的リソースの最適化」「社内業務にかかるコストの低減」といった効果が見込めるほか、データ活用による付加価値の創出でも役立ちます。また、DXと共に語られることの多いデータドリブン経営やデータ民主化においても、その背後にはデジタルプラットフォームが存在していることが求められます。デジタルプラットフォームの形成には相応の時間とコストが必要になるため、自社開発・SaaS・パッケージなどの中から、最適な実現方法を選択しましょう。
デジタルプラットフォームの形成では「Sler」や「製品ベンダー」が主な支援事業者となります。また、必要なDX推進人材としては「プロデューサー」「アーキテクト」「UXデザイナー」「エンジニア/プログラマ」などが挙げられます。
開発体制の構築、プロジェクト推進
DXを実現するにあたって必要な業務システムの開発では、社内外の人材を結集してプロジェクトチームを組成したいところです。特に、自社のコア事業に関連するシステムについては、外部ベンダー主導で開発を進めるよりも、自社主導でしっかりと要件を固めながら仮説立案・開発・検証を繰り返し、システムの質を高めていくことが望ましいでしょう。そのため、場合によっては従来のウォーターフォール型開発よりも、アジャイル型開発のほうが適していることもあります。一般的にウォーターフォール型開発は、細かな改善案の反映が難しいという弱点を持ちます。これに対してアジャイル開発は、スケジュールやコストが把握しにくく、プロジェクトコントロールが難しくなります。
DXの基盤となる大規模システム開発は「正解」が存在しないため、ウォーターフォール型とアジャイル型を織り交ぜた「ハイブリッド型」を採用するなど、一定の工夫が求められるでしょう。ハイブリッド型開発は主に製造業で導入されており、ウォーターフォール型開発が持つ計画性の高さと、アジャイル型開発が持つ柔軟性・スピード感を両立するために使われています。
このステップで中心となる支援事業者は「SIer」や「クラウド製品ベンダー」です。また、アサインすべきDX推進人材としては「プロデューサー」「エンジニア/プログラマ」が挙げられます。
DX人材の育成、確保
DXを実現させるための仕組みがひととおりできあがったあとは、DX人材の育成に努めていきましょう。このステップではグループ企業やシステム子会社を活用し、グループ全体としてDX人材の育成と確保を推進します。まずはDXに関連するスキル・経験と、必要な人材の数を精査し、育成・採用計画を作成していきましょう。
もし、新規採用による人員補充が難しい場合は「レガシー技術を持つシニア人材の有効活用」なども検討していくべきでしょう。グループ会社やシステム子会社に在籍するレガシーシステムの運用担当者に「リスキリング(職業能力の再開発、再教育)」の機会を提供し、DX人材として活躍してもらうことです。また、これと並行して、評価制度や人事制度、学習環境の整備なども進めていってください。
このステップでは、自社およびグループ企業、システム子会社などが主なプレイヤーです。また、育成・確保すべき人材としては「プロデューサー」「ビジネスデザイナー」「先端IT人材(データサイエンティスト/AIエンジニア)」などが挙げられます。
3. DX推進時のポイント
3. DX推進時のポイント

最後に、DXを推進するにあたって特に意識すべきポイントを列挙します。実際のDXプロジェクト推進時には、下記3つのポイントに配慮すべきです。
越境を意識した体制構築
DXを実現するためには、強みの異なる事業者をうまく活用しながら、プロジェクトを推進していかなくてはなりません。したがって、「得意領域が異なる人材」同士を融合させるようなチームづくり・組織体制が必須となるでしょう。
これまで日本企業のITシステムは、「外部の支援事業者が構築を担い、情報システム部やグループ会社が運用を担う」といった役割分担の上に成立してきました。また、外部の支援事業者同士が人事交流や情報交換を行うケースは稀で、どちらかといえば「役割を終えたら次の事業者にバトンを渡して撤退する」といった動きが多いようです。一般的なITシステム開発プロジェクトでは、確かにこの「役割分担」が最も効率の良い形と言えるでしょう。
これに対し、DXプロジェクトは法律に例えるならば「憲法改正と同じレベルの大改正」です。国内ではまだまだ事例が少なく、確固たる成功モデルも存在しないとも言える状況です。DXを成功させるためには、ビジネス・システム・日々の業務に精通した人材の知識を結集しなくてはなりません。具体的には、コンサルティングファーム、SIer、製品ベンダー、グループ会社が互いに情報を共有し、ノウハウやアイディアを交換できるような場を設けていくのがベストです。
適切な事業者の選定
二つ目のポイントは、事業者の選定です。事業者の選定では、「各事業者の強みが自社のDXプロジェクトにマッチするか」が最大のポイントと言えます。これに加えて、事業者ごとに次のような点を踏まえて選定を進めたいところです。
・コンサルティングファーム
DXプロジェクトでは、業務改善やシステム導入などに強みを持つ「総合系コンサルティングファーム」、基幹システムなどITシステムの導入・刷新に強みを持つ「IT系コンサルティングファーム」などを候補とすることが多いでしょう。一方、近年はDXプロジェクトに対応可能なコンサルティングファームが増えているため、選定ポイントが曖昧になりがちです。
そこで、選定の目安として「自社で具体的なサービスを提供しているか」に注目してみてはいかがでしょうか。ビッグデータ、AI、BI、データ統合基盤といったDX関連ソリューションを提供しているコンサルティングファームであれば、比較的スムーズにプロジェクトが推進できるはずです。
・SIer
Slerの場合は、人員調達力や過去のプロジェクト実績などを重視すべきでしょう。Slerはいわゆる「実行部隊」であり、技術力が高いに越したことはありません。その技術力を明確に測る指標が存在しない場合は、過去の実績や人員の数といった「定量的なデータ」を重視する方法がおすすめです。DX関連のプロジェクトは国内でも事例が少ないため、まずは実績を持つベンダーに問い合わせてみるとよいでしょう。
・クラウド製品ベンダー
クラウド製品ベンダーは、「製品の機能」や「料金体系」「カスタマイズの可否(自由度)」「セキュリティ強度」などが選定ポイントになります。また、SIerと同様に過去の実績を重視することも必要です。
アジャイル、ウォーターフォールのハイブリッドを目指す
DXプロジェクトにおいては「プロジェクトの進行方法」が問題になることがあります。つまり「ウォーターフォールかアジャイルか」という2択を迫られたとき、どちらを採用すべきかの判断が難しいのです。これは、システム開発のみならず、DXプロジェクト全体の進行に言えることです。
一般的にウォーターフォール型プロジェクトは、プロジェクト全体の工程や流れ、現在地が把握しやすいことが特徴です。また、工程ごとに必要な人材・期待される役割・アウトプット(成果物)が明らかにされており、リソースの過不足を認識しやすいというメリットもあるでしょう。その反面、上流から下流へと流れる工程の間には「不可逆性」が形成されるため、要件変更や仕様変更の際にかかるコストが大きくなるというデメリットもあります。このデメリットは、正解が見出しにくいDXプロジェクトにおいて、足枷になるおそれがあるのです。
DXは、大半の企業にとって未知の領域であり、成功事例も乏しいのが実情です。そのため、いくらTo-Be分析を行ったとしても、それが正解とは限らず、常に手戻りや修正の発生を想定しておくべきと言えます。
こうした事情から、アジャイル型プロジェクトの採用が推奨されることもあるでしょう。しかし、アジャイル型プロジェクトは柔軟性とスピードを担保しやすい反面、全社横断型の大規模プロジェクトでは統制が取りにくいというデメリットがあります。また、ウォーターフォール型に比べると「人材の認識やスキルレベルが均一であること」が求められるでしょう。
以上の事柄から、DXプロジェクトには「ウォーターフォール型」と「アジャイル型」を適宜使い分けていくのも一つの手です。具体的には、「プロジェクト体制の整備やDX戦略の策定ではウォーターフォール」「以降のステップではアジャイル」を導入するといった試みが考えられます。
4. おわりに
本稿では、DXに必要な支援事業者と、DXに至るまでのステップについて解説してきました。現状、日本国内にはDXに関する「正解」が示されていません。そのため、まずは個々のステップで最適化を進めつつ、全体の整合をとっていく必要があります。DXの目的は「ビジネスモデル・人・組織の変革」であり、実現のためにはリソースの確保が重要です。まずはどういったリソースが必要なのかを整理しつつ、支援事業者の選定を進めてみてはいかがでしょうか。
この記事の目次
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK®
サービスに関するご質問など
お気軽にお問い合わせください
資料ダウンロード
-
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK®
サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください
サービス詳細情報は こちら





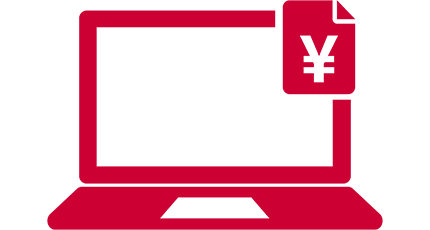
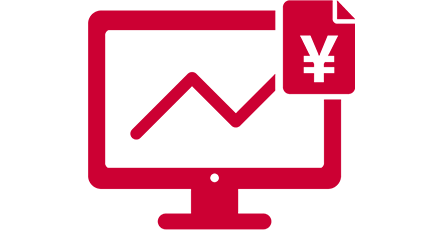

 JP
JP
















