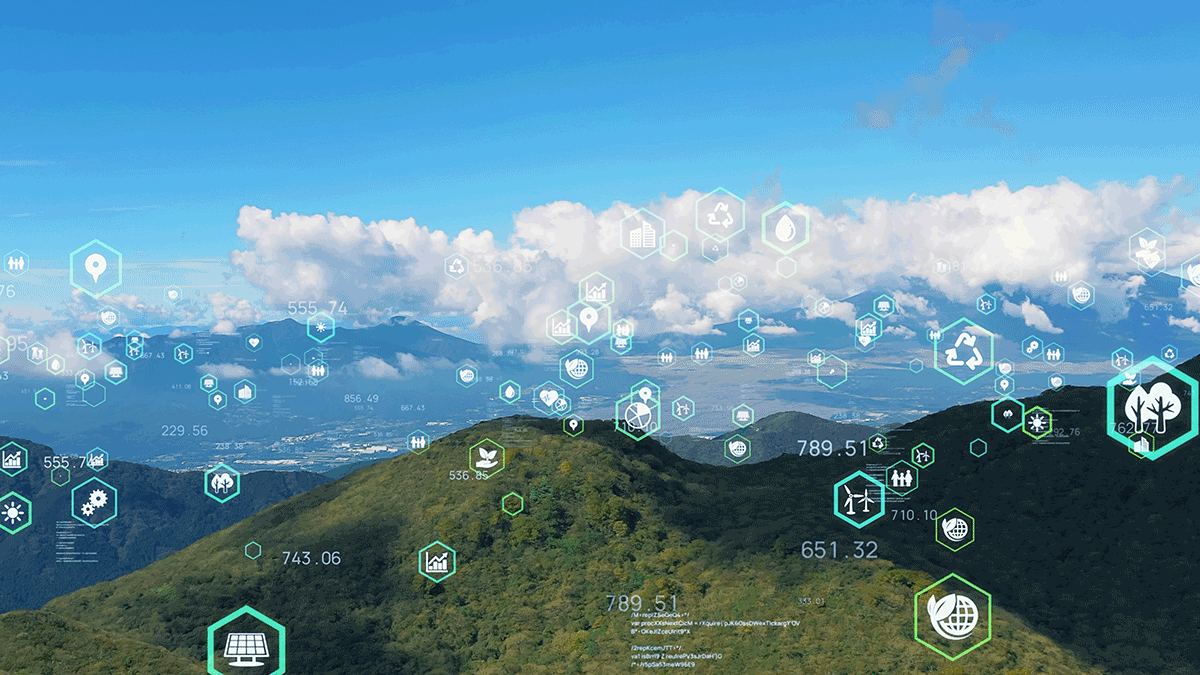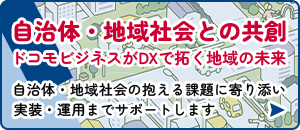■地域共創の基本からご覧になりたい方はこちら
【中小企業のビジネスをサポート】NTTドコモビジネスによる地域の取り組み
オーバーツーリズムとは何か
「オーバーツーリズム(Overtourism)」という言葉は、2016年に米国観光産業専門メディアであるスキフト(Skift)社が造語し、後に商標化した言葉で、「観光公害」「観光過剰」などと訳されます。具体的には「許容範囲を超えた観光」という意味で、特定の観光地に観光客が過度に集中することで、地域社会や環境に悪影響を与える現象を指します。
昨今、オーバーツーリズムに注目が集まっている背景には、LCC(Low Cost Carrier、格安航空会社)の登場により航空券の価格が低下したこと、航空券・宿泊施設予約のオンライン化により海外旅行の手続きに関するハードルが下がったこと、SNSなどにより特定の観光地の情報が急速に拡散することで一極集中が起こりやすい環境となったことなどがあります。
また、日本特有の背景として円安の影響で日本への旅行のコストが低下したこと、東京オリンピックや大阪・関西万博など国際的なイベントが開催され注目が集まったことなどがあります。

オーバーツーリズムの日本国内事例と問題点
オーバーツーリズムにより、具体的には「交通渋滞」「ゴミのポイ捨てなどによる自然環境破壊」「地域住民のプライバシーの侵害」「騒音」「人混みによる景観の悪化」などの悪影響が生じます。
オーバーツーリズムの発祥はイタリアやスペインなどのヨーロッパ各国ですが、近年は日本国内でも深刻化しています。そのうちいくつかを紹介します。
京都府京都市の事例

京都府京都市には、世界遺産である清水寺を中心に年間5,000万人を超える観光客が押し寄せています。そのため京都駅への観光客の一極集中のほか、市バスの混雑など、地元住民に直接影響する混雑が発生していました。また、記念撮影のため私有地に無断で立ち入ったり、ごみをポイ捨てしたりなどの観光マナーも問題となっていました。
岐阜県白川村の事例

同じく世界遺産である、約500人の村民が暮らす合掌造り集落で有名な岐阜県白川村の白川郷では、1995年の登録以降、特に外国人観光客が顕著に増加しました。2023年の外国人観光客数は日帰り・宿泊を合わせて約66万人と、約500人の村民の数千倍の観光客が訪れる事態となり、ゴミの増加や騒音などの被害が発生しました。
北海道美瑛町の事例

「白金青い池」のライトアップや夕焼けが美しい「新栄の丘展望公園」で有名な北海道美瑛町には、2023年には人口の200倍に相当する約240万人が押し寄せ、記念撮影に伴う私有地への立ち入りや路上駐車、交通渋滞などの被害が発生していました。そのため2025年には地元の農家を守るため、ついに40本のシラカバ並木を伐採するという厳しい決断をせざるを得ない状況となりました。
大阪府の事例

大都市圏も例外ではありません。2023年の都道府県別の観光客数が約1,800万人と、約2,400万人の東京都に続く2位となった大阪府では、関西国際空港の直行便数がコロナ禍以前まで回復し、特に中国、韓国、台湾など東アジアからの外国人観光客が増加しました。大阪・関西万博開催の影響もあり、今後のオーバーツーリズムが懸念されています。
オーバーツーリズムが解消されない場合、日常生活に支障が出ることにより「観光客嫌悪」につながり、住民と観光客の共存が難しくなる危険性があります。そのため、社会問題として深刻化する前に、適切な手順を講じて対策する必要があります。
オーバーツーリズムの対策方法と事例
こうした悪影響を受け、すでにオーバーツーリズムが大きな社会問題となったイタリアのベネチアやスペインのバルセロナなどでは、地域住民の生活環境を守るため、団体客の人数を制限する、観光税を引き上げるなどの対策を実施しました。
同様に、日本国内においても着々と対策が進んでいます。
国土交通省観光庁は、既に「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた取組」を公表しています。さらに、令和5年に同取り組みでは「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた対策パッケージ」として、「①観光客の集中による過度の混雑やマナー違反への対応」「②地方部への誘客の推進」「③地域住民と協働した観光振興」の3点が挙げられており、具体策を講じる取組に対し、国として総合的な支援を行うことが発表されています。
※参考:国土交通省 観光庁「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた取組」
上記指針の中で特に重要となるのは「①観光客の集中による過度の混雑やマナー違反への対応」です。
観光客の地理的・時間的な分散とマナー啓発は各地域が主体的に推進すべき対策ですが、そのためにはまず現状の把握が必要となります。対策地域において、どのエリアに観光客が集中しているのか、そのうちどの国からの訪日外国人が多いのかを把握することで適切な対処が可能となります。
NTTドコモビジネスの「モバイル空間統計」は、ドコモの携帯電話ネットワークの仕組みを使用して、いつ・どんな人が・ドコから・ドコへ動いたかを24時間365日把握することができる新たな人口統計情報です。前述の観光庁「オーバーツーリズムの未然防止・抑制に向けた取組」にも、訪日外国人旅行者のローミング(海外キャリア利用者のドコモ携帯ネットワーク利用)を統計処理したデータの一例として紹介されています。訪日外国人の国/地域別、出入国空港別、訪問先都市など多様なデータをエリアや時間別、季節ごとに分析可能なため、顧客ターゲットの選定や誘客施策などに活用できます。
京都府京都市の対策事例
京都市では「観光課題対策」として「観光地の混雑対策」「市バスの混雑対策」「マナー対策」など7点の対策を実施。
例えば観光地の混雑対策としては、閑散期や朝・夜の観光への誘導、ビッグデータを活用した混雑状況・観光快適度の見える化などの対策を取りました。また、市バスの混雑対策としては、「観光特急バス」の新設や、地下鉄などへの分散、市バスの運行状況のオープンデータ化などの対策を打ち出しています。
合わせて「市民生活と観光の一層の調和の推進」「京都観光の質・満足度の向上」にも取り組んでいます。
※参考:京都市情報館「令和5(2023)年 京都観光総合調査」
岐阜県白川村の対策事例
岐阜県白川村では、地域の魅力をより感じられるよう、合掌造りに宿泊するプラン、世界遺産エリアや周辺エリアを周遊するプランなどの作成を計画。NTTドコモビジネスの「モバイル空間統計」を活用し、まずは国/地域別の外国人観光客数を季節ごとに把握することを目指しました。その結果、夏季にはスペインからの観光客数が急増すること、冬季には「冬の白川郷、雪の体験」を求めるタイからの観光客が多くなることなどが把握できました。今後、これらの結果を新たな観光プランの作成、効果的なプロモーションの検討などに活かす予定です。
また、「レスポンシブル・ツーリズム(責任ある観光)」を掲げ、「火の取り扱いは厳禁」「ゴミの持ち帰り」「夜の観光客受け入れ停止」など5つのルールを定めて住民の生活環境の保護を実現しました。
※参考:白川村「白川郷レスポンシブル・ツーリズム」
北海道美瑛町の対策事例
美瑛町では、最寄り駅からの交通手段不足や観光地への一極集中による渋滞発生などへの対策として、令和4年7月より近距離周遊型の新たな人流および関係人口(地域と多様な関わりを持つ人々)の創出を目的としたカーシェアリングサービスの実証事業を行いました。
また、美瑛町観光ポータルサイトに「ゴミの不法投棄の禁止」「農地に絶対に入らない」「池に石やゴミを捨てない」などのルールを周知しました。さらに交通渋滞については観光スポットの混雑状況を発信するシステムを導入し、観光客の分散を図っています。
※参考:
美瑛町観光ポータルサイト「観光客の皆様へのおねがい」
丘のまちびえい活性化協会「カーシェアリング実証事業」
大阪府の対策事例
大阪道頓堀では大阪市と観光庁、NTTドコモビジネスなどが連携し、ゴミ圧縮機能やごみの蓄積量を遠隔把握できる機能を備えた「スマートゴミ箱」を設置し、ポイ捨てゴミを約39%削減することに成功しました。合わせて多言語対応の街頭スピーカーなども設置し、観光客のマナー啓発に取り組んでいます。
※参考:道頓堀ナイトカルチャー創造協議会ほか「道頓堀観光DX化計画 第四弾!」
「②地方部への誘客の推進」を推進するためには、現在メインストリームとなっている観光地から収容人数に余裕のある地域へと観光客を誘導する取り組みが必要となります。具体的には、SNSや広告メディアの活用を通じて、観光集中エリア外の地域の魅力を主体的かつ効果的に発信することが重要です。株式会社D2C Xが運営する訪日外国人向けメディア「tsunagu Japan」を始めとするメディアを活用するのも良いでしょう。
また、内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部事務局、内閣府 地方創生推進事務局では、内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」を公開しています。これまで10年の地方創生への取組と今後の推進方向に関する情報や、地域興しのスペシャリスト「地域活性化伝道師」の紹介などが掲載されているため、地域の特性を生かしつつ、より良い周遊環境を描きたいとお考えの方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
持続可能なまちづくりにむけて
今回はオーバーツーリズムについて解説しました。オーバーツーリズムへの対策はSDGsのうち「住み続けられるまちづくりを」の達成にも貢献するため、各地域が主体的に取り組むべき重要な課題と言えます。
オーバーツーリズムを解消するには、今回紹介したように適切なオーバーツーリズム対策を採る必要があります。例えば人口統計の分析を通じ、いつ、どんな国からどのくらいの人が来ているのかといった現状を高い精度で把握したうえで、「住民と観光客とが無理なく共存でき、活気のある地域振興を成功させる」などの「ゴール」を明確にした対策を取ることが重要です。
あわせて読みたい記事(まちづくり)
地域共創の注目記事

村上信五さんが農業ビジネス、ぶどうプロジェクトに挑戦!
地域共創の基本から実践まで学べる!
- 地域創生のトレンドを学ぶ
-

地方創生実現のために「東京」がするべき5つのこと

政府が推進中のまちづくり「スーパーシティ」とは何か?
- 地域活性化に繋がる次世代技術
- 有識者や専門家の視点で学ぶ
- 地域創生の成功事例を学ぶ
- 知っておきたいDX用語集








 JP
JP