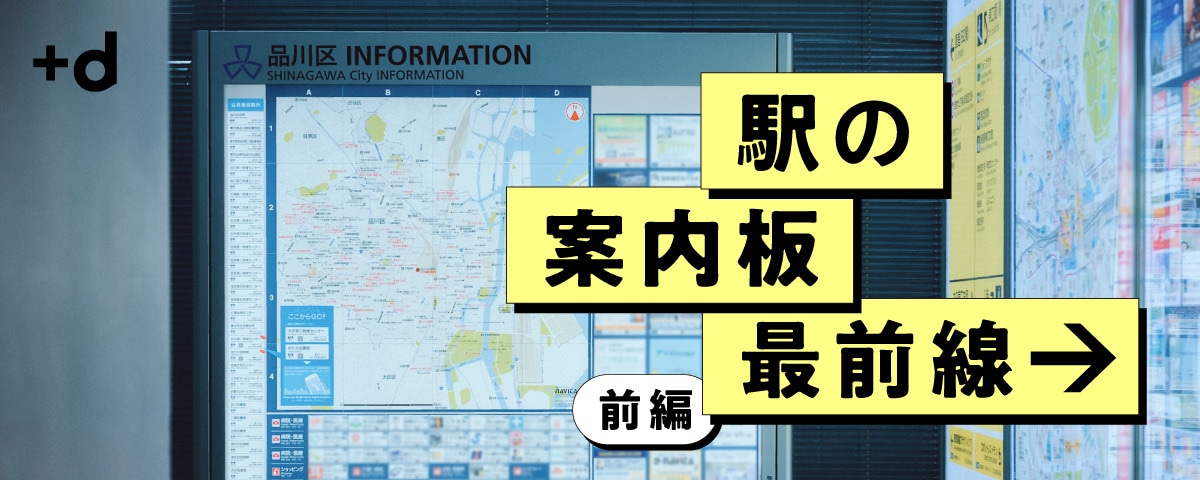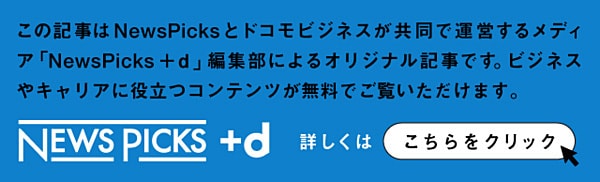バス停の手書き地図からスタート
全国の鉄道駅にある周辺案内地図の多くを設置・運用しているのは、名古屋市で1967年に創業した表示灯株式会社です。創業以来、鉄道会社と連携して全国の駅構内に案内板を提供、設置し、駅の利用者を目的地へと導いてきました。
ビジネスモデルは創業当時から変わらず。創業メンバーが「公共性の高い事業をやろう」と名古屋市内の小さなバス停に、広告を掲載した手書きの周辺案内地図を掲示したのが、始まりでした。徳毛孝裕社長が、当時の状況についてこう説明します。
「最初の大きな転機は鉄道駅に出すようになったことですが、何の実績もない小さな会社が『広告付きの地図を出したい』と言ったところで、当時はなかなか相手にしてもらえなかったと聞いています。何度も追い返されながらも、バス停での実績を掲げて粘り強く営業活動をした結果、約半年後に鉄道駅第1号となる駅案内板を名古屋鉄道の上飯田駅に設置することに成功しました」
表示灯が設置する駅案内板「ステーションナビタ」は、出口案内や駅周辺の地図、公共施設、災害時の避難場所などの情報をひとつの画面に収め、駅利用者に対して目的地までの道のりを伝える役割を担う「公共インフラ」に近い存在です。

周辺案内地図の制作、設置などを担っているのは、すべて表示灯。同社が地域でスポンサーを募って周辺案内地図と一緒に広告を掲載し、掲載料を得ることで設置、運営にかかる費用と収益に充てるビジネスモデルなのです。
「当社が創業まもないころの鉄道駅では、利用者向けの周辺案内地図を設置している駅はあまりなく、利用者が自分で地図を持参したり、駅員が道案内の問い合わせに対応したりすることも多かったようです」と徳毛社長は言います。
そこへ同社が、大きくて見やすく、わかりやすい周辺案内地図を設置してくれるというのだから、鉄道駅にとっては願ったりかなったりの話でしょう。駅利用者の利便性はアップし、駅側も利用者から道を聞かれることが大幅に減り、業務効率化につながります。
表示灯にとっても、駅という人の流れがある場所の広告枠は販売しやすく、まさに鉄道会社、スポンサー、自社、そして利用者の“四方よし”のビジネスで、同社の案内板は全国の鉄道駅に急速に普及していったのです。現在は、JR各社や私鉄、地下鉄など全国の約2400の駅に設置されているといいます。

同社は、周辺案内地図の制作と設置、運用管理はもちろん、そこに掲載する広告を集める代理店業務までを一気通貫で担っています。案内板に広告を掲載するスポンサーは、その地域の医療機関や事業所、飲食店などその地域ならではの顔ぶれが中心。広告を出稿したスポンサーの施設名は、地図上でも赤文字で目立つように表示していて、見る人への視認性をアップしています。
もっとも、周辺案内地図は1回作ったら終わりではありません。地図に掲載されている施設が変わったり、新しいビルができたりするのは日常茶飯事。同社関東支社インフラ開発部の伊藤祥部長は、案内板のメンテナンスはスタッフが現地まで足を運び、その目で確認していると言います。
「専任の担当者が、定期的に現地を訪れて実際に歩きながら変更がないかを調査し、地図をアップデートしています。頻度は施設によって異なりますが、多くは年に1回、広告を含めて刷り直します。張り替えが間に合わない場合は、変更が生じた箇所にシールのように修正文字を貼りつけることもあります」

スマホの地図アプリ登場に警戒感
駅案内板である「ステーションナビタ」事業で順調に成長してきた同社でしたが、2000年ごろから頭打ちの気配が見え始めます。広告収入が見込める公共交通機関の駅には限りがあるうえ、廃線などでなくなる駅も出てくるため、無限の成長は不可能だからです。
そこへさらに、駅の案内地図の役割を大きく変えかねない環境変化も重なりました。スマートフォンの普及です。それまでは当たり前のようにアナログの周辺案内地図を見ていた駅利用者が、スマートフォンの地図アプリを活用し始めたのです。
アプリでは、ナビゲーションに従って歩けば目的地に行けるうえ、間違った方向に向かってしまったときも、すぐに気づくことができます。徳毛社長が、こう振り返ります。
「広告の営業先でも『もう駅の周辺案内地図は誰も見なくなるのでは?』と言われることが増え、社内でも心配する声や警戒する雰囲気が広がりました」

しかし実際は、心配したほどにはステーションナビタのニーズは減りませんでした。スマートフォンを手に持ったまま案内板で出口の方向を確認したり、アプリの地図と見比べたりする“二刀流”を実践する人たちが数多く現れたのです。これは、同社の地図が設置場所に合わせて地図をカスタマイズしている点も、功を奏しました。
「一般的に地図は、北が上になるよう制作されますが、当社が駅に設置する周辺案内地図は、利用者が向いている方向が上になるように制作されています。これにより、地図に不慣れな人でも、右に行ったらいいのか、左に行ったらいいのか、直感的に理解しやすくなります」(徳毛社長)
まずはステーションナビタを見て進む方向や出口番号を確認したうえで、そこから先はスマホの地図を使うという使い分けをする人も多いようです。
「このため同じ駅に複数のステーションナビタが設置されている場合でも、それぞれ地図の向きがまったく違っているということは、ふつうにあることです。スマホの向きを変えたり、傾けたりしながら、ステーションナビタの地図と方向を合わせて確認している人の姿もよく見られます」(同)

それでも、スマホの地図アプリの普及で、広告媒体としてのステーションナビタの価値が下がったと考える広告主も一定数存在しました。そこで同社が取り組んだのは、周辺案内地図のデジタル化です。
2011年には、新横浜駅に初のデジタル版ステーションナビタを設置しました。この新しいステーションナビタはタッチパネルを採用し、利用者がタッチすることでより多くの情報を得られるようになっています。開発担当でもある、同社新規事業推進本部の佃直幸副本部長は、こう振り返ります。
「広告をタップすると詳細な情報が表示される機能や、スマホでより多くの情報を提供するための2次元コードを掲載するといった取り組みを進め、都市部を中心にすでにあるステーションナビタをデジタル版に更新していきました。当初は広告の情報量を増やすことで広告効果をアップし、単価を引き上げることが主な目的でしたが、デジタル化によって、それまで印刷・張り替えを伴っていた地図の修正もリモートで対応できるようになり、運用の効率化も実現しました」


アナログ案内板を残す意味
さらに、一部の大型駅ではデジタルサイネージを導入し、動画広告を掲載したり、タッチパネルによる言語の切り替えや緊急情報への即時対応を可能にしたりする、デジタルサイネージ版の周辺案内地図も活用されています。
デジタルサイネージにすることで情報の更新が容易なうえ、広告単価も上がって収益性は向上しました。しかし、すべてをデジタルに置き換えるつもりはないと徳毛社長は言います。
「長く広告を出稿いただいている地場のクライアント様の中には、広告単価が上がることで出稿を控えるケースもあると考えられます。そうしたお声に引き続き応えていくことも重要だと考えているので、デジタル化する場所とアナログの案内板を維持する駅は慎重に選んでいます」

さらに同社では、ステーションナビタのデジタル化に加え、鉄道駅以外に設置場所を拡大する取り組みにも力を入れました。たとえば、車移動が多い地方では、人々の移動の拠点となっている「道の駅」にも周辺案内地図のニーズがあると着想したのです。またデザイン面でも、観光客が多く訪れる鉄道駅や道の駅などでは、従来のステーションナビタや公共サインではカバーできない、独自のデザインを求める需要があることにも着目しました。
「観光地ではより柔らかいイメージの周辺案内地図や、筐体そのものにエリアの特徴や特産品をデザインするニーズもあります。たとえば、鉄道会社の車両デザインを模した筐体などそのエリアの個性を出す取り組みを一部の鉄道会社で始めています」(徳毛社長)
個性的な筐体は人目を引くうえに、SNSでの“映え”も期待できます。観光地仕様のイラストマップでは視覚的に楽しめる要素を増やし、地元の魅力を直感的に伝えられるようデザインを工夫しました。タッチパネル型のデジタルサイネージを導入することで、バスのリアルタイム位置情報や近隣施設情報へのアクセスも可能にしています。



こうした展開の先駆けとなっているのが北海道で、道の駅を中心にナビタの“横展開”を進めています。新千歳空港や道と川の駅「花ロードえにわ」、南幌町の誘客交流拠点など、12カ所にデジタル版のイラストマップを導入していて、2026年春には世界自然遺産・知床の町として有名な羅臼町でも新設を予定しています。
「駅が無人化されたり路線が廃止されたりするなかでも、人が多く訪れる場所には必ず周辺案内地図が必要です。今後も鉄道駅の外や、地域の中へと役割を広げていきます」(徳毛社長)
スマートフォンが人々の情報収集の主役となったいまもなお、誰もが見ることができる情報や、迷わず動き出すための道しるべの必要性はなくなりません。地域観光の魅力アップやアクセシビリティ向上という面からも、表示灯の新しい役割が期待されています。
※後編に続く
この記事はNTTドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております。
取材・文:森田悦子
撮影:大橋友樹
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:鈴木毅(POWER NEWS)








 JP
JP