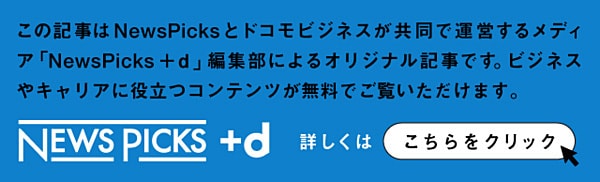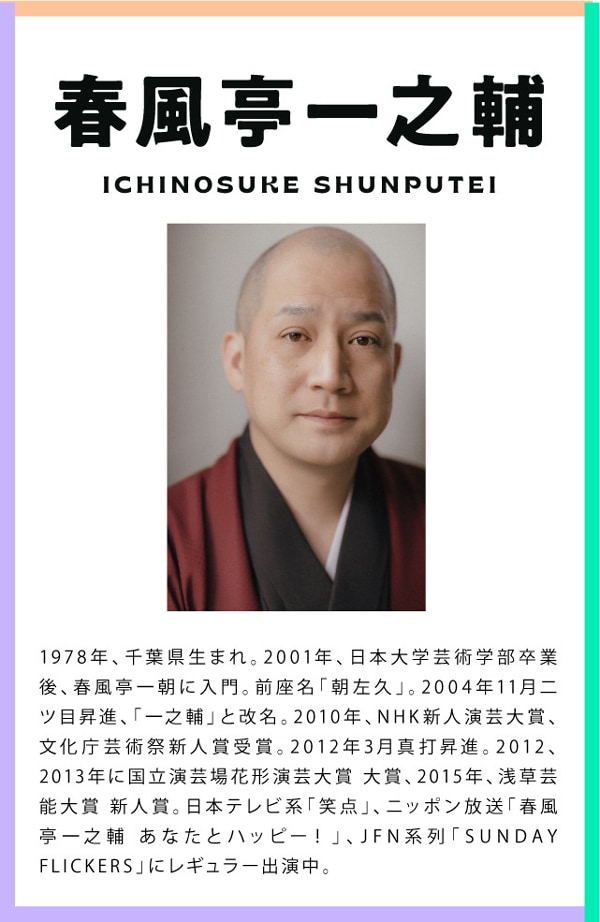
寄席という「不確実性」の巣窟
寄席というところは、毎日「昼の部」と「夜の部」の2回興行。それぞれ落語家だけでなく講談や漫才、マジック、太神楽、紙切りなど、15~20組程度の芸人が代わりばんこに出てきて芸を披露します。
お客さんは好きなときに入ってきて、好きなときに出ていっていい。前座さんから主任(トリ)まで熱心に聴いていく人もいれば、ひいきの芸人を目当てにお越しになる人もいる。そこが市民会館などで開催される「ホール落語」(落語会や独演会)とは異なります。
落語会はあらかじめ登場する芸人が公表されているので、「好きな芸人が出るから行こう!」という動機が働くし、独演会ともなればその傾向はなおさらです。
演じる側も、落語会や独演会にお越しになるお客様は、「ファン」とは言わないまでも、自分に対して悪い印象を持っていないからこそお金を払って来てくださるわけです。言ってみれば「ホームゲーム」のようなもの。

その意味での緊張感がある半面、「やりやすい」ともいえます。
一方の寄席は、自分のファンじゃない人も大勢来る。「アウェー」です。加えて、寄席という空間に慣れていない人、ハッキリ言えば「マナーが身についていない人」もいる。
だからいろんなことが起きるんです。噺の途中で入ってきて、お客さんの前を横切って席につくのも困りものですが、一番厄介なトラブルはというと、「携帯電話」でしょうね。
まだマクラのうちならどうにかなるけれど、噺の本筋に入って、サゲに差し掛かろうというところでケータイが鳴り響くと、演者も他のお客さんもガッカリする。
電話が鳴ってもすぐに切るならまだ可愛いんだけど、さんざん鳴らした挙げ句に出るヤツがいる(笑)。
そんなとき、僕はその客をにらみつけます。「おいっ、出るのかよ!」って叫ぶこともありますが、そんな人は気にしないんですね。
この手のトラブルをうまく笑いにつなげることもできなくはないけれど、僕はしない。そんなことをするとその客は、「俺のおかげでウケた」と喜んだり自慢したりするから……。

高齢のお客様のなかには「携帯電話の電源を切る」ということが理解できない人もいる。僕の独演会では、開演前の“影アナウンス”を自分でやっていますが、このときすべてのお客さんにケータイやスマホをカバンから出してもらって、電源を必ず切ってもらう。
「電源を切った人は拍手!」と言うと拍手が起きる。次に「切れなかった人は拍手!」と言うと、やっぱり何人か拍手が起きる。
そうなると隣近所の席の人が切り方を教えてくれるし、それでもダメな人のところには係員が行って対処する。それほど演芸の途中でケータイを鳴らされると困るんです。
これはある程度お客さんを統括できる独演会ならではの対応で、寄席ではそこまではできない。だから寄席の高座に上がるときは、つねに緊張感を強いられます。
ストレスの度合いは噺の内容によっても違います。人情噺でシーンと静まり返ったところでピロピロ鳴り出したら、それまで高座と客席とでつくり上げてきた世界観がおかしなことになっちゃう。そしてそのストレスは決して小さくありません。
ただ、毎日寄席に出ていると、次第に場慣れはしていきます。しかも、僕はその場でストレスは感じてもあまり引きずることもない。その日のことはその日のうちに忘れていく性格なんです。
これは落語家向きの性格だと思ってます。

「笑点」に出演することのメリットとデメリット
エゴサーチはしますよ。ただ、ネガティブな意見に対して、反省してその意見を取り入れるようなことはしない。「そんな意見もあるんだな……」といった程度の受け止めです。
落語って好き嫌いがあるので、必ずしもすべてのお客様に喜んでもらえるとは限らない。来てくれたお客さんには喜んでもらえるよう努力はしますが、こればかりは限界がある。
そんな時に「いろんな意見があるんだな……」と考えるのは、悪いことではないと思うんです。
「笑点」のレギュラーが決まったときも、好意的ではない反応があることは予想してました。そもそも僕自身が「笑点」に出るとは思ってなかったし、若い頃は「『笑点』こそ悪の元凶」って思ってましたから。
それだけに、オファーを受けたときは悩みました。
でも考えてみると、落語家が座布団に座って面白いことを喋る──ということを何十年も発信し続けているのは「笑点」だけなんです。
きっちりと落語を聴かせる番組もあるけれど、それは深夜にマニアが見るような番組で、日曜の夕方に家族がそろって見る馬鹿馬鹿しい番組なんて他にない。そう考えるとむげにできないんじゃないか……って思うようになったんです。
ただ、だからといってなぞかけなんてやりませんよ。そもそも普段から「機嫌悪いオーラ」を出しているので、僕になぞかけを求めてくる人はまずいない(笑)。

それでも独演会などで地方に行くと、「『笑点』に出てるヤツが来たから聴きに行ってみるか……」というお客さんが一定数いるのも事実。それで噺を聴いてもらって落語に興味を持ってもらえたら、ありがたいことですよ。
時代の流れや“波”に乗ることを期待するな!
これまでの人生を振り返ってみると、本当にラッキーだったと思いますよ。何のビジョンも持たずに、行き当たりばったりで生きてきた。
入門当時の落語界は下火だったのに、二ツ目に上がる頃にブームが来た。真打昇進も、当時の落語協会会長だった故・柳家小三治師匠が花火を上げたいと考えていたときに僕がめっかっちゃって抜擢してもらえた(21人抜き)。
僕は何も考えていないのに、周囲がどんどん流れをつくって、僕はそれに流されるだけだったんです。
でも、「波に乗れる人」っていうのはごくまれな存在で、だからこそ僕は「運がよかった」と思うんです。
そして、「運のよさ」は、必ずしも希望通りにいくわけじゃない。そんなものに期待するのは危険です。

だから弟子には「ビジョンを持て!」と言うんです。とはいえ壮大な目標を持つというのではなく、まあ現実的なところを狙わせますね。
いま20人規模の居酒屋さんで勉強会を開いているなら、3年後は50人のキャパを目指せ──とか。そういう現実的な目標を一つひとつクリアしていくことが大事だと思うんです。
行き当たりばったりで生きてきた師匠に「ビジョンを持ちなさい!」なんて言われて、ちょっと可哀想な気もするけれど、そもそも「弟子は取らない」って断っているところに強引に潜り込んできたんだから文句は言わせませんよ。
しかも、彼らが僕の言う通りビジョンを持ってやっているのかどうかまで、僕はフォローしていません。そこまで面倒見切れないし、知ったこっちゃないですよ。
でもね、弟子が人づてにでもほめられたり評価されたりするのを耳にすると、やっぱりうれしいものです。親心なのか何なのかわかりませんが、不思議なものですね。
ただ、将来もし弟子が売れて、僕より稼ぐようになったら拗ねちゃうかもしれないな……。

前座噺でトリをとるカッコよさ
噺家になって最初に師匠から教えてもらった噺が「子ほめ」で、前座としての初高座もこの噺でした。
酒好きの男が、赤ちゃんが生まれた家に行って赤ん坊をほめるとお酒を飲ませてもらえる──と、ご隠居からほめ方を教わってお祝いに行って失敗するという典型的な落とし噺。いわゆる「前座噺」の一つで、僕も弟子に最初に教えるのがこの噺です。
人情噺や超大作もいいけれど、何か一つおすすめの噺をと言われたら、僕は「子ほめ」を推しますね。

落語の本質は、人が欲張って失敗する姿が面白いわけで、「子ほめ」はその最高傑作だと思うんです。
短い噺ですが、仕込みがあって、それを全部バラして笑いにつなげていく。笑いの基本が全部詰まっているし、笑いどころも多い。
前座噺っていうと軽く見られがちだけど、亡くなった桂文朝師匠がこの噺を寄席のトリでかけたのを見たときは「カッコイイ!」と感動したのを覚えています。
こういう噺をトリでかけるには相応のウデが必要で、僕なんかはまだまだその域には達していない。
でも僕が寄席で「子ほめ」をかける割合は多いほうです。サゲをちょっと変えたり、途中を練り直したりしてみては高座にかけて反応を確かめる。
まあウケますよ。
いつかトリで「子ほめ」を演(や)ってみたいですね。あまり人には言ったことはないけれど、ちょっと憧れがあるんです。
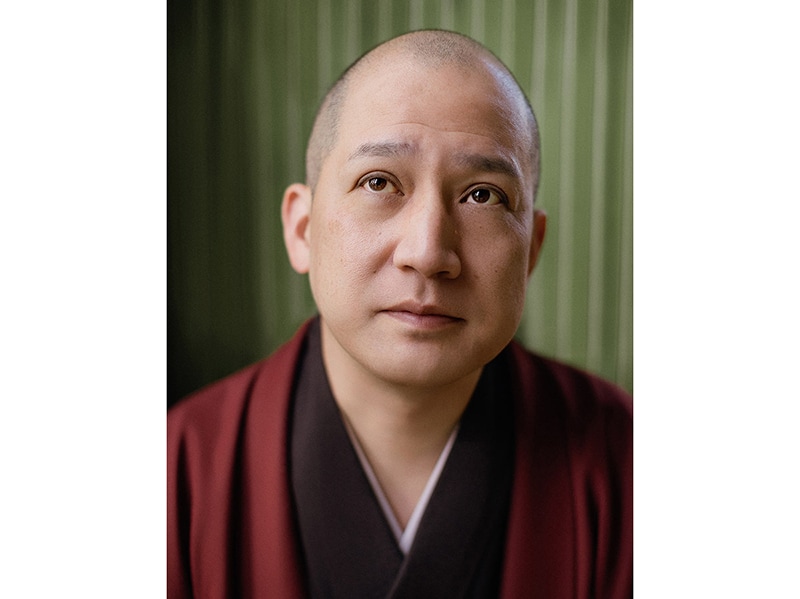
後編では「ネガティブさを力に変える方法」についてお話しいただきました。
※本記事のタイトルバナーで使用している文字は、株式会社昭和書体の昭和寄席文字フォントを使用しています。
この記事はNTTドコモビジネスとNewsPicksが共同で運営するメディアサービスNewsPicks +dより転載しております 。
執筆:長田昭二
写真:小田駿一
デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)
編集:奈良岡崇子








 JP
JP