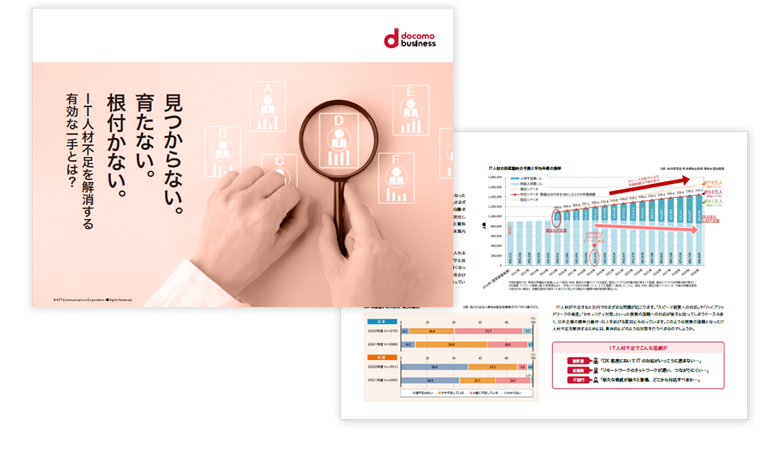選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK®
オフィスに縛られないハイブリッドワークを快適にしたい。働く場所に合わせてスピーディかつリーズナブルに最適なネットワークやゼロトラストのセキュリティ対策を導入したい。 いつでも、どこからでも、安心・安全・簡単にセキュリティと一体化した統合ネットワークサービスです。
関連コラム
ネットワーク冗長化とは? メリット・デメリットや実施方法
インターネットやネットワークへの常時接続が前提となっている多くのビジネスでは、ネットワーク冗長化が重要です。予備の機器や回線を備えておくことで、緊急時に事業を継続できる可能性を高められます。メリットやデメリットを理解し、実施方法を知ることで、自社に最適なネットワーク冗長化の方法を選択できます。
予備の装置や回線で緊急時に備えるネットワーク冗長化
ネットワーク冗長化とは、同じ機能を持つ予備の回線や機器をあらかじめ準備することです。これにより、通信障害や機器故障など、緊急事態が発生した際に速やかに予備に切り替えてビジネスを継続できます。
現在、多くの企業では、システムが停止すると業務効率や収益に影響が及ぶだけでなく、企業の信頼性にも悪影響を及ぼしかねません。このような事態を防ぐためにも、冗長化に取り組むことをおすすめします。
ネットワーク冗長化の3つのメリット
ネットワーク冗長化には、事業の遅延や停止を防ぐ、サービスの競争力を強化する、負荷分散でパフォーマンスを向上させるといった重要なメリットがあります。ここでは、これらの3つのメリットについて詳しく解説します。
インシデント発生時にも事業を継続
機器やネットワーク回線に異常が発生してシステムが停止することがあります。ネットワークをあらかじめ冗長化しておけば、予備の機器・回線に切り替えることでダウンタイムを最小限に抑え、事業を継続できます。インシデント発生時でも事業を継続できるネットワークは信頼性が高まり、ビジネスの競争力を強化します。
BCP(事業継続計画)対策
地震や火災などの災害発生時にシステムが使用できるよう、ネットワークの冗長化が必要です。基幹システム、アプリ・Webサイトなどを止めないことはBCP(事業継続計画)に欠かせない要素です。BCPに必要な機器の導入や使用に際しては、中小企業向けの税制優遇を受けられる可能性もあります。
参照:税制優遇の紹介(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)
https://kyoujinnka.smrj.go.jp/guidance/tax_system.html
サーバーやシステムの負荷軽減
ネットワークの冗長化には、アクセスを分散してサーバーやシステムの負荷を軽減するメリットがあります。例えば、サイトにアクセスが集中することでシステムがダウンする際、冗長化していれば、負荷分散処理を行うことで特定の経路やサーバーにアクセスが集中しすぎず、ネットワークのパフォーマンスを向上させられます。
さらに、冗長化はサイバー攻撃対策としても有効です。例えば、DDoS攻撃でネットワークに多大な負荷がかかっても、冗長化することでトラフィックを分散し、帯域幅を増加させて攻撃の影響を最小限に抑えられます。
ネットワーク冗長化のデメリット
ネットワークを冗長化する際には、導入コストや運用保守の負担を考慮する必要があります。
まず、冗長化には機器や回線の購入費用、設置費用、電気代がかかります。また、冗長化の内容や規模に応じて高度な専門知識が求められるため、人件費も増加します。さらに、定期的な保守やアップデートが必要となり、運用保守の負担も増大します。
これらのコストと労力を考慮した上で、優先順位を決めて冗長化を進めることが重要です。
ネットワーク冗長化には構成と選定方法の理解が重要
ネットワークを冗長化する際の構成は、メイン機器と予備機器の設置方法や回線の稼働方法によって主に3種類に分けられます。予備を待機させておくアクティブ・スタンバイ(ホットスタンバイ、コールドスタンバイ)、そしてメインと予備を常に稼働させるアクティブ・アクティブです。
アクティブ・スタンバイ:予備危機を待機させる構成
アクティブ・スタンバイは普段は予備を使わずに待機させます。予備機器に電源を入れて待機させる方式をホットスタンバイ、普段は予備機器の電源をOFFにしておき、必要時に電源を入れる方式をコールドスタンバイと呼びます。
ホットスタンバイ
ホットスタンバイでは、予備機器にも常に電源を入れて待機状態にし、必要時に自動で切り替えます。また、同期も都度行います。これにより、切り替え時のダウンタイムが少ないのが大きなメリットです。しかし、障害時に確実に自動で切り替わるように設計する必要があり、事前の検証や動作確認も重要です。このように構成が複雑になるため、構築には手間と費用がかかるのがデメリットです。
この方法は銀行や証券、地方自治体などの金融・行政システム、病院やクリニックなどの医療業界、インターネットサービスプロバイダーや携帯電話会社といった通信業界など、常時稼働が強く求められる分野で多く使われます。
コールドスタンバイ
コールドスタンバイは、予備機器に電源を入れずに待機させ、必要時に電源を入れて起動させる方式です。この方式では、電源を入れてから予備機器が本格稼働するまでに必ずダウンタイムが発生します。一方で、自動同期や自動切り替えの必要がなくシンプルなネットワーク構成のため、構築費用や手間を減らせるメリットもあります。
限られた予算内でネットワーク冗長化を実現したい場合や、即時の稼働が必須でないシステムでの使用に適しています。
アクティブ・アクティブ:予備機器を常時稼働させる構成
アクティブ・アクティブは、同じ機能を持つ機器や回線を複数用意して、普段からすべて同時に稼働させる方式です。これにより、平常時は高速レスポンスが実現され、トラブル時も完全停止を回避できます。また、すべての機器が常に稼働しているため、設備投資が無駄なく有効利用されます。
この方法は、高可用性や負荷分散が常に求められる証券取引所やオンラインバンキング、SaaSなどのクラウドサービス、ISPなどの通信サービス、大規模なセールスプロモーションなどで一時的にトラフィックの負荷分散を行う必要がある場合などに適しています。
ネットワーク冗長化はレイヤごとに実施
ネットワークにはレイヤ(階層)があります。これは、ネットワーク通信に必要なプロトコルを役割ごとに分類し、層として整理したもので、7層に分けたOSI参照モデルがよく知られています。ネットワークのレイヤごとに以下のような冗長化の実施方法があります。
▼【階層別一覧】ネットワーク機器の種類・特長を解説
https://www.ntt.com/business/services/rink/knowledge/archive_05.html
レイヤ1:物理層(ネットワーク機器の電源など)
レイヤ1は物理層で、LANケーブルやコネクターなどの機器接続を担当します。一般的な冗長化手法としては、ネットワーク機器に複数の電源を搭載する電源冗長があります。
レイヤ2:データリンク層(スイッチ・NICなど)
レイヤ2は、機器同士の信号処理とデータの受け渡しを管理します。レイヤ2での冗長化には以下の方法があります。
NICチーミング
NICチーミングは、複数のネットワークインターフェースカード(NIC)を1つの論理インターフェースとして束ね、帯域幅を拡張したり、障害時に回線を切り替えたりする技術です。
リンクアグリゲーション
リンクアグリゲーションは、複数の物理回線を1つの論理回線として扱う技術で、処理スピードの向上や回線の冗長化を実現します。これにより、回線の障害時にも別の回線で通信を継続できます。
フォールトトレランス
フォールトトレランスは、メインとバックアップの回線を用意し、障害発生時に自動的にバックアップ回線に切り替える仕組みです。
マルチホーミング
マルチホーミングは、複数のプロバイダーの回線を契約し、一方の回線に障害が発生してももう一方の回線で接続を維持する方法です。
スパニングツリープロトコル(STP)
スパニングツリープロトコルは、ネットワークの一部分でデータ経路を遮断し、ループが発生しないようにします。これにより、回線がダウンすることを防ぎ、安定した接続を維持します。
スタック
スタックは、複数のスイッチを一体化して冗長化する仕組みで、1つのスイッチが故障しても他のスイッチでネットワークを維持できます。スタック接続されたスイッチは一括管理が可能です。
レイヤ3:ネットワーク層(ルーター・サーバーなど)
レイヤ3は、社外のLANやネットワークとの通信を管理します。主な冗長化方法には、以下があります。
VRRP
VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol)は、複数のルーターを1つの仮想ルーターとしてまとめ、1つの機器が故障しても他のルーターが自動的に引き継ぐプロトコルです。
ECMP
ECMP(Equal Cost Multipath)は、複数の経路に負荷を分散させ、効率的に通信を管理する方法です。これにより、複数の経路を使用してデータを分散し、ネットワークのパフォーマンスを向上させます。
レイヤ4:トランスポート層(サーバーなど)
レイヤ4は、アプリケーション間のデータ送受信を管理します。主な冗長化技術にはDSR(Direct Server Return)があり、これはデータのやり取りを複数のサーバーに分散し、ネットワーク負荷を軽減する仕組みです。
レイヤ7:アプリケーション層(サーバーなど)
レイヤ7は、ユーザーとネットワークが直接やりとりする層です。冗長化にはリバースプロキシーサーバーが使われます。複数のWebサーバーを統合して外部からのアクセスを一元管理します。これにより、負荷を分散し、サイバー攻撃に対する防御を強化します。
柔軟なネットワーク環境を実現するならdocomo business RINK®
docomo business RINK®は、ネットワーク環境とゼロトラストセキュリティを一括してクラウドで提供する統合ネットワークサービスです。いつでもどこからでも安心・安全・簡単にアクセス可能な環境を実現します。
このサービスは、固定回線とモバイル通信という異なる種類の回線を組み合わせることで、ネットワーク冗長化を実現します。固定アクセスに障害が発生した場合でも、高速5G回線を利用して継続することが可能です。
docomo business RINK®は、最短10営業日で5Gモバイル回線を開通でき、その後固定回線を追加することも可能です。その場合、5G回線はそのままバックアップ回線として利用できます。
さらに、安全にデータをやり取りするためのシステムが構築されているため、リモートやテレワーク環境下でも快適に利用できます。複数のWeb会議を同時開催するなどして高負荷がかかっても、Web上の管理画面を操作して帯域を拡張したり、Web会議に使う通信を切り分けたりすることで、最適なICT環境を確保します。
まとめ
現在、多くの企業では社内システムの大半がネットワークに接続されて稼働しています。ネットワークのアクシデントで業務システム全体が停止すると、業務効率や収益、社会的な信頼に大きく影響する恐れがあります。不測の事態に備えるために、ネットワーク冗長化はぜひ検討したい対策です。
柔軟で信頼性の高いネットワーク環境を実現するならdocomo business RINK®がおすすめです。固定回線と無制限の5Gモバイル通信の両方を利用でき、セキュリティ対策も万全です。また、最短10営業日で導入可能です。ICT環境を最適化し、ネットワークの信頼性を高めてみませんか。
この記事の目次
- 予備の装置や回線で緊急時に備えるネットワーク冗長化
- ネットワーク冗長化の3つのメリット
- ネットワーク冗長化のデメリット
- ネットワーク冗長化には構成と選定方法の理解が重要
- ネットワーク冗長化はレイヤごとに実施
- 柔軟なネットワーク環境を実現するならdocomo business RINK®
- まとめ
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK®
サービスに関するご質問など
お気軽にお問い合わせください
資料ダウンロード
-
選べるネットワーク、選べるセキュリティ
docomo business RINK®
サービスに関するご質問など、お気軽にお問い合わせください
サービス詳細情報は こちら








 JP
JP