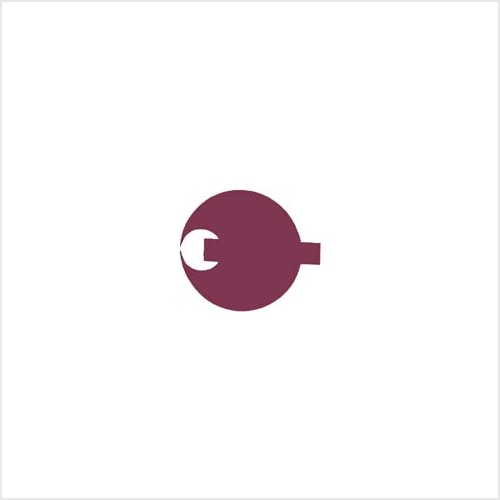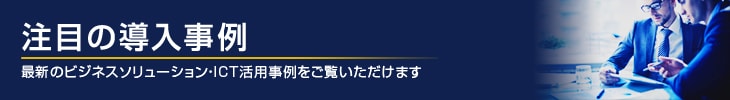奈良県

奈良県
総務部 管財課 企画係
係長
糸井敏郎氏
「私たちの業務環境は観光地が近く、電話がつながりづらいのですが、こまめに庁舎内の電波状況を調査し、すぐに改善していただけるドコモビジネスの手厚いアフターフォローには感謝しています」

奈良県
総務部 管財課 企画係
主任主事
中西馨氏
「従来の固定電話に比べてガラホのいいところは、電話を受けられないときでも着信履歴が残ることです。手が空いたらすぐに折り返しの電話をするなど、柔軟な対応ができるとの声をよく聞きます」
課題
働く場所を選ばない業務環境を構築したい
庁舎内のABW※に向けた業務環境の整備が急務に
※ ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング):仕事の内容や気分に合わせて働く場所や時間を自由に選べる働き方
日本の歴史や文化の礎が築かれた日本の始まりの地として知られる奈良県は、歴史や文化施設のさまざまな魅力を備えた日本の「まほろば」(古語で丘や山に囲まれた稔り豊かな住みよいところ)である。このような歴史や伝統に重きを置く一方、奈良県では革新的な施策を続々と打ち出している。たとえば、働く人が健康でやりがいを持ち、いきいきと働けるウェルビーイングな業務環境の実現に向けて『地域において良い人材を集め育成することを目指した良い職場づくりの推進に関する条例』という、条例を策定している。「この条例のもと、健康が基本的価値となる組織の構築、創造的で生産性を高める体制の整備、円滑に外部とのつながりや内部の交わりを強固にする体制の整備などを行っています」と、総務部管財課企画係の係長 糸井敏郎氏(以下、糸井氏)は説明する。
この取り組みの一環として、同県では生産性の高い職場環境の構築に向けた庁舎の改修工事を進め、2025年度中の完成を目指している。これまで同県の業務環境は3つの障壁に縛られていた。1つめは紙の書類、これは電子化と庁内の書棚撤去でペーパーレス化が大幅に進んでいる。2つめのPCとネットワークについてはLTE環境の整備により、どこにノートPCを持ち運んでも仕事ができる環境の整備を終えている。「そして最後に残っていたのが電話です。行政の業務は電話への依存度が高く、従来の働き方から脱却するには、固定電話の代替手段として外線が受けられる、内線通話もできるモバイル環境の構築が必要だと考えていました。現場の混乱を避けるために既存の電話交換機や電話番号を流用、あまり従来の電話システムと使い方を変えずに移行することも重要でした」(糸井氏)
そこで奈良県がモバイル環境で使用する端末に求めた条件は、電話での通話に絞ったものだった。情報セキュリティの観点に加え、ランニングコスト抑制のためにデータ通信は最初から想定していなかった。「ノートPCで安全にデータ通信ができるので、通話機能に絞ったケータイで充分なのです。その上で電話交換機を通過しない外線発信の規制、突発的な人事異動などでのクイックな対応などが必要でした」(糸井氏)
対策
既存の電話交換機が活用できる「オフィスリンク」を導入
内線電話を携帯化、コスパの良いドコモケータイを1人1台貸与
県が求める仕様を確定し一般競争入札で決定したサービスが、ドコモビジネスの「オフィスリンク」だった。既存の電話交換機とドコモのネットワークをつなぎ、ドコモの携帯電話が内線として利用できるサービスだ。インターネット環境に依存しないクリアな音声品質、クラウド・オンプレミス100種以上の電話交換機に対応、端末1台に携帯番号・内線番号を集約できるといった特長を持っている。「電話交換機の更新にはコストや時間がかかります。従来の電話交換機を活かし、スピーディに新たな電話システムに切り替えられる点を高く評価しています」(糸井氏)
オフィスリンクを基盤とした新たな電話システムは、先行してABWを実践している50人程度の部署にスモールスタートで導入された。「ここで試験的な運用をしながら、新たな電話システムの課題や改善ポイントなどを吸い上げて、私たちの業務環境にフィットさせる調整を行いました。並行して職員への周知と使い方のレクチャーも実施、ドコモビジネスからわかりやすいマニュアルや動画の提供があったため、職員からの問い合わせも少なくスムーズに試験運用を開始できました」(糸井氏)
このようにして新たな電話システムは、業務環境の整備とセットで導入され、徐々に庁舎内に広がっていった。職員に好意的に受け入れてもらえたものの、実際に職員自身が利用する立場になると少し話が違ってくることを実感したと語るのは、糸井氏とともに電話システムの刷新を担当した中西馨氏(以下、中西氏)だ。「端末を渡す際には、新たな運用方法などの理解を得るための説明が必要です。内線モバイル端末は固定内線電話と異なり、各人に運用を含めた管理をしっかりやってもらう必要があるため、特にその点を重点的に説明しました。骨の折れる対応でしたが、電話システムの変更は職員の働き方が変わることと考えれば楽しく、やりがいがあったことも事実です」
個別対応という地道な取り組みも功を奏し、内線電話のモバイル化は着実に庁舎内に根付いていく。
効果
フリーアドレス、在宅勤務といった多様な働き方が可能に
1人1台の電話により取り次ぎ、折り返しといった無駄を軽減
業務環境整備の進捗に合わせて、オフィスリンクをベースにした新たな電話システムは徐々に拡大。2025年1月の時点で約700人強の職員がドコモケータイを利用している。「2025年度末には約2,000人への配布が完了する予定です」(糸井氏)

内線電話のモバイル化により、想定通りの効果が出始めているようだ。奈良県では働き方改革の推進に向けて在宅勤務の申請を簡略化、前日にPCで申し込める仕組みになっている。「よく私自身も在宅勤務を利用するのですが、これまでは個人の携帯電話で外部に電話をかけることに抵抗がありました。しかし、内線番号で庁舎内の職員と通話することができ、外線発信する際も県の番号で発信することで、相手にも安心して受け入れてもらえるなど、今回の施策により、モバイルPC(ドコモネットワーク)と併せて普段庁舎で業務している環境と同等の環境で在宅勤務ができるようになったと感じています」(糸井氏)
「1人1台、電話が持てるようになり、相手を特定して電話がかけられるため、取り次ぎの手間や折り返しのストレスがなくなったという声も上がっています。在宅勤務やABW化の利用についても好意的な意見が多いです。私自身も電話がつながる頻度が高くなり、以前に比べるとかなりスムーズに仕事が回るようになったと感じています。もちろん、在宅勤務を利用する機会も増えました」(中西氏)
業務環境の整備や今回の内線電話のモバイル化により、奈良県内または県外の自治体から「見学したい」「話を聞きたい」という依頼を受けることもある。「見学に来られた方がまず驚かれるのは、既存の電話交換機を活かしたコスパの良い構成です。なぜスマホにしなかったのかと聞かれることもあります。スマホだと持ち出し制限などのセキュリティ対策で柔軟な運用が難しい、ケータイの方がスマホより大幅に導入コストを抑えられると説明すると、みなさん納得されますね。電話に機能を絞った端末には、ほぼ機密データは入っておらず、万一、落としてもインシデントにつながることはありません」(糸井氏)
現在、奈良県ではもう1つの懸案事項だった電話が集中する窓口の応対業務改善に向け、新たな電話システムにナビダイヤルを連携させた試験運用に取り組んでいる。ナビダイヤルとはドコモビジネスが提供する全国共通の「0570」に続く6桁の専用番号を利用して、コール振り分けやIVR(音声自動応答)であらかじめ指定した電話番号につなぐサービスだ。電話受付業務の効率化や顧客窓口設置を検討する自治体や企業に数多く利用されている。試験運用では応対時間の短縮といった効果も出始めており、業務のさらなる効率化に向けて将来的な全庁導入を検討している。
「多様な働き方が選べる時代を迎えています。今回の施策は抜本的に行政の働き方を変える方法の1つだと感じています。奈良県の事例が全国の自治体に広がって行けば嬉しく思います。」(糸井氏)

奈良県

概要
働く人が健康でやりがいを持ち、いきいきと働けるウェルビーイングな業務環境の実現に向けて、健康が基本的価値となる組織の構築、創造的で生産性を高める体制の整備などに取り組んでいる。
(PDF形式/878 KB)
(掲載内容は2025年3月現在のものです)
関連リンク








 JP
JP