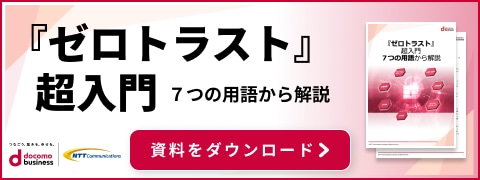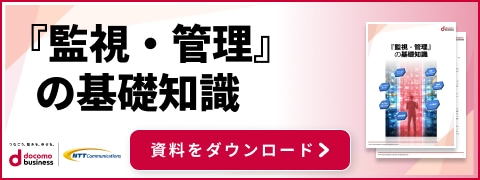店舗DXとは?今こそ始めるべき理由
~基本から実践までまとめて解説
デジタル化の波によって小売業界が変革されるなか、「店舗DX」は単なるトレンドではなく生き残り戦略として重要視されています。店舗DXによって得られるさまざまなメリットのために、多くの企業が取り組みを進めています。しかし、「店舗DXとはなにか」「なぜ必要なのか」についてわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、店舗DXの基礎知識から必要とされる背景、導入のメリット、課題・注意点、顧客体験を向上させる店舗DX戦略や具体例についてまで解説します。

目次
店舗DXとは?
はじめに、店舗DXの概要と合わせて、その目的や期待される効果について解説します。
店舗におけるデジタルトランスフォーメーション
店舗DXとは、店舗ビジネスにおいてデジタル技術を活用しながら、業務の効率化にとどまらず、顧客体験やビジネスモデルそのものを変革する取り組みです。
データやデジタル技術を活用することにより、在庫管理や売上分析、顧客データの収集・分析が可能になります。これらは、リアルタイムでの意思決定やパーソナライズされたサービスの提供を実現するための、経営上の鍵です。
店舗DXは単純なIT化や業務のデジタル化にとどまらず、店舗経営やサービス提供のあり方そのものを変革することが特徴といえます。
店舗DXの目的と期待される効果
店舗DXの主な目的は、店舗における業務プロセス改善と顧客体験価値の向上です。つまり、店舗DXは2種類に大別されることを念頭に置きましょう。
目的の1つめは「店舗運用に関わるDX」です。業務効率化・省人化を目的とし、会員カードの電子化やアプリ活用、キャッシュレス決済、電子タグ、デジタルサイネージ、セルフレジ、AI(人工知能)カメラを利用した動態分析などがDXの主な手段となります。
2つ目は「店舗体験に関わるDX」です。こちらは店舗そのものをオンライン化するなどして、お客さまの利便性を高めることを目的としています。オンラインによる注文や予約システム、バーチャルショップなどがDXの主な手段です。
これらのように、店舗DXは目的に合わせて選択すべき手段も異なります。しかし、最終的にはどちらも店舗の収益性や競争力を向上させるものです。
店舗DXが必要とされる理由

店舗DXが必要とされている背景には、さまざまな要因があります。これらの要因に対応するため、多くの企業がデジタル技術を活用した変革に取り組んでいるところです。ここでは、主要な4つの要因について解説します。
深刻化する人手不足と労働力確保の課題
2022年には小売業における不足要員は24万人を超え、全産業のなかでも特に人手不足が深刻な状況です。また、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少し続けており、2050年には2021年に比べて29.2%減となる、5,275万人に減少すると予測されています。
このことから将来的にも人手不足は続き、より悪化する可能性が高いことがわかるでしょう。また、コロナ禍を契機に働き方の価値観が大きく変化し、柔軟な働き方が一般化したことも少なからず影響を与えています。
実店舗では出勤やシフト勤務が不可欠であるため、求職者のニーズとのギャップにより店内の人材確保が一層困難となっています。このような課題に対応するためには、店舗DXが必要です。
店舗DXの実現にはIT人材も欠かせません。しかし、現在ではそのIT人材も不足しているといった状況です。IT人材の不足に関するより詳細な説明については、こちらの記事をご覧ください。
消費者の購買行動の多様化
消費者による購買行動の多様化も、店舗DXが必要とされる要因の1つです。消費者は「いつでも・どこでも」買い物ができる環境とその利便性を求めるようになり、その結果として購買体験のデジタル化が進んでいます。
SNSやECサイトの普及によって情報収集の手段や購買チャネルが多様化するとともに、店舗で商品を確認してECサイトで購入する「ショールーミング」などの新しい購買行動も増加中です。
このように消費行動や価値観が多様化するなかで、小売業界では市場競争が激化しています。他社と差別化を図り優位性を確保するために、顧客データの活用やニーズに応じた商品・サービスの開発が不可欠となっており、データ主導(データドリブン)の経営への転換が求められています。
ECサイトの台頭による実店舗の役割変化
ECサイトの急速な普及により、実店舗での販売機会は減少傾向です。そのようななか、実店舗の役割が現在では「商品を販売する場」から「ブランド体験やお客さまとの接点を創出する場」へと変化しています。
具体的には、体験型店舗やショールーミング店舗などのように、新しい業態が登場しています。店舗DXによる新たな顧客体験の提供が不可欠であり、ECと実店舗の連携によるオムニチャネル戦略が重要です。
競争が激化する小売市場での差別化の必要性
Amazon、楽天、メルカリなどといったECプラットフォームの成長により、小売業界での競争が一段と激化しています。プライベートブランド(PB)の開発や価格での競争だけでは差別化が難しく、店舗DXを活用した「顧客体験の向上」や「顧客ロイヤリティの強化」が生き残りの鍵です。
お客さまごとの購買データや行動データを活用し、パーソナライズされたサービスや新しい顧客体験を提供することが、今後の小売業に求められる戦略の1つといえるでしょう。
店舗DXを導入するメリット

店舗DXには、業務効率化やコスト削減、顧客体験の向上などさまざまなメリットがあります。
多くの企業が店舗DXの導入を検討するなか、業務を効率的に行いながら、顧客に寄り添った質の高い接客をどう維持・向上させるかが課題となっています。業務負担の軽減と接客品質の両立は、現場にとって大きな変革です。実際、店舗ではスタッフの作業を支援するデジタルツールの活用が進んでおり、現場の最適化に貢献しています。ここでは、そうした店舗DXの導入によって得られるメリットについて詳しく紹介していきます。
人手不足の解消
店舗DXの一環として、店舗業務にデジタル技術を導入することによりレジ業務や予約業務などを効率化して、省人化が実現できます。デジタル技術の導入により業務分担が容易となり、従業員一人ひとりの負荷を軽減することも可能です。
さらに、複数人で業務を分担して1人当たりの負担を減らす「ワークシェアリング」も推進しやすくなります。
コスト削減による収益性の改善
店舗DXによる業務効率化や自動化が実現すれば、人件費などのコスト削減につながります。例えば、POSシステム導入による効率化や予約管理システムの自動化による人件費の削減、在庫管理システム導入による食材ロス削減などが例としてあります。
これまで人手で行っていた工程をデジタルツールにより自動化すれば、さまざまなコスト削減が実現され、最終的には店舗の収益性向上へとつながります。
データ分析による顧客理解の深化
店舗DXを進めるためには、お客さまに関する情報の収集が欠かせません。収集する情報は、お客さまの住所や名前といった属性情報のほか、購買履歴などの行動情報などです。収集した情報は、POSシステムや顧客管理システムを導入すると、情報の管理だけでなく分析もできるようになります。情報分析の結果、お客さまのニーズに合わせた商品・サービスの開発や、集客のための効果的な施策が立案可能となり、売上の向上へとつながるでしょう。
データドリブンな経営により顧客理解が深化し、売上だけでなく顧客満足度の向上も期待できます。
新たな顧客体験の創出による競争力強化
店舗DXを通じて顧客体験を向上させる最も直接的な方法は、購買プロセスの簡素化とスピードアップです。お客さまがストレスなく買い物できる環境を提供することによって、顧客満足度の向上につながります。
加えて、前述のデータ分析結果と組み合わせることにより、パーソナライズされたサービスも導入できます。お客さまに新たな価値を提供することができれば、リピーターの増加や収益の向上が見込めるため、競合他社との差別化にもつながるでしょう。
店舗DXの導入における課題・注意点
店舗DXは多くのメリットをもたらす反面、認識しておくべき課題・注意点も存在します。これらの課題を事前に把握して適切な対策を講じることが、店舗DXを成功させるための鍵となります。
初期投資・ランニングコストの負担
最新のデジタルツールやシステムを導入する際には、ハードウェアやソフトウェアの購入費用や設置工事費などの初期費用がかかります。また、サブスクリプション型の課金体系のサービスも多く、月額利用料や保守費用といったランニングコストも発生します。
加えて、これらを導入後すぐに効果が表れるとは限らず、費用対効果が見えにくいことも課題の1つです。初期費用やランニングコストを事前に試算して、中長期的な視点で投資の回収計画を立てることが重要になります。
従業員のITリテラシー向上と研修の必要性
店舗DXの一環としてデジタルツールなどを導入しても、実際に利用するのは従業員であるため、使い方や運用方法についての教育が欠かせません。適切に利活用できなければ、十分な導入効果は得られないでしょう。
また、場合によっては従来の業務フローやプロセスを見直さなければならず、従業員の理解や協力を得ることが困難な可能性も考えられます。店舗DXを推進する際には、研修や教育の時間・コストも含めて計画し、現場の意見を取り入れながら段階的に進めることが求められます。
セキュリティとプライバシー保護の課題
デジタル化が進むことによって多様な情報を取り扱えるようになると同時に、情報漏えいなどに対するセキュリティリスクへの備えが必要になります。データの暗号化やアクセス権限管理、システムの定期的なアップデートなどといったセキュリティ対策が必須です。
合わせて、個人情報の適切な取り扱いやプライバシー保護のために、プライバシーポリシーの整備や従業員への情報セキュリティ教育も欠かせません。技術的な対策と同時に、人的な対策も十分に行うことが重要です。
顧客体験を向上させる店舗DX戦略
店舗DXの主要な目的の1つは、顧客体験の価値を高めることです。ここでは、顧客体験を向上させるための具体的な戦略について解説します。
オムニチャネル戦略による顧客接点の拡大

オムニチャネル戦略とは、実店舗、ECサイト、モバイルアプリ、SNSなど、あらゆるチャネルを連携させてお客さまとの接点を拡大する事業手法です。お客さまとの接点を多様化してそれらを連携し、あらゆる販売・流通経路を統合的に管理して多角的にアプローチします。
お客さまは商品購入時に各種のチャネルを意識することなく、どのチャネルからでも同じサービスや情報を受けられるため、シームレスな購買体験が実現します。各チャネルを統合管理することにより顧客データを一元管理できるほか、パーソナライズされたサービスやプロモーションの実施も容易になります。
近年では、オンラインとオフラインの両側面からの戦略的アプローチが必要です。お客さまの利便性と満足度を高めるためのオムニチャネル化は、小売業にとって不可欠な戦略となっています。
モバイルアプリを活用した新たな顧客体験の創出
モバイルアプリの導入は、店舗DXにおいて顧客体験を大きく向上させる効果的な手段です。例えば、モバイルオーダー機能を活用することによって、来店前の事前注文や決済が可能となり、店舗での待ち時間を削減できます。
そのほかにも、アプリを通じたクーポンの配信やプッシュ通知、デジタル会員証やポイント付与などといった機能を提供することにより、お客さまとの継続的なコミュニケーションやリピーターの獲得へとつなげられます。
また、アプリ経由でお客さまごとの注文履歴や来店頻度などのデータを自動的に収集できるため、混雑予測や個別マーケティング施策の立案に活用することも可能です。これらの施策は、顧客体験の向上を通じて、店舗の売上向上へとつなげることができます。
AR・VRを活用した没入型ショッピング体験
AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術を活用した没入感のあるショッピング体験は、店舗DXの先進的な取り組みとして注目されています。お客さまはARによるバーチャル試着によって自分に似合う商品を確認したり、VR空間でバーチャル店舗の商品を手に取るような体験をしたりすることが可能です。
このように仮想的な試着や体感でもリアル体験と同等な購買体験を得られ、実店舗とオンラインの垣根を超えた新たな購買体験を提供できます。特に新しい技術や体験に抵抗感の少ない若年層やデジタルネイティブ世代の、新規顧客獲得につながるでしょう。
AR・VRを活用した没入型の体験は、購入前の不安を軽減して満足度や購買意欲を向上させるだけでなく、ブランドのエンゲージメント強化にも有効です。
店舗DXの基盤となる多店舗のネットワークを安価に監視する
「多店舗ネットワークマネジメント」
店舗DXの一環としてデジタル化を進める場合には、ネットワークの運用・管理が重要な要素となります。ネットワークはシステム間・店舗間をつなぐほか、業務の根幹を担う存在であるためです。
ネットワークは常時つながっていることが前提であり、一度切断されると業務に多大な影響をもたらしかねません。そのため、適切な監視・運用を継続的に実施する必要があります。
NTTドコモビジネスでは、多数の店舗を展開する流通・サービス業などのお客さま向けに、ネットワーク監視保守サービス「多店舗ネットワークマネジメント」を提供しています。お客さまのIT部門に代わり、24時間365日体制で多店舗ネットワークの監視・管理、故障対応などを行うサービスです。
複雑化している関連ベンダーの統制や、オンサイト保守などもワンストップで対応可能で、7万店舗・23万ノードを超える国内最大級の運用実績があります。多店舗経営ならではの課題に特化したサービスであるため、フランチャイズ展開などによるシステム監視・管理にお困りの際は、ぜひ1度ご相談ください。
まとめ
店舗DXは、人手不足や消費者ニーズの多様化、ECの台頭など、小売業界が直面している課題を解決し、業務効率化や顧客体験の向上を実現するための重要な取り組みです。
店舗DXを進める際は、日々の店舗運営にどのような変革が必要かを見極め、自社にとって最適なソリューションを選ぶことが成功の鍵です。例えば、業務プロセスの自動化によって時間を短縮できれば、接客や戦略的業務への集中が可能になり、目に見える成果につながります。すでに成果を上げている成功事例を参考にしながら、自社に合ったDXのあり方を検討することが不可欠です。
初期投資や従業員教育、セキュリティ対策などの課題もありますが、店舗DXを進めることで競争力を高めることが可能です。今後も進化するデジタル技術を柔軟に取り入れ、持続的な成長を目指すことが店舗経営の鍵となるでしょう。
デジタルトランスフォーメーションは「企業が生き残るための鍵」といわれていますが、IT環境の複雑化による運用負担の増加が課題となりやすくなっています。その負担を軽減するために注目されている施策が「ゼロタッチオペレーション」です。ゼロタッチオペレーションは店舗DXにも通じる話であるため、以下の記事も合わせてご覧ください。