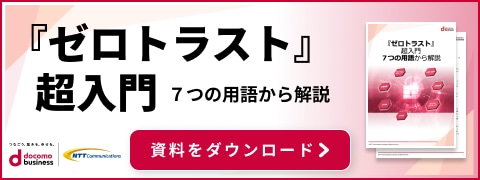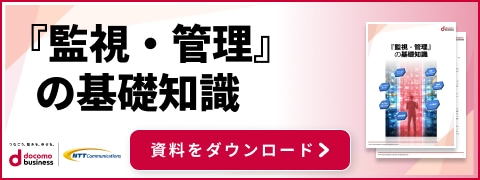Fit&Gap分析とは?
システム導入で失敗しないためのFit&Gap分析の
目的・手順・注意点まとめ
システムを導入する際には、自社の業務にどの程度適しているかを見極めることが重要です。Fit&Gap分析を通じて業務要件とシステム機能の間のズレを特定することによって、企業ニーズに最も適したシステムの選択と円滑な導入・運用・管理を可能にします。
この記事は、Fit&Gap分析の実施を検討している方向けの記事です。Fit&Gap分析の概要から必要とされる背景、目的や実施の手順、失敗を避けるための注意点などについて解説します。

目次
Fit&Gap(フィットアンドギャップ)分析とは?

Fit&Gap分析は、ERPなどのパッケージシステムを導入する際に、自社の業務要件とシステムの標準機能との間の適合度を評価するための重要な手法です。ここでは、Fit&Gap分析の基本的な概念、要件定義やFit to Standardとの違いについて解説します。
Fit&Gapにおける「Fit(適合)」と「Gap(乖離)」の意味
Fit&Gap分析における「Fit」「Gap」とは、パッケージシステムなどの標準機能と自社の業務要件を比較した際に見られる以下の部分を指します。
- 適合している部分:Fit
- ズレがある部分:Gap
自社が必要とする機能と、導入を予定しているシステムが備える機能を比較し、どの程度適合または乖離しているかを明確にするのがFit&Gap分析です。
Fit&Gap分析の目的と期待される効果
Fit&Gap分析のおもな目的は、企業が求める要件とシステムが提供する機能がどれほど一致しているのかを分析し、カスタマイズの要否を判断することです。
分析結果は、自社に最適なシステムを選定するための判断材料として活用可能です。Fit&Gap分析によって、システム導入後の使用感におけるミスマッチや、想定外のカスタマイズコストの発生などの問題を未然に防げるでしょう。
Fit&Gap分析と要件定義の違い
要件定義はシステム開発の初期段階で行なわれるものであり、ユーザーやクライアントが必要とする機能や性能を把握し、それらをシステム上で実現するための設計指針を決定する作業です。要件定義はシステム開発における工程の一つであるのに対し、Fit&Gap分析はシステムを選定するための分析手法である、という違いがあります。
また、要件定義は依頼先を決めたうえで、発注側と受注側が協力して行うものですが、Fit&Gap分析は多くのケースで発注側の担当者が主体となって行ないます。
Fit&GapとFit to Standardの違い
Fit to Standardとは、システムの基本機能に合わせて業務の流れを再構築するというアプローチです。システムを企業の業務に合わせて改変することはなく、業務の流れをシステムの標準仕様に合わせて変更します。
一方、Fit&Gap分析にもとづくアプローチは、基本的には業務に合わせてシステムをカスタマイズすることを前提としています。そのため、両者の違いはギャップ部分に対してシステム側を適応させるか、業務側を適応させるかの違いといえるでしょう。
どちらのアプローチが適しているかは、企業の状況や導入するシステムの特性によって異なるため、慎重に判断する必要があります。
Fit to Standardについてはこちらの記事でも解説しているため、詳しく知りたい方は合わせて合わせてご覧ください。
Fit&Gap分析が必要とされる背景

Fit&Gap分析の重要性を理解するために、それが必要とされる背景について理解しておくことは大切です。ここでは、その主要な理由について紹介します。
業務プロセスとシステム機能のミスマッチ問題
パッケージシステムは一般的に標準的とされる機能を持っており、各企業の多様で複雑なプロセスに完全に適合することは稀です。このミスマッチがあるまま導入を進めると、業務効率化やコスト削減といった本来の目的を果たせず、導入効果が薄まってしまうおそれがあります。
業務プロセスとシステム機能のミスマッチは、システム導入プロジェクトが炎上する主要な原因の一つとなっているため、事前の分析と対策が不可欠です。
カスタマイズコストと導入リスクの増大
標準機能では対応できない部分をカスタマイズすると、開発コストや保守費用が大幅に増加し、導入時のリスクも高まります。特に、カスタマイズ範囲が当初の想定を超えて拡大すると、予算やスケジュールの大幅な超過を招きかねません。
過度なカスタマイズを避け、標準機能を最大限に活用するためにもFit&Gap分析が必要であり、結果として長期的な視点でのTCO(総所有コスト)削減にもつながります。
オンプレミス型からクラウド型への移行による分析手法の変化
近年、オンプレミスからクラウドへのシステム移行が進むにつれ、Fit&Gap分析の手法も変化しています。
クラウドサービスでは、標準機能を活かしつつ業務プロセスを見直す「Fit to Standard」の考えが浸透しています。しかし、依然として業務特性に応じたFit&Gap分析は欠かせません。
クラウドサービスの特性として柔軟性や拡張性の高さが挙げられますが、近年ではこれらの要素も含めた新たな分析の視点が必要になっています。定期的な機能アップデートやセキュリティ対策の強化などといった観点も採り入れ、総合的に分析・評価することが重要です。
Fit&Gap分析の進め方・手順

Fit&Gap分析は、システム導入を成功させるための重要なプロセスです。ここでは、効果的にFit&Gap分析を実施するための手順を、6つのステップに分けて解説します。
STEP1:システム要件の洗い出しと整理
Fit&Gap分析の最初のステップでは、自社がシステム導入によって実現したい要件や必要とする機能を網羅的に洗い出す作業が必要です。既存の業務フローを整理し、システム導入によって改善したいポイントや効率化したいポイントを明確にします。
現場の声を直接聞くヒアリングも大切であり、実際のシステム利用者から意見を広く集めることによって、要件の抜け漏れを防げます。
この段階で要件が明確でないと、システム導入後に「思っていた機能がない」などといった問題が発生する可能性があります。そのため、要件の洗い出しと整理を入念に行うようにしましょう。
STEP2:パッケージシステムの機能調査と比較分析
STEP1で洗い出した要件を満たせるかどうかという観点で、候補となるパッケージシステムをいくつかピックアップし、それぞれのシステムが有している機能の調査を行ないます。この段階で、各システムの標準機能が自社の要件をどの程度満たしているかについて詳細に調査することが重要です。
調査に際しては、ベンダーへのRFI(情報提供依頼書)の発行や、デモの実施依頼を行うと効果的です。特に重要な機能については実際にデモを実施することにより、カタログやWebサイトだけではわからない操作性や画面構成なども確認できます。
STEP3:FitとGapの判定基準の設定
システム要件と各パッケージ機能を比較する際には、明確な判断基準を設けることが重要です。例えば、要件を満たしている場合は「◯」、部分的に満たしている場合は「△」、満たしていない場合は「×」などの記号で評価します。
また、洗い出した要件を必須要件と希望要件に区別し、それぞれの重要度に応じた評価基準を設定するようにしましょう。例えば、必須要件には大きな重み付けをするなど、単純な◯×の数だけでなく、要件の重要度も加味した評価方法を採用することをおすすめします。
STEP4:Gap部分への対応策検討(カスタマイズ・業務変更・運用対応)
標準機能だけで自社の要件を完全に満たせるシステムは稀であり、ほとんどの場合はギャップが生じます。このギャップ部分への対応策について検討し、それぞれのコスト・期間・実現可能性などを評価することが重要です。
ギャップ部分への対応策としては、主に次の3つの方法が考えられます。
- パッケージに追加で開発を行う(カスタマイズ)
- 業務を標準機能に合わせる(Fit to Standard)
- 運用で対処する
特にクラウド型のシステムではカスタマイズが制限されていることが多いため、Fit to Standardの考え方が重要になってきます。詳しくは、こちらの記事も合わせてご覧ください。
STEP5:Fit&Gap分析表の作成と評価
Fit&Gap分析の結果は、表形式でまとめるとわかりやすくなります。この表には、自社が求める機能の一覧と各パッケージの対応状況、ギャップ部分の対応策などを記載します。
この分析表を作成することによって、各パッケージシステムの強みや弱み、導入にあたってのリスクポイントが可視化され、関係者間での情報共有や意思決定がスムーズになります。
STEP6:複数パッケージの比較検討と選定
最終ステップでは、Fit&Gap分析の結果に加えて、導入コスト・保守費用・ベンダーのサポート体制・将来的な拡張性なども踏まえて総合的に評価し、最適なパッケージを選定します。
TCOの観点による評価も重要であり、初期費用だけでなく運用保守費用、将来的なアップグレード費用なども含めた長期的なコスト試算を行ないましょう。最終的な選定結果は、経営層を含めた関係者に報告し、合意を得たうえで導入計画の策定へと移行します。
TCOについてはこちらの記事でも詳しく解説しています。TCOの基本的な概念や削減方法などについて解説しているため、合わせてご覧ください。
Fit&Gap分析の成功事例と失敗回避のポイント
適切なFit&Gap分析のために、実際の成功事例から学ぶべきポイントと、失敗を回避するための重要な教訓について解説します。
成功例に見る丁寧な要件整理と関係者巻き込み
多くの成功事例で共通している点は、システム導入前に自社が求める要件を詳細に洗い出し、しっかりと整理できていることです。例えば、ある製造業では現場の作業フローを徹底的に可視化し、必要な機能の優先順位を付けたうえでシステム選定を進めたことにより、導入後のユーザー満足度が大幅に向上しました。
また、情報システム部門だけでなく、実際にシステムを利用する全部署の担当者からヒアリングを行ない、現場の意見を十分に反映させることが重要です。幅広い関係者を巻き込むことによって、システム導入後の「思っていた機能がない」といった不満を未然に防ぎ、スムーズな運用へとつなげることができます。
失敗事例に学ぶ製品理解不足と過度なカスタマイズ
失敗事例では、導入するパッケージの機能や特性に対する理解不足が原因となっているケースが多く見られます。製品知識が不十分なまま分析を進めると、業務プロセスとの整合性を正確に判断できず、結果としてミスマッチが生じてしまいます。
また、既存の業務プロセスを維持することに固執した結果、過度なカスタマイズやアドオン開発へとつながるケースも少なくありません。このような失敗を避けるためには、製品の機能を十分に理解したうえで、本当に必要な要件とそうでない要件を見極めることが求められます。
標準機能を活かす業務プロセス変更の効果
Fit&Gap分析でギャップが生じた場合、必ずしもカスタマイズすることが最適解とは限りません。特に近年では、Fit to Standardの考え方にもとづくアプローチが注目されています。
業務プロセスの見直しを通じて標準機能を最大限に活用することによって、カスタマイズコストを抑えつつシステムのパフォーマンスを最大化することが可能です。特にクラウド型ERPの場合、カスタマイズが制限されていることが多いため、Fit to Standardの考え方はより重要となります。
Fit&Gap分析における注意点とよくある課題
Fit&Gap分析を成功させるためには、いくつかの注意点と課題について理解しておくことが重要です。ここでは、主要な注意点・課題について解説します。
全システム利用者からの意見収集の重要性
システム主管部門の意見のみを聞いて、システム利用者である他部署の意見を聞かなかった場合、実際の利用者にとって使いづらいシステムとなるおそれがあります。
そのため、現場の声を直接聞いたうえで、実務上の細かな要件も把握することが重要です。システムを利用するすべての部署の利用者にヒアリングを行ない、要件をくまなく洗い出すことに注力しましょう。
必須要件と希望要件の明確な区分け
Fit&Gap分析を通じて明らかにした要件は、同等に並べるのではなく、実装の緊急性や業務への影響度に基づいて優先順位を付けることが成功の鍵となります。特に、必須要件と希望要件を明確に分け、必要以上にカスタマイズしないようにする意識が重要です。
安易に必須要件を増やさず「本当に必要な要件か」「運用などで代替できないか」などといった観点から内容を精査しましょう。クラウドサービスを導入する場合にはカスタマイズの制約も多いため、必須要件を厳選することが大切です。
システム開発をベンダー任せにしない体制づくり
適切なシステム導入を実現するためには、自社の業務に精通した担当者が積極的にかかわり、ベンダーとの認識のズレを防ぐことが重要です。ベンダーは自社特有の業務内容や運用方法に詳しいわけではありません。例えば、Fit&Gap分析をベンダーに一任してしまうと、実際の業務ニーズとシステム機能の適合性について適切に評価できなくなるかもしれません。
自社も積極的にかかわる体制を構築し、現場の業務ユーザーも巻き込んで現行業務を把握し、業務に応じた機能の必要性について整理することが重要です。
クラウドサービス特有のFit&Gap分析の課題と対応
クラウドサービスはオンプレミスに比べてカスタマイズ性が低く、追加開発だけでギャップを埋めようと考えると対応が難しくなる場合があります。クラウドの特性である柔軟性を活用するためには、Fit to Standardの考え方を採り入れるなど、柔軟な対応も必要です。
また、クラウドサービスを導入する際には、既存システムとデータを連携するAPIの有無なども重要な検討事項となります。対応できない業務については、必要に応じて他のクラウドサービスを追加して対応する、などといった柔軟な発想が求められます。
「X Managed」ならICTのデザインからオペレーションまでお任せいただけます
Fit&Gap分析で的確にソリューションを選定できても、その後の運用についてはまた別問題です。NTTドコモビジネスでは、デザイン・デリバリー・オペレーションをワンストップで提供するトータルマネージドサービスを提供しています。
NTTドコモビジネスのMSPサービス「X Managed」は、運用業務のベストプラクティスを標準化した「セミオーダー型」のマネージドサービスです。
1,000件以上の導入実績、1,000名を超えるSE体制でお客さまのICT環境を最適化します。トータルマネージドサービスのため、運用効率を意識したデザインからオペレーションに至るまで、一気通貫で対応可能です。
お客さまが必要とするサービスレベルに応じて自由に選択し組み合わせることが可能なサービス/メニューを用意しており、お客さまの要望や時代の先端技術・トレンドに応じて多彩なコンポーネントをご利用いただけます。
NTTドコモビジネスのMSPサービス「X Managed」
まとめ
Fit&Gap分析は、パッケージシステムなどを導入する際に、自社の業務要件とシステム標準機能の適合度について評価する手法です。ソリューションを選定する際の重要な判断基準となるため、おろそかにするとソリューションの導入効果を最大限に活かすことができません。
近年ではクラウドサービスの業務利用も増え、Fit to Standardの考え方も重要視されるようになっています。この記事で解説した進め方や注意点なども参考にして、自社に最適なアプローチを選択しましょう。