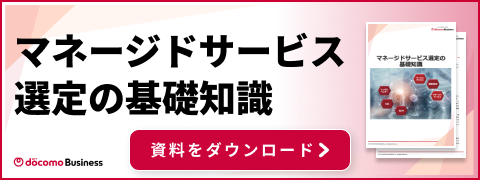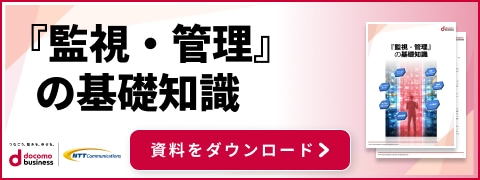SPOCのメリットと導入時の課題とは?
運用を支援するサービスも紹介
SPOC(サービスデスクの単一窓口化)の導入は、お問い合わせ対応の効率化だけではなく、業務全体の生産性向上に直結する重要な取り組みです。しかし、SPOCの必要性や導入時の注意点など、わからないことがあるという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、サービスデスクの種類やSPOCのメリット、導入時の課題などについて解説します。問題解決に役立つサービスも紹介しているため、SPOCの導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

目次
SPOCの意味とは?
SPOC(Single Point of Contact)とは、ユーザーのお問い合わせ先を1つの窓口にまとめることです。ここでいうユーザーとはお客さまのことだけでなく、自社内のシステムを利用する社員なども含まれます。
SPOCでは技術的なサポートやシステムの不具合などで社員やお客さまからのお問い合わせを広く受け付けており、サービスデスクとも呼ばれています。お問い合わせの内容により、担当の部署へつなげる役割を担っています。反対に、システム部門などからの情報を社員やお客さまに向けて発信することもSPOCの重要な役割の1つです。
このように、お問い合わせ先を一元化することによって社員やお客さまの利便性向上を図ることがSPOC導入の主な目的です。
SPOCの導入には、お問い合わせを通してナレッジを集約できるというメリットもあります。ナレッジを管理・分析して経営判断の材料にしたり、製品・サービスの品質向上を図ったりすることが可能です。
SPOCの導入によってお問い合わせの利便性の向上を図ることは、ITIL®においても推奨されています。ITIL(Information Technology Infrastructure Library)とは、ITサービスマネジメントのベストプラクティスを紹介するガイドブックのことです。
ITIL®はシステム運用現場において世界中で取り入れられており、ITサービスマネジメントの知識を問うITIL®認定資格も存在します。信頼性の高いITIL®に準拠してSPOCを導入することにより、ITサービスの運用をさらに高度化できるでしょう。
サービスデスクとヘルプデスクの違い
サービスデスクはヘルプデスクと混同されることが多い用語ですが、両者には明確な違いがあります。
サービスデスクは幅広い業務を担い、インシデントが生じてから解決するまでサポートします。社内で検知されたアラートに対応したり、新サービスについての情報を発信したりと、広範にわたる業務を担当する点が特徴です。
一方のヘルプデスクは、ITに関するトラブルシューティングの役割を担っています。「テクニカルヘルプデスク」などとも呼ばれ、社員やお客さまのお問い合わせを受けてトラブルの解決を目指します。サービスデスクと異なり、ヘルプデスクの側から情報を発信することは基本的にありません。
ヘルプデスクは対応できる範囲が限られており、専門外のお問い合わせがあった場合はほかの部署に回します。お問い合わせをしたユーザーはほかの部署から連絡を受けることになり、コミュニケーションが煩雑になりやすいことが難点です。
ヘルプデスクをアウトソーシングするメリットについては、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
サービスデスクの種類

サービスデスクは大きく4つの種類に分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社に合ったタイプを選択することが重要です。ここからは、4種類のサービスデスクについて解説します。
中央サービスデスク
中央サービスデスクは、お問い合わせへの対応拠点を1箇所にまとめるタイプです。ユーザーの拠点が複数あるのに対し、1箇所に集約されたサービスデスクでインシデントに対応します。
中央サービスデスクのメリットは、熟練のスタッフによりお問い合わせに対応できることや、コストを抑えられることです。コールセンターを1箇所に集中させることで、人件費などの運営コストを節約できます。
一方、デメリットとしては現地対応などに時間を要することです。ユーザーとの距離が離れていることから密接なコミュニケーションが難しく、情報伝達などに高い技術が求められます。また、通信状態によってはサポートが遅延するリスクもあります。
ローカルサービスデスク
ローカルサービスデスクは、ユーザーの拠点と同じ場所、もしくは近い場所にお問い合わせ対応の拠点を設置するタイプです。
ローカルサービスデスクのメリットは、密接なコミュニケーションによってユーザーをサポートできることです。スタッフがユーザーの近くに常駐するため、遠隔では難しい担当者の派遣なども簡単にできます。実地でユーザーの状態を確認することにより、業務上の問題点やニーズを正確に把握できるメリットもあります。
一方、デメリットとしては運営にコストがかかることです。複数の拠点にスタッフを常駐させる必要があり、ユーザーをサポートするためのリソースが求められます。
バーチャルサービスデスク
バーチャルサービスデスクは、通信技術やサポートツールなどを使って窓口を1つに集約しているように見せるタイプです。実際にはスタッフが別々の場所にいても、ユーザーからは中央サービスデスクのように1つの拠点で運営しているかのように見えます。
バーチャルサービスデスクのメリットは、柔軟な運営体制が実現することです。リモートワークやアウトソーシングに対応できるため、ニーズに応じて任意の組み合わせを選択できます。お客さまにとっても中央サービスデスクのように機能するため、スムーズに問題を解決できます。
一方、デメリットとしてはサービスの品質や一貫性を保つ工夫が求められることです。また、専用ツールを使用するためのコストや手間なども考慮に入れなくてはなりません。
フォロー・ザ・サン
フォロー・ザ・サンは、複数の拠点が連携して24時間体制のサポートを提供するタイプです。海外に拠点を設け、時差を利用することでユーザーのお問い合わせにいつでも即時対応できる環境を構築します。
フォロー・ザ・サンのメリットは、深夜などでもお問い合わせに対応できることや、単一シフトで拠点を運営できることです。
一方、デメリットとしてはツールの使い方や引き継ぎなどによる課題が生じやすいことです。拠点ごとに文化や生活スタイルが異なるため、業務のルールやプロセスを確実に浸透させる必要があります。
SPOC導入のメリット

SPOCを導入して窓口を単一化することにより、お問い合わせ先の明確化やナレッジの蓄積といったさまざまな利点が生まれます。ここでは、SPOCを導入することによって得られる主要なメリットについて解説します。
ユーザーのお問い合わせ先が明確になる
サービスデスクはインシデントの発生から解決までを一手に担う機能です。ユーザーは1つの窓口のみに問い合わせれば問題を解決できるため、たらいまわしを防ぐ効果が得られます。
例えば、システムに不具合が発生した際にユーザーがサポート窓口にお問い合わせをしたとしましょう。このとき、サポート窓口では問題に対応できないため、システム担当者へ案件の引き継ぎが必要です。
電話に出たシステム担当者にユーザーが状況を説明した結果、現在のプランでは問題を解決できないことが判明しました。システム担当者ではプラン変更に対応できないため、営業担当者に引き継ぐ旨をユーザーに伝えます。
続いて営業担当者がユーザーに連絡し、サポート窓口からプラン変更に関する書類を発送することを説明する、といった具合に対応のたらいまわしが生じやすい構造です。このようなケースでは問題解決までに時間がかかり、複数部署を経由することによりユーザーも不快感を覚えやすくなります。
一方、SPOCを導入すればサービスデスクが一手に問題を引き受け、担当部署と連携しながらユーザーへの回答を用意できます。上記の例では、サービスデスクがまずシステム担当者に調査を依頼し、営業担当者と連携してプラン変更の見積もりや書類などを準備、ユーザーに対して最終的な回答を提示するといった流れです。
SPOCを導入してユーザーのお問い合わせ先が明確になることにより、お客さまの満足度の向上や、各部署の手間を省くことにより生産性の向上にもつながるでしょう。
スムーズな問題解決につながる
SPOCの導入によって、お問い合わせ内容やシステムトラブル・復旧などの情報がサービスデスクに集約されることになります。その結果、サービスデスクにナレッジが蓄積され、類似のお問い合わせであれば担当部署へ確認せずに解決できるようになります。
SPOCを導入していない場合、ユーザーの抱えているトラブルにはそれぞれの担当部署による対応が不可欠です。ほかの部署にはトラブル解決の情報が共有されず、ユーザーをたらいまわしにするリスクは残り続けます。
SPOCを導入すれば、ナレッジの蓄積によってサービスデスクのみで完結するお問い合わせの幅が広がり、スムーズな問題解決につながるでしょう。
本来の業務に集中できる
SPOCの導入によって、各部門の担当者が本来の業務に集中できるようになることもメリットの1つです。
インシデントが発生した際、お問い合わせを受けたシステム担当者は調査や原因の究明、システムの復旧対応、記録などを行います。これは本来の業務ですが、SPOCを導入していない場合、ユーザーへの対応まで行うことがあります。不慣れな人にとって、ユーザー対応は負担が大きい業務であり、ほかの業務にも支障をきたす恐れがあります。
SPOCの導入によって、各部門の担当者はユーザー対応に煩わされることなく、原因究明やトラブル解決などの本来の業務に集中できるようになります。
蓄積されたデータを活用できる
SPOCを導入してサービスデスクに情報を集約することによって、効率的にデータを蓄積できるようになります。そして、サービスデスクに蓄積されたデータはお客さま対応やマーケティングに活用することが可能です。
例えば、過去の対応状況をデータベース化して分析することにより、お客さまへの対応を改善できるでしょう。また、お客さまの意見を参考にしてマーケティング戦略を立案する際などにも蓄積されたデータが役に立ちます。
SPOCの導入によるデータ活用の強化は、企業の効率的な成長にもつながるはずです。
SPOCを導入する際の注意点
SPOCのメリットを最大限に活かすためには、運用における注意点についても把握しておくことが大切です。ここからは、SPOCの導入にあたって注意が必要な2つのポイントについて紹介します。
ナレッジの蓄積に時間がかかる
SPOC化したサービスデスクではユーザーからのすべてのお問い合わせを集約できますが、集約されたデータをすぐに活用できるわけではありません。ナレッジが蓄積され、スムーズな問題解決につなげるためには一定の時間が必要です。SPOCを導入してすぐに一次解決率などが向上するわけではないことに注意しましょう。
また、SPOC化したサービスデスクの運用を始めたら、データを蓄積していく方法についても考えておく必要があります。ナレッジの品質を安定させて有効活用するためにも、ルールを定めて有益な情報を蓄積させていくことが大切です。
ナレッジの整備が求められる
SPOCを運用する期間が長くなるほど、取り扱うデータも膨大な量になります。ナレッジの整備を怠ると、共有場所がわからなくなったり、情報が古くなったりするので注意が必要です。
ナレッジの品質が低いと、サービスデスクの担当者も働きにくくなります。ユーザーに間違った情報を案内してしまって企業の信頼度が低下したり、担当者のモチベーションが下がったりすることにもなりかねません。
SPOC化したサービスデスクを導入したあとはナレッジを継続的に整備し、使いやすい状態にしておくことが重要です。
SPOC運用の課題を解決する方法

SPOCを導入したあとは、主にナレッジに関する課題にアプローチする必要があります。ここでは、SPOC運用の課題を解決する方法について2つ紹介します。
ナレッジマネジメントの実施
ナレッジマネジメントとは、個々の社員が持つスキルを共有し、組織全体の生産性を高めるマネジメント手法のことです。社員一人ひとりが所有しているスキルを全社員が業務に活用できるようにすることで、新たな変革を促します。
ナレッジマネジメントにおいて重要なことは、社員が所有する暗黙知を形式知に変換することです。各社員が蓄積してきたスキルを文章などの理解しやすい形に置き換えれば、社内で共有することが可能になります。
ナレッジマネジメントは専用のシステムを導入して実施することが効率的です。試しにナレッジマネジメントを始めてみたい場合には、Excelを活用して地道にナレッジを言語化・蓄積する方法もあるでしょう。
ナレッジマネジメントによりナレッジの整備や共有を行えば、サービスデスクにおけるオペレーターの負担を効果的に軽減できます。
ツールの活用
ツールを活用することによりSPOCを導入しやすくなる場合もあります。SPOC化したサービスデスクの運用によって生産性やユーザーの満足度を向上させたい場合には、SPOC化を支援するツールの利用も検討しましょう。
例えば、インシデント管理ツールは窓口で取り扱うインシデントを記録しカテゴライズしてくれるツールです。インシデントの集計・分析や対応状況の一覧表示など、ツールに備わっている機能は多岐にわたります。インシデントの管理が容易になるため、オペレーターの負担軽減につながるでしょう。
お問い合わせのチャネルを増やすマルチチャネルツールを活用することもおすすめの方法です。お問い合わせへの対応を自動化するチャットボットなどを使えば、オペレーターの負担を抑えると同時にナレッジの蓄積にも役立ちます。
サービスデスクの目的や規模に応じて適切なツールを選ぶとよいでしょう。
SPOC運用を強力に支援するNTTドコモビジネスのサービス
NTTドコモビジネスでは、SPOCされたサービスデスクの運用を強力に支援するマネージドサービスやIT運用管理サービスを提供しています。ここでは、サービスデスク運用を支援するNTTドコモビジネスの2つのサービスを紹介します。
X Managed
「X Managed」はITシステム運用保守業務の負担を軽減させるトータルマネージドサービスです。その魅力は、デザイン・デリバリー・オペレーションのベストプラクティスをワンストップで提供していることです。
ITインフラ構築保守運用の知見を集約・標準化しており、効率的な運用の高度化やコスト最適化が図れます。システム運用の負担を減らし、コア業務に集中したい企業には最適なサービスなので、ぜひ導入をご検討ください。
多店舗ネットワークマネジメント
「多店舗ネットワークマネジメント」は、全国に100以上の店舗や拠点を持つ企業のネットワーク監視や管理・故障対応などを行うサービスです。お客さまにとっての一元窓口体制を実現しており、多拠点の煩雑・複雑な運用業務をスムーズにアウトソーシングできます。
多店舗ネットワークマネジメントを導入すれば、お客さまのICT環境に精通したサービスマネージャーが品質改善やトラブル対応を行って、環境の最適化・高度化を図ります。
情報システム部門のネットワーク運用負荷をもっと軽減したい企業や、店舗におけるトラブルを低減したい企業におすすめのサービスです。
まとめ
SPOCの導入によりユーザーのお問い合わせ先を1つに集約すると、問題解決の迅速化や業務効率の向上といったメリットが得られます。SPOC化されたサービスデスクに蓄積されたデータは、マーケティング戦略の立案などにも役立つでしょう。
ただし、SPOC化されたサービスデスクで扱う膨大なデータは、継続的に整備して使いやすい状態に保つことが大切です。ナレッジマネジメントやツールを活用しながら、SPOCの導入効果の最大化を図るとよいでしょう。
店舗DXについては以下記事で詳しく解説しているのでご参照ください。