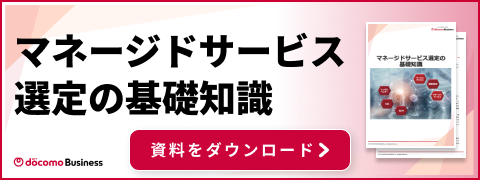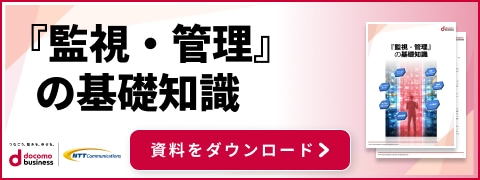小売DXが重要な理由とは?
推進する際のポイントや企業事例7選を紹介!
デジタル技術の進歩や普及にともない、小売DXの重要性が高まっています。しかし、小売DXの概要や必要な理由、導入の進め方などについてわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、小売DXが重要な理由や推進のメリット、DX推進の際のポイントなどについて解説します。小売DXに成功した企業の事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

目次
小売DXとは?
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、データやデジタル技術を活用することによりビジネスモデルを変革させることです。現代社会では、AI(人工知能)やRPAといった技術の導入によって新たな価値を生み出し、競争力を高めていく必要があります。
それを踏まえると、小売DX(小売デジタルトランスフォーメーション)とはデータやデジタル技術を活用して、小売業のビジネスモデルや業務プロセス、顧客の体験を根本的に変革することを意味します。
小売業界においては、主に顧客中心のアプローチで新たな顧客体験やビジネスモデルを創出することが肝要です。
また小売業界では、慢性的な人手不足や物価上昇、顧客の購買行動における変化などが経営に大きな影響をおよぼしています。従来のやり方のまま変わらずにいては、厳しい生存競争に敗れて事業を続けられなくなることもあるでしょう。
小売業界では倒産する企業も増加しているなかで、DX推進による業務効率化や健全な経営を図る必要があります。
小売業界においてDX推進が必要な理由

消費行動の変化や人材不足といった問題を背景に、小売業界ではDX推進の必要性が叫ばれています。ここからは、小売業界においてDX推進が必要な理由について紹介します。
老朽化していることが多いため
システムやデータベースの更新には大きな労力が必要なため、その実行に二の足を踏んでいる企業も多いようです。しかし、老朽化したシステムを使い続けることによって、余計なコストや業務の負担が大きくなる例も珍しくありません。
また、蓄積できる有益なデータの量が少なく、データ解析による戦略の立案などが難しいケースもあります。従来のシステムやデータベースが現在の業務に適していない場合には、最新システムの導入が必要です。
既存のシステムが老朽化していると、技術的な問題により新システムへの移行がうまくいかない場合もあります。しかし、DX推進で競争力を高めるためには欠かせないプロセスでもあります。経営陣が主導する形で、時間とコストを惜しまずに最優先で取り組む戦略が求められるでしょう。
消費行動が変化しているため
従来は店舗への来店や電話注文によって商品を購入していた消費者が、今ではECサイトを頻繁に使うようになりました。スマートフォンなどのデバイスやインターネットが普及し、誰でも好きなときにショッピングを楽しめるようになったためです。
このような消費行動の変化に対応する意味でも、小売DXは重要な施策の一つです。ECサイトの運営はもちろん、顧客が商品を購入した際などに蓄積されるデータを適切に活用することも求められます。
ECサイトの運営で蓄積されるデータは、顧客の購入履歴や流入経路、滞在時間など多岐にわたります。小売業界でもDX推進を行い、データを管理・分析するための体制を整えることが重要です。
経営判断のためのデータを効率的に収集できるため
現代のデジタル社会においては、客観的なデータによって経営判断を行う「データドリブン経営」が主流となりつつあります。
データドリブン経営のメリットは、経営判断の根拠を明確にできることです。経営者の勘や経験に頼らず、データをもとに方針を決めることによって、株主などのステークホルダーに対しても納得させやすくなります。
データドリブン経営を行うためには、十分な量のデータを蓄積させる必要があります。しかし、DXが進んでいないと経営判断に必要なデータを効率的に集められません。DX推進により顧客の情報や売上などのデータを分析・活用できれば、新商品や新サービスの開発にも役立つでしょう。
慢性的な人材不足を解消できる
少子高齢化による労働人口の減少が社会問題となっています。小売業界においても人材不足は慢性化しており、サービスの品質維持が難しくなっている状況です。
店舗運営において慢性的な人材不足に悩んでいる場合には、DX推進が役に立ちます。デジタル技術やシステムの導入によって業務効率化を図ることが、問題解決への有効なアプローチとなるでしょう。
セルフレジの導入やAI(人工知能)による需要予測などによって業務効率を高め、限られた人的リソースを有効活用することが大切です。
DXを推進するために、まずはIT人材を確保する必要があります。IT人材は今後も不足し続けることが予想されているため、早い段階から人材確保に向けて動き出さなくてはなりません。
小売DXを推進するメリット

小売業界でDXを推進すると、顧客満足度や生産性の向上、データドリブン経営の実現といったメリットが得られます。ここからは、小売業界でDXを推進する5つのメリットについて紹介します。
顧客視点でのマーケティングが可能になる
DXを推進すると、ECサイトなどで商品を購入した顧客の年齢や居住地といったデータを収集できるようになります。これらのデータを活用することによって、顧客⼀⼈ひとりの行動パターンや好みの分析などが可能になるでしょう。
その結果、おすすめ商品や関連商品をECサイト内で表示するなど、顧客の視点に立ったマーケティングを行えるようになります。さらにMAツールを利用するとキャンペーン情報の配信なども行えるようになり、効果的に施策を展開できます。
顧客の満足度が向上する
DXによるデータ分析によって顧客への理解が深まり、マーケティングやサービスの精度が高まれば、顧客の満足度向上にもつながります。
例えば、実店舗の在庫をインターネットで確認できるシステムを導入することにより、顧客にとっての利便性が高まるでしょう。また、ECサイトと実店舗でデータを共有することによって、顧客がECサイトで閲覧していた商品を実店舗でおすすめすることも可能です。
プロモーションの精度が改善されれば、関心の薄い顧客に商品をおすすめして反感を買うリスクも抑えられます。DXを推進して顧客の満足度を向上させることにより、リピート客の増加や売上の向上も期待できるでしょう。
データドリブン経営が実現する
DX推進によってあらゆるデータを活用できるようになれば、データをもとに経営判断を行うデータドリブン経営が実現します。データ分析によって売上の傾向や顧客のニーズを把握することによって、より的確な戦略を立てられるでしょう。
小売業界では収集したデータをマーケティングや人材育成、サプライチェーンの構築など、多岐にわたる分野で活用できます。データに基づいた予測によって、あらゆる分野で精度の高い意思決定を行える点がデータドリブン経営の強みです。
生産性向上・コスト削減につながる
AI(人工知能)技術やデータなどを活用して需要予測を行えば、無駄のない生産管理や在庫管理が実現します。小売業界ではモノをメインに扱うため、生産量や在庫を適切に管理できるかどうかが重要なポイントです。
また、DXを推進して生産性を向上させることにより、小売業界の人材不足にも対応できます。人が行う作業を減らせば新たな人材を確保する必要がなくなるため、人件費などのコスト削減にもつながるでしょう。
運営の省人化が図れる
商品の仕入れや在庫管理などを手作業で行うと膨大な手間がかかることは、小売業界が抱える課題の一つです。しかし、DX推進により業務効率化を実現させれば、省人化運営が可能となります。
店舗業務や商品準備といった作業の負担が減り、従業員の満足度も高まるでしょう。また、店舗運営の省人化によって人的ミスを効果的に防げることもメリットの一つです。
小売DXを推進するときのポイント
小売DXを推進するときは、DX人材を育成しつつ、必要なコストを考慮して施策を展開することが求められます。ここからは、小売業界でDXを推進する際の3つのポイントを紹介します。
経営戦略に則って施策を展開する
小売DXを推進する際は、経営層が主体的に関わり、経営戦略に則って施策を展開することが重要です。
まずは経営の理念やビジョンに基づいた戦略を立て、現状分析を通して課題を抽出しましょう。課題を可視化することにより、デジタル技術を活用するべき領域も見えてきます。
次に、「業務の効率化」といった目標を立て、予算の確保や導入システムの選定のために計画を策定します。しっかりと準備を整えたうえで、段階的にDX施策に取り組むことが成功のポイントです。
小売DXの推進は、小さな規模でスタートすることによりリスクを抑えられます。また、DX施策の運用を始めたあとはその効果を測定し、最新の技術動向を意識しながら運用を改善し続けることが大切です。
DX人材を育成する
DX推進にあたっては、DX人材の確保および育成も重要なポイントとなります。
DX人材を育成する方法としては、OJTプログラムでの研修や資格取得の支援などが挙げられます。そのほか、DXを実践しているコミュニティに参加したり、外部の専門家が主催している勉強会に参加したりすることもよいでしょう。
DX人材の育成で効果を上げるためには、研修の対象者にデジタル技術導入のメリットを訴えることが重要です。DX推進によって得られる具体的な成果を明示し、従業員が主体的に研修に取り組める雰囲気を醸成しましょう。
また、従業員がデジタル技術の進歩に合わせて継続的にスキルアップできる環境づくりも欠かせません。
必要なコストや時間を考慮する
DXの本格的な推進には多くのコストや時間を費やすことになります。設備投資や人材育成、働き方改革など、DXの推進に際して行うことは多岐にわたります。短期的に売上が悪化する可能性なども考慮しながら、慎重にDXを推進する姿勢が肝心です。
DXの考え方が組織全体に浸透するまでには長い時間がかかるでしょう。DX化によってすぐに効果を得ようとするのではなく、長期的な構えで着実に取り組みを進めていく必要があります。
小売DXの企業事例7選

小売DXを推進する際は、ほかの企業の成功事例が参考になります。ここからは、小売DXに成功した企業の事例を7つ紹介します。
イオンモール
イオンモールでは「イオンモールアプリ」を導入して、クーポンの配信機能やWAONポイントとの連携機能などを実装しました。セールなどの最新情報もアプリで通知しており、顧客は店舗内や駐車場の混雑度などもアプリで把握可能です。
これは実店舗とオンラインを融合させ、顧客の利便性を向上させた事例だといえるでしょう。DXによって経営効率の改善も実現しており、2022年には「DX認定事業者」にも指定されています。
DX認定事業者とは、経済産業省の定める「デジタルガバナンス・コード」に対応してDXを推進している事業者のことです。
三越伊勢丹
三越伊勢丹では、ショッピングアプリを利用したオンライン接客サービスを提供しています。店舗のみに在庫がある商品でもオンライン経由で購入できるほか、顧客はビデオチャットを通じて商品の説明などを聞くことができます。
さらに、三越伊勢丹ではカジュアルギフトの市場拡大を受けてECサイト「MOO:D MARK(ムードマーク)」を展開しました。そのほかにもDX推進によって新たなマーケティング施策を展開しており、顧客の購買意欲向上を実現しています。
ローソン
ローソンにおけるDX推進の代表例として、完全キャッシュレス・タッチレスの次世代型コンビニ「Lawson Go(ローソンゴー)」をスタートさせたことが挙げられます。ローソンゴーでは、入店時に専用アプリのQRコードを読み込ませれば、商品を持ったまま店舗の外に出ると自動的に決済が行われます。
AI(人工知能)を活用した需要予測システムを取り入れて、在庫管理を最適化していることも特徴の一つです。廃棄ロスを削減しつつ、従業員の業務負担も軽減する取り組みだといえます。
カインズ
カインズではデータ分析によるマーケティング最適化戦略の立案や、顧客体験の向上に取り組んでいます。顧客の購買行動を分析したうえで、一人ひとりのニーズに合わせたレコメンドや特典の配布を実施していることがその取り組みの一つです。
また、「カインズアプリ」では商品の在庫確認ができる機能や、駐車場に停めた車まで商品を届けるサービスなどを展開しています。DX推進により顧客が楽しく買い物できるように工夫を凝らし、効果的にファンを増やしている事例です。
Walmart(ウォルマート)
ウォルマートでは、オンライン注文した商品を店舗で受け取れるサービスを展開しています。
オンラインで商品を注文するとメールが届き、そこにあるバーコードを店頭で読み取らせれば商品を受け取れる仕組みです。顧客と従業員双方の手間を省きつつ、実店舗での購買機会提供にも貢献する施策だといえます。
ウォルマートではアプリの開発にも注力しており、ナビゲーションなどの機能を実装することで、顧客はより快適に店舗内でのショッピングを楽しめるようになりました。
IKEA(イケア)
イケアではオンラインストアと実店舗のどちらからも商品を買えるオムニチャネル戦略を展開しています。店舗で見つけた商品をオンラインで購入したり、オンラインで注文した商品を店舗で受け取ったりできる仕組みを整え、顧客の利便性向上を図っています。
「IKEA Place」というARアプリを開発したことも特徴の一つです。このアプリでは、仮想的にIKEAの家具を自宅に設置し、購入前にイメージを確認できる機能を提供しています。
Amazon Go(アマゾンゴー)
「Amazon Go」はAmazonが提供するレジのないコンビニです。専用アプリのQRコードをゲートでかざして入店し、顧客が手に取った商品は自動的にスマートフォンに表示されます。レジ待ちのストレスを省くことにより顧客体験を向上させている事例です。
アマゾンではほかにも「Amazon Fresh」というネットスーパーを展開しています。野菜や果物などの食品をオンラインで買うと、最短で当日に配達してくれるサービスです。
小売DXにおける具体的な施策
小売DXを推進するうえでカギとなるのが、OMOの実施とシステムの導入です。ここからは、小売DXにおける具体的な施策を紹介します。
OMOの実施
OMO(Online Merges with Offline)は、オンラインとオフラインを一体化させて顧客体験の向上を図るマーケティング手法を指します。
OMO戦略を展開することにより、オンラインであるECサイトで商品を検索した顧客に、オフラインである実店舗の在庫情報を紹介するなどといったアプローチが可能になります。デジタル技術を駆使して顧客満足度を高められるOMOは、小売DXにおいて重要な施策の一つだといえます。
OMO手法の具体例として、オンライン接客やSNS集客、多様な決済手法への対応などが挙げられるでしょう。
オンライン接客では、チャットボットやビデオチャットなどの技術が活用できます。SNSは無料でアカウントが作れるうえ、すぐに店舗のPRができるため、積極的に活用したいツールです。
多様化している決済手段にも対応すると同時に、実店舗とECサイトを連動させて収集したデータを有効活用するとよいでしょう。
ただし、OMOを実施する際に気を付けたい点が、店舗スタッフのモチベーション維持です。店頭でレコメンドした商品がECサイトで買われた場合、店頭のスタッフが正当に評価されないとモチベーションの低下につながります。OMOの導入と合わせて、人事評価制度を整理することも重要なポイントです。
システムの導入
店舗運営で解決したい課題がある場合には、適切なシステムの導入が効果的です。
例えば、顧客の情報を一元管理したい場合にはCRM(顧客管理システム)、顧客の行動に関するデータを管理したい場合にはMA(マーケティングオートメーション)などのシステムが役に立ちます。販売データの一元化や請求書作成業務の効率化を図りたい場合には、販売管理システムを導入するとよいでしょう。
そのほか、レジの混雑を緩和したい場合にはキャッシュレス決済の導入がおすすめです。従業員の勤務スケジュールに問題がある場合には勤怠管理システムの活用を検討してください。
これらのようなリテールテックを導入することにより、データの収集・分析を通して適切な経営戦略を立てられるようになるでしょう。
小売業界でのネットワーク運用の課題を解決する「多店舗ネットワークマネジメント」
小売業界でDXを推進する場合、業務の根幹を担うネットワークの適切な監視・運用が欠かせません。そこでおすすめしたいソリューションが、NTTドコモビジネスの「多店舗ネットワークマネジメント」です。
多店舗ネットワークマネジメントは、100店舗以上の多店舗を運営するお客さま向けのマネージド・サービスです。24時間365日体制で、お客さまの代わりに多店舗ネットワークの監視・管理・故障対応などを実施します。
NTTドコモビジネスの「X Managed」をベースにしており、関連ベンダーの統制やオンサイト保守手配などもワンストップで対応可能です。高度なシステム運用スキルを持ったサービスマネージャーが運営を担当し、お客さまのビジネスをバックアップしています。
店舗にIT人材がいない、監視保守体制の維持にコストがかかりすぎるなど、多店舗経営で課題を抱えている場合には多店舗ネットワークマネジメントの利用をご検討ください。
まとめ
デジタル技術の進歩によって顧客の購買行動が変化しており、小売業界でもDX推進による対応が求められています。小売DXの推進によってデータドリブン経営を実現させれば、意思決定の精度が高まり事業も発展しやすくなるでしょう。
小売DXを推進する際にはDX人材を確保し、OMOの実施やシステムの導入といった施策を展開することが重要です。ほかの企業の成功事例を参考にしながら、長期的な視点でDX推進に取り組むとよいでしょう。
店舗DXについては、以下記事でも詳しく解説しているのでご参照ください。
店舗DXとは?今こそ始めるべき理由~基本から実践までまとめて解説
NTTドコモビジネス「多店舗ネットワークマネジメント」の詳細はこちら