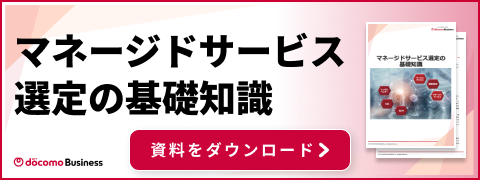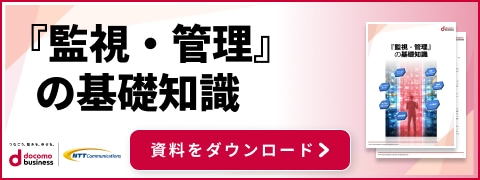リテールテックとは?
小売企業にとってのメリット・技術事例を紹介
少子高齢化や人手不足、消費者ニーズの多様化など、小売業を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。こうした課題に対応する手段として注目を集めているのが「リテールテック」です。リテールテックとは、小売業にテクノロジーを活用し、業務効率化や顧客体験の向上、売上拡大などを実現する取り組みを指します。
当記事では、リテールテックの基本的な定義から、注目される背景、導入による企業・消費者双方へのメリット、代表的な技術とその活用事例などを解説します。導入を検討している企業担当者の方はぜひご一読ください。

目次
1. リテールテックとは

リテールテック(Retailtech)とは、小売業(Retail)にIT技術(Technology)を導入し、業務の効率化や顧客体験の向上、さらには売上の最大化を目指す技術革新を指します。リテール(小売業)とテクノロジー(技術)を組み合わせた造語で、近年急速に注目されています。AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、クラウドコンピューティングなどの技術を活用したシステムは、流通や在庫管理、商品陳列、顧客サービスの向上に貢献しています。
具体的なリテールテックの例として、キャッシュレス決済やセルフレジが挙げられます。これらは消費者の利便性を高め、店舗側のレジ業務を効率化します。また、AIによる顧客への商品提案や、ECサイトと実店舗の連携などもリテールテックに含まれ、消費者はよりパーソナライズされた買い物体験を享受できます。リテールテックは小売業の運営における課題解決を助け、消費者に新たな購買体験を提供する重要な役割を果たしています。
2. リテールテックに注目が集まる背景
リテールテックへの注目が高まる背景には、慢性的な人手不足や店舗運営の効率化ニーズ、顧客ニーズの多様化などさまざまな要因が考えられます。以下では、それぞれの要因について詳しく解説します。
2-1. 慢性的な人手不足
小売業界では、少子高齢化により深刻な人手不足が続いています。この問題は、業務が多岐にわたる小売業において特に顕著であり、限られた人数での対応が求められるため、一人当たりの業務負荷が増大しています。加えて、離職率が高く、人材の確保や育成が容易でないことから、採用活動や教育にかかるコストも増加傾向です。
これらの状況において、リテール業界は人手不足を解消するために業務の効率化や省力化を急務としており、その解決策として注目されているのがリテールテックによる技術導入です。セルフレジや無人店舗、AIを活用した在庫管理など、テクノロジーを駆使した省人化の取り組みは、限られたリソースでの業務を円滑に進め、効率的な運営を可能にしています。
2-2. 店舗運営の効率化ニーズ
新型コロナウイルスの影響を受け、消費が落ち込み大きな打撃を受けた小売企業は多く、さらに物価高の影響も加わり、経営が厳しくなっています。こうした状況で求められるのは、店舗運営にかかるコストの削減です。
人件費や管理コストの増加に対応するため、業務効率化は急務となっています。リテールテックの導入は省人化や無人化を進める手段として注目されており、AIやロボット技術を活用した業務効率化は、直接的に人件費の削減や電気代の削減など、店舗運営コストの低減につながります。業務効率化により、経営の安定化が図れるとともに、競争力も高まります。
2-3. 顧客ニーズの多様化と体験価値の重視
消費者行動はIT技術の進歩により多様化しており、たとえばキャッシュレス決済の普及がその一例です。今やキャッシュレス決済に対応していない店舗は避けられることもあり、消費者のニーズに応えることが競争力の源となっています。そこで多くの小売業がリテールテックを導入し、キャッシュレス決済やセルフレジ、オンライン接客などを積極的に取り入れています。リテールテックの導入は、販売機会を逃さず、顧客満足を高めるための重要な手段として位置付けられています。
また、オンラインショッピングの普及により、単に商品を陳列するだけでは売上が伸びにくくなっています。顧客に快適でパーソナライズされた購買体験を提供することが、今後の成功に欠かせない要素となっています。
2-4. データ活用による戦略的経営
小売業界では、POSデータや購買履歴などの顧客データを活用した需要予測やマーケティングが進んでいます。顧客データを活かすことで、販売戦略をより精緻化し、効率的な在庫管理やプロモーション活動が可能です。しかし、誰がいつ、どの商品を購入したかといったデータは十分に活用されていない場合が多く、購買データや来店履歴の分析が不足しています。
この結果、消費者一人ひとりに合わせた商品提案やプロモーションの機会が失われ、競争力が低下するおそれがあります。データを有効に活用することで、消費者のニーズに合った戦略的なアプローチが可能となり、売上向上につながるでしょう。
2-5. テクノロジー進化と外部環境の変化
リテールテックが注目される要因には、AIやIoTなどの技術革新もあります。スマートフォンの普及により消費者のITリテラシーも向上し、小売業においても先進的なテクノロジーの導入が求められる時代になりました。海外ではAR(拡張現実)やVR(仮想現実)を活用した販売手法も進んでおり、日本でもこうした新技術の導入が加速しています。
加えて、新型コロナウイルスの流行は小売業のあり方に大きな変化をもたらしました。非接触が求められるようになり、キャッシュレス決済やセルフレジなど人との接触を減らす手段が広く受け入れられるようになり、リテールテックへの関心が一気に高まりました。技術の進化と社会的要請の両面から、リテールテックの導入はますます必要となっています。
3. リテールテックを導入するメリット

リテールテックの導入は、企業にとって業務の効率化やコスト削減、売上や在庫管理の最適化につながります。また、データを活用した判断がしやすくなる点も大きな利点です。消費者にとっても、快適な購買体験や柔軟な決済手段の選択といったメリットがあります。
以下で、企業と消費者それぞれの視点からメリットを詳しく紹介します。
3-1. 【企業】業務を効率化しコストを削減できる
リテールテックの導入により、小売業務の自動化や省人化が進み、人手不足を補いながら効率的な運営が可能になります。従業員一人ひとりの業務負担が軽減され、少人数でも日々の業務を回せるようになるため、人件費を含む運営コストの削減につながります。たとえば、在庫管理や売上分析、顧客管理のシステム化によって、手作業の負担を減らし、ミスの防止にも効果を発揮します。
また、掃除ロボットの導入や無人店舗の運営なども現実的な選択肢となり、店舗のスリム化が進むことで、さらに業務効率が向上します。限られた人材で最大限の成果を出せる環境づくりを支えるのが、リテールテックの魅力の1つです。
3-2. 【企業】データにもとづいた意思決定が可能になる
顧客の購買履歴や売上、在庫などのデータを継続的に収集・蓄積・分析できることも、リテールテックを導入するメリットの1つです。リアルな消費行動にもとづくファーストパーティデータは、従来のマーケティングに使われてきたサードパーティデータよりも精度が高く、消費者ニーズの解像度を飛躍的に高めることが可能です。
また、POSレジなどを通じて収集したデータを活用すれば、売れ筋商品の分析や販売タイミングの最適化、プロモーション施策の精緻化が図れます。ツールによっては売上情報をリアルタイムで把握でき、曜日・時間帯・店舗ごとに傾向を分析することも可能です。
3-3. 【企業】売上の拡大を期待できる
リテールテックの導入は、業務の効率化や顧客体験の向上を通じて、売上拡大にも貢献する施策です。たとえば、Eコマースの活用やオンライン接客により、実店舗に依存しない販売チャネルを確保でき、販売機会が広がります。RFID(無線ICタグ)の導入により、商品管理や精算の効率が高まり、在庫精度も向上します。
また、データにもとづいたマーケティングの強化によって、消費者ニーズに合った商品提案やプロモーション展開が可能になるでしょう。新規顧客の獲得やリピーター育成が期待され、売上の向上につながる点も大きな利点です。業務の効率化によって従業員が接客や企画といったコア業務に集中しやすい環境が整います。
3-4. 【企業】在庫管理を最適化できる
リテールテックの導入は、在庫管理の正確性と効率性を大きく向上させる手段となります。従来の紙ベースや手作業による在庫管理は、ヒューマンエラーが生じやすく、棚卸や確認作業にも多くの時間と労力がかかっていました。しかし、RFIDやバーコード技術を活用したデジタル管理を導入すれば、目視に頼らず正確な在庫把握が可能になり、作業の効率化が図れます。
また、ピッキング作業へのロボット導入などにより、倉庫内業務の自動化も進めやすくなります。自動化が進むとスタッフの負担が軽減され、少人数でも安定した在庫管理体制を構築できる環境が整います。在庫の過不足を防ぐことで欠品や余剰在庫といったリスクも抑えられ、無駄なコスト削減にもつながる点もメリットです。
3-5. 【消費者】購買体験が向上する
買い物に対する利便性や快適さは、消費者満足度を大きく左右する要素です。リテールテックの活用により、ECサイトやアプリから自宅で商品を検索・購入できる環境が整い、店舗を回る手間が減りました。購入履歴や検索履歴にもとづく商品提案で、「欲しかったもの」に出会える可能性も高まります。
バーチャル試着や仮想シミュレーションといった体験型サービスも広がり、購入後のイメージがしやすくなっています。セルフレジやキャッシュレス決済など、スムーズな会計手段も満足度を高める要素です。リテールテックは、こうした多様な仕組みで快適な購買体験を支えています。
3-6. 【消費者】決済手段を柔軟に選択できる
現金やクレジットカードに加え、QRコード決済や電子マネー、ポイント払いなど、多様な支払い方法に対応する店舗が増えています。スマートフォンをかざすだけで決済が完了するため、現金の受け渡しやカードの挿入といった手間が省け、よりスムーズな会計が実現します。
また、キャッシュレス決済にはポイント還元などの特典があることも多く、買い物を楽しみながらお得感を得られる点も魅力です。支払い方法を自由に選べることで、消費者の利便性と満足度が一層高まっています。
4. リテールテックの技術・活用事例
リテールテックは、さまざまな技術を組み合わせることで実店舗やECサイトの運営を支えています。以下では、リテールテックの代表的な技術の概要と、実際の活用事例を紹介します。
4-1. RFID
RFID(Radio Frequency Identification)は、ICタグに記録された情報を電波で読み取り、非接触で商品を識別・管理できる技術です。複数の商品を同時に読み取れるため、在庫管理や会計業務の効率化に優れた効果を発揮します。
たとえば、大手アパレル企業ではセルフレジにRFIDを導入し、買い物カゴを専用スペースに置くだけですべての商品を一括で読み取り、合計金額を瞬時に表示できる仕組みを構築しました。導入により、会計時間は最大で従来の3分の1に短縮され、レジ待ちの解消と顧客満足度の向上に寄与しています。棚卸や検品、万引き防止にも活用されており、店舗全体の運営効率化に役立っています。
4-2. 無人店舗
無人店舗とは、従業員が常駐せずに運営される店舗形態で、AIやセンサー、カメラなどの技術を組み合わせることで、来店から決済までのプロセスを自動化しています。商品を手に取った情報をシステムが認識し、購入データとして記録します。店を出るときに、登録済みアカウントに自動で決済が行われる仕組みが一般的です。
代表的な事例として、2016年に大手EC企業が開設した無人店舗が挙げられます。画像認識や音声認識を活用し、レジをなくすという大胆な発想で大きな注目を集めました。省人化による人件費削減だけでなく、レジ待ちの解消や24時間営業への対応といった顧客利便性の向上にもつながっています。実店舗のあり方を大きく変える新しい小売モデルとして、導入が広がっています。
4-3. RPA
RPA(Robotic Process Automation)とは、AIや機械学習などの技術を活用し、これまで人間が行ってきた業務をソフトウェアロボットで自動化する仕組みです。定型的な処理を高速かつ正確にこなせるため、業務効率の向上やヒューマンエラーの削減につながります。
たとえば、Eコマースの拡大で物流業務が増えた企業では、RPAを導入して商品管理や入荷処理、ピッキング、検品などを自動化しました。作業スタッフの負担軽減に加え、人的ミスの削減や生産性の向上といった効果が得られました。人手不足の解消にもつながる技術として、注目が高まっています。
4-4. Eコマース
Eコマース(EC)とは、インターネットを通じて商品やサービスを売買する仕組みです。スマートフォンやPCから24時間いつでも購入できる利便性から、近年は実店舗を持たない小規模事業者にも広く利用されています。顧客との接点を拡大し、商圏を全国・世界へと広げられる点が大きな魅力です。
ある企業では、ECサイトと基幹システムを連携し、受注から売上処理までの業務を自動化しました。個別の販促対応も正確に反映されるようになり、オペレーターの業務負担を軽減しつつ対応の質も維持できています。Eコマースの導入により、販売機会の拡大と業務の効率化を同時に実現することが可能となりました。
4-5. POS
POS(Point of Sales)とは、商品の販売時点でバーコードなどを読み取り、売上や在庫、顧客情報をリアルタイムで収集・管理できるシステムです。いつ・どの商品が・どれだけ売れたかといった情報を記録することで、在庫管理の最適化や販促活動の精度向上に役立ちます。
ある企業では、POSレジと販売管理システムをクラウドと連携させることで、売上データの即時取り込みを可能にしました。従来は20時間ほどかかっていた処理がボタン1つで完結できるようになり、作業時間の大幅削減とコストの見直しに成功しました。POSの導入により、業務の効率化だけでなく、マーケティング施策の強化や意思決定の迅速化にもつながっています。
5. リテールテックの導入を成功させるためのポイント4つ
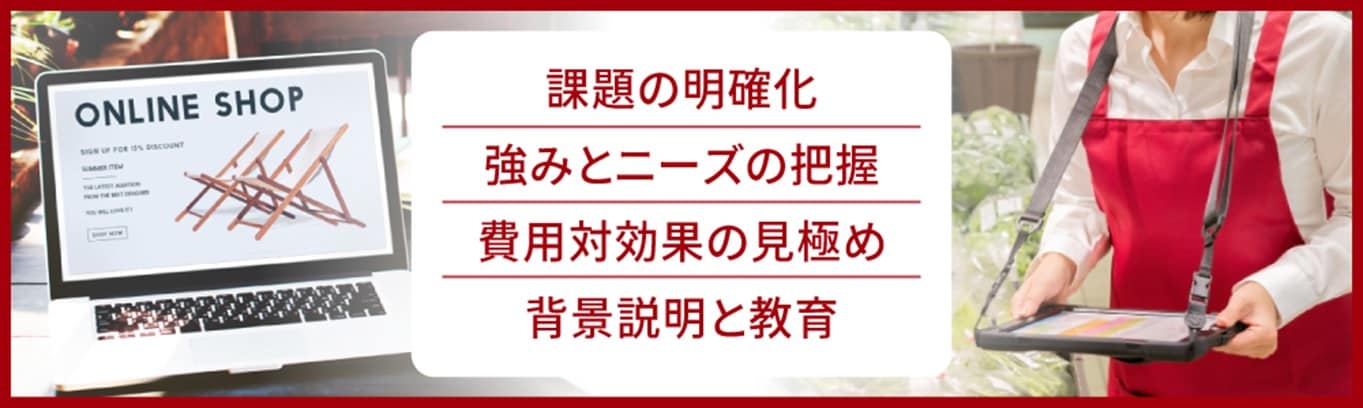
リテールテックは便利な技術ですが、やみくもに導入しても十分な効果は得られません。自社に合った形で計画的に導入・運用することが成功のポイントです。以下では、導入を検討する際に押さえておくべき4つのポイントについて解説します。
5-1. 解決すべき課題を明確化する
リテールテックを導入するにあたっては、まず自社の課題を明確にすることが重要です。課題が曖昧なままでは、導入後に期待する効果を得られない可能性があります。「人手不足の緩和」「レジ業務の効率化」「在庫管理の精度向上」など、改善したい業務領域や具体的な問題点を洗い出しましょう。
たとえば、レジの混雑解消を目的とする場合は、混雑する時間帯や待ち時間の平均をデータで把握し、セルフレジ導入などの対応策を検討します。現状と目指す姿を明確にし、導入の方向性を具体的に描くことでリテールテックの導入を成功につなげられます。
5-2. 自社の強みと顧客ニーズを踏まえて設計する
リテールテックを有効に活用するには、自社の強みを活かしつつ、顧客ニーズに合った設計を行うことが大切です。たとえば、接客力を強みとする店舗にはスタッフ対応を補完するツールが適しており、品ぞろえに特徴がある場合には検索性の高いEC機能の導入が効果的です。
また、顧客視点だけでなく、自社の業務効率や人員体制も考慮する必要があります。顧客満足を優先するあまり、スタッフの業務負荷が増えてしまうと逆効果になります。全体のバランスを見ながら導入を進めましょう。
5-3. 費用対効果を慎重に見極める
初期投資や運用・保守費用などを含めた総コストを把握し、それに対してどの程度の効果が期待できるかを総合的に評価することもリテールテック導入時には重要です。単に導入コストが安いからといって選定すると、期待した成果が得られず、結果的にコストだけがかさむ可能性もあります。
たとえば、在庫管理システムを導入する場合、システム費用や保守費用、社員教育にかかるコストに対して、在庫の最適化や人件費削減、売上の増加といった効果が見込めるかを慎重に検討する必要があります。目先の費用ではなく、将来的なリターンまで含めて総合的に評価することが、導入を成功させるポイントです。
5-4. 社員教育と運用体制を整備する
リテールテックの導入によって業務フローや役割が変化する場合、なぜその技術を導入するのかという背景を丁寧に伝えましょう。導入の意図が不明確なまま現場に展開すると、現場の戸惑いや混乱を招き、定着せずに終わる可能性があります。
導入の経緯を理解してもらった後に、機器やシステムの使い方について教育を行います。業務手法を変えることは一時的に従業員の負担になりますが、自信を持って技術を使えるようになれば業務効率化による負担軽減が期待できます。
以上の本編を踏まえ、当記事の監修者であるNTTドコモビジネスの本多英洋氏があてた音感的に美しく意味深なキャッチフレーズを読者のみなさまにお届けします。
「Retail’s details entail tomorrow’s decisions.」
(訳)小売の細かなことが、未来の意思決定を導く
まとめ
リテールテックとは、小売業にIT技術を導入し業務効率化や顧客体験向上を図る取り組みです。人手不足や運営コスト削減、顧客ニーズ多様化への対応策として注目されています。RFID、無人店舗、RPA、Eコマース、POSなどの技術により、企業は業務効率化・データ活用・売上拡大を実現し、消費者は快適な購買体験を享受できます。成功には課題の明確化、自社に適した設計、費用対効果の検討、社員教育などが重要です。
多店舗展開においては、ネットワークの安定性と一元管理も欠かせません。NTTドコモビジネスの「多店舗ネットワークマネジメント」は、店舗のICT環境を一括管理し、運用負荷を軽減します。業務効率とセキュリティを両立した店舗運営を支援するソリューションとして有効です。
NTTドコモビジネス「多店舗ネットワークマネジメント」の詳細はこちら
また下記ページでは、店舗DXの必要性やメリットなどに関する内容を詳しく解説しています。併せてご覧ください。