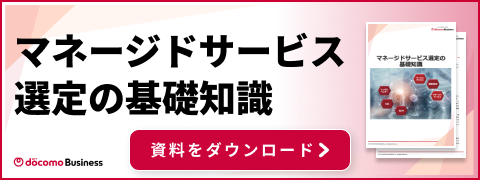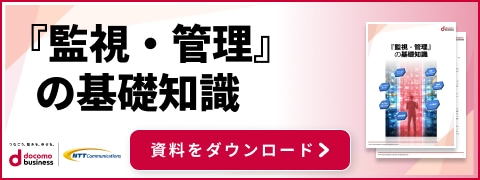ポストモーテムとは?
意味やほかの振り返り手法との違い・やり方を解説
ポストモーテムとは、システムトラブルや業務上の問題が発生した後に、その原因と対応内容をチーム全体で振り返る取り組み(KPT:Keep-継続すべきこと Problem-問題点 Try-次回試み)です。近年、IT業界や大規模プロジェクトを中心に、ポストモーテムが重視されるようになってきました。
ポストモーテムは単なるインシデント報告ではなく、「なぜそのような事態が起きたのか」「どうすれば防げたのか」を徹底的に掘り下げ、再発防止や業務改善につなげる点が特徴です。この文化が根づくことで、組織全体の心理的安全性が向上し、継続的な成長が期待できるでしょう。
当記事では、ポストモーテムの意味や類似概念との違い、導入による効果、具体的な進め方、実施時の注意点などを詳しく解説します。

1. ポストモーテムとは
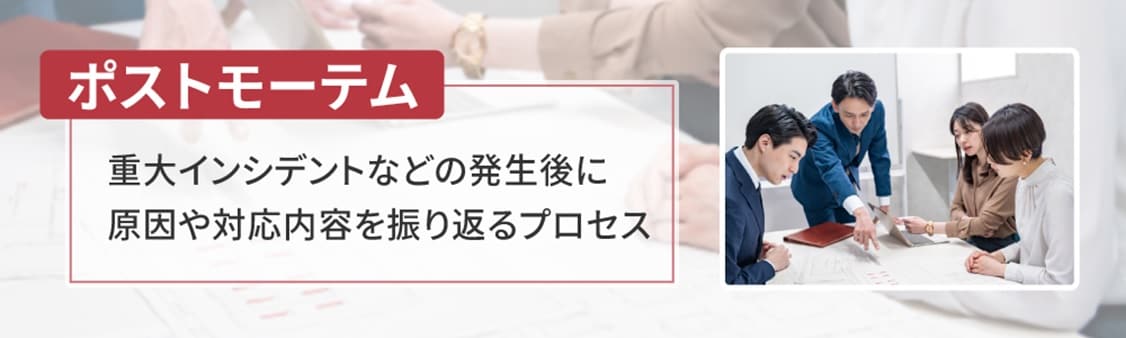
ポストモーテムとは、システムトラブルや業務上の重大なインシデントが発生した後に、その原因や対応内容を振り返るプロセスのことです。英語での直訳は「検死」や「死後解剖」を意味し、トラブルの全容を明らかにするために「仕組み」を徹底的に分析する姿勢を表しています。
ポストモーテムの特徴は、特定の誰かを責めることなく、何が起こったのか、なぜ起きたのかを客観的に整理し、再発防止策を検討する点にあります。このプロセスを通じて、インシデントの教訓が次の改善につながり、組織の信頼性向上にも寄与します。
1-1. ポストモーテムとレトロスペクティブ(振り返り)の違い
ポストモーテムとレトロスペクティブはいずれも業務の改善を目的とする振り返り手法ですが、実施のタイミングや対象に違いがあります。
ポストモーテムはインシデントが発生した後に行い、再発防止や根本原因の分析を目的とするプロセスです。一方、レトロスペクティブはアジャイル開発などで活用される定期的な振り返りであり、インシデントの有無に関わらず実施されます。チームの作業効率やコミュニケーション、プロセスの改善を図る場として活用され、心理的安全性の向上にもつながります。
どちらも重要な学習の機会ですが、ポストモーテムはインシデントへの対応力向上に、レトロスペクティブは日常的な業務改善に主眼を置いている点が異なります。
1-2. ポストモーテムとインシデント報告書の違い
ポストモーテムとインシデント報告書はどちらもトラブルが発生した後の対応記録ですが、目的や読者、内容が異なります。
インシデント報告書は、上司や顧客などへの説明責任を果たすことを重視し、トラブルの概要や原因、復旧内容、再発防止策を簡潔にまとめる文書です。一方、ポストモーテムは上下関係にとらわれず、チームや組織全体を対象に「学びの機会」として位置づけられます。失敗の原因を深く掘り下げ、非難を避けながら教訓を共有することが目的です。
ポストモーテムは関係者全員の視点を反映し、将来の改善につながる幅広い洞察を引き出す柔軟なフォーマットで記録されます。説明文書にとどまらず、組織の成長を支える資産となるのが特徴です。
2. ポストモーテムの効果
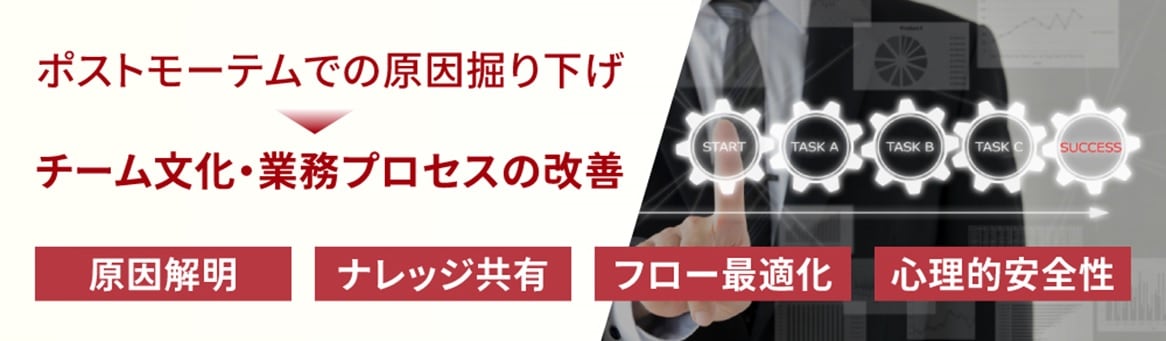
ポストモーテムによって原因を掘り下げて学びを得ることで、技術面の強化だけでなく、チーム文化や業務プロセスの改善にもつながります。ここでは、ポストモーテムの実施によって得られる代表的な4つの効果を解説します。
2-1. インシデントの原因が放置されにくくなる
業務中に発生したインシデントは、目先の復旧対応に追われているうちに根本的な原因の解明が後回しになることが少なくありません。ポストモーテムを導入すれば、発生原因を振り返る時間を意図的に確保できます。
特に夜間や休日に対応したトラブルは、そのまま忘れられてしまうケースが多いため、後日冷静に状況を分析する体制を整えることが大切です。ポストモーテムは、問題の背景や判断の経緯を関係者で共有し、再発防止につなげる仕組みとして機能します。こうした習慣が定着すれば、インシデントの軽視や属人的な対応が減り、継続的な業務改善にもつながります。
2-2. 組織内でナレッジを共有できる
ポストモーテムは、チーム内の共有にとどまらず、組織全体でナレッジを広げる役割も果たします。あるチームで起きたインシデントについて、経緯や対応策を文書化・公開することで、他部署のメンバーにも知見が広がります。特に共通技術を使う複数のプロジェクトが並行する環境では、他部署のインシデントは自チームにとって貴重な学習機会です。
さらに、プロダクトが終了した場合でも、ポストモーテムを中央で管理する体制があれば、ナレッジは組織に残り続けます。ナレッジ共有によって、特定の人やプロジェクトに閉じた情報を資産化でき、チームの技術力や運用スキルの底上げにもつながります。
2-3. 業務プロセスの最適化につながる
ポストモーテムを通じて得られた知見は、インフラやアプリケーションの改善だけでなく、業務フロー全体の最適化にも役立ちます。たとえば、インシデント発生時の意思決定プロセスや、情報共有の手順に課題が見つかるケースもあります。こうした構造的な問題は、通常の技術レビューでは見落とされやすいですが、ポストモーテムによって明文化されることで改善につながります。
業務全体を俯瞰し、改善ポイントを継続的に見つけていくことが、信頼性の高い運用体制を構築するポイントです。
2-4. 心理的安全性につながる
ポストモーテムの重要な前提は「非難しない文化」です。個人を責めるのではなく、仕組みや環境に目を向けて原因を探ることで、メンバーが安心して意見を出せる環境を整えます。この姿勢が組織内の心理的安全性を高め、問題や課題を率直に話し合える雰囲気を生み出します。
インシデントの報告や振り返りが「責任追及の場」ではなく「学びの場」として認識されれば、失敗を隠さず共有する文化が育ちます。心理的安全性の高い環境は、イノベーションや継続的な改善の基盤にもなり、結果的にプロジェクトの成功率やチームの結束力にもよい影響を与えるでしょう。
3. ポストモーテムのやり方
ポストモーテムによって再発防止と業務改善を目指すためには、適切な進行手順と明確な役割分担が欠かせません。ここでは、ポストモーテムを効果的に進める具体的な6つのステップを紹介します。インシデント直後の迅速な準備から、課題の抽出、共有まで、実践的な流れを把握しましょう。
3-1. ポストモーテムのオーナーを決める
インシデント対応が完了したら、すぐにポストモーテムのオーナーを指名します。
オーナーはポストモーテムの進行を担い、関係者のスケジュール調整や会議の開催日時の設定を行います。また、オーナーはインシデントの概要を整理し、影響範囲や対応者の記録、収集したログや時系列の情報などを下準備としてまとめます。この初期ステップを丁寧に進めることで、振り返りが形骸化せず、実効性のあるポストモーテムが実現します。
3-2. ポストモーテムの参加者を決める
ポストモーテムは、インシデント対応に関わったメンバーだけでなく、影響を受けた関係部署や今後の運用に関係するメンバーも含めた広い視点で実施すると効果的です。
たとえば、開発・運用チームに加えて、カスタマーサポート、品質管理、営業担当者などの参加も検討すると、より多角的な分析が可能になります。さまざまな立場の意見を集めることで、見落としがちな根本原因や改善点を浮き彫りにでき、より実効性のある対策を導き出せます。
メンバーを各所から集める場合、会議の冒頭では「非難しない文化」を明確にし、誰もが安心して発言できる場であると共有しましょう。ルールを事前に伝えておくことで、建設的な議論が進みやすくなります。
3-3. 根本原因を検討する
ポストモーテムの中心となるのが、インシデントの「根本原因(Root Cause)」の特定です。ここでは「なぜそれが起きたのか」を繰り返し問いかけ、表面的な原因ではなく、システムやプロセスに潜む構造的な問題を掘り下げることが求められます。
大切なのは、個人のミスを責めるのではなく、「なぜそのミスが起き得たのか」「それを防ぐ仕組みはなかったのか」といった視点で考えることです。「なぜ?」を5回繰り返す「5 Whys」などのフレームワークを活用すると、再発防止につながる実効性の高い学びが得られます。
3-4. インシデントを解決するために何を行ったのか探る
ポストモーテムでは、対応時に何が行われたのかも詳細に振り返ります。初動対応から復旧までの流れを整理し、どの判断が有効だったのか、または改善の余地があったのかを明らかにします。もし対応が遅れた原因が曖昧な責任分担だったとすれば、フローの見直しが必要です。
何が効果的で、何が課題だったかを時系列で振り返ることで、今後のマニュアル化や教育体制の改善にもつながります。このプロセスは、技術だけでなく組織運営にも関わる大切な視点です。
3-5. タイムライン順に情報をまとめ直す
インシデントの経緯をタイムライン形式で整理することで、問題の発端や判断の転機、復旧までの流れが明確になり、関係者全員が共通の理解を持ちやすくなります。
この際、チャットのやり取り、アラートの発生時刻、システムのログ、対応者の行動などはできるだけ正確に記録しましょう。可能であれば、各項目にメトリクスや証拠データのリンクを添えておくと、後から見返したときに検証しやすくなります。曖昧な記憶や印象に頼らず、客観的な情報にもとづく分析が行えるようにすることで、根拠のある改善策の立案につながります。
3-6. 成功要因と課題例をまとめる
ポストモーテムの最後には、対応がうまくいったポイントと、改善の余地があった課題の両方を整理しておきましょう。成功要因は、今後のベストプラクティスとしてほかのプロジェクトにも応用できます。一方で、初動の遅れや情報共有の不足などが課題であれば、その原因を明確にし、具体的な対策を検討します。たとえば「誰が意思決定すべきか曖昧だった」ことが原因なら、責任分担の明確化が必要です。
「何がよかったか」「何をすればよりよくできたか」を明文化することで、チームの経験値が蓄積され、次回以降の対応に生かせる体制が整います。
4. ポストモーテムを行うときの注意点

ポストモーテムを有意義なものにするには、正しい進め方だけでなく「どう向き合うか」も大切です。ポストモーテムでは非難ではなく改善に焦点を当て、再発を防ぐと同時に学びを得られるように心がけましょう。そのためには心理的安全性や客観的な分析姿勢、文化としての継続的運用など、いくつかの重要なポイントに注意を払う必要があります。
ここでは、ポストモーテムを成功させるために押さえておきたい5つの注意点を解説します。
4-1. 人間ではなく仕組みを改善する
ポストモーテムにおいて最も大切なのは「誰が悪かったか」ではなく「なぜそのようなことが起きたか」を追究する姿勢です。個人を責める雰囲気があると、本質的な原因が隠れてしまい、学びを得る機会が失われます。心理的安全性の確保は、参加者全員が率直に意見や疑問を出すための土台となります。
たとえば、「この操作が危険と気づけなかったのはなぜか」「チェック体制は妥当だったか」といった問いかけを通じて、改善すべきは人ではなく仕組みであることを明確にします。「失敗を非難せず、仕組みでカバーする」という文化が根づけば、より強い組織づくりが可能です。
4-2. 問題が発生してすぐに実施する
ポストモーテムは、インシデントの発生後、できるだけ早く行いましょう。時間が経つほど関係者の記憶は曖昧になり、対応の経緯や判断理由を正確に再現することが難しくなります。特に夜間や休日など、通常業務外での対応だった場合は、週明けすぐに会議を設定するなど、タイミングを逃さない工夫が必要です。
早期に実施するように心がけると、ログの保存を行えたりSlackなどのチャット履歴を遡りやすかったりするため、時系列での分析がスムーズに行えます。加えて、現場の臨場感が残っている状態であれば、関係者が「なぜそのように動いたか」といった判断背景も共有しやすくなります。
鮮度の高い事実をもとに議論できることが、ポストモーテムの学びの深さを決定づけるポイントです。
4-3. メンタルモデルまで掘り下げる
ポストモーテムでは、対応時に「何が起きたか」だけでなく、「なぜそのような判断をしたのか」に踏み込むことが大切です。これにより、現場で働く個人の頭の中にある「暗黙知」を形式知として記録・共有できます。
たとえば、操作を間違えた理由が「過去に似た対応で問題がなかったから」といった経験則にもとづいていたとしたら、このメンタルモデルをチーム全体で見直す必要があります。暗黙知を可視化することで、属人的な対応から脱却し、共通認識のもとに再発防止策を設計できます。
「どのように考えたか」「どうしてそう判断したか」といった心理的プロセスの共有は、教育や標準化にも役立ち、次世代への知識継承にもつながります。
4-4. 「起こさない」対策と「流出しない」対策の双方を考える
ポストモーテムでは、同じインシデントを2度と起こさないための「原因除去」に加え、起きたとしても素早く検知し、影響を最小限に抑える「軽減策」の両面から対策を検討する必要があります。
たとえば、設定ミスが原因でトラブルが発生した場合には、チェック機構を強化することが「起こさない」対策になります。一方で、トラブルを素早く検知するためのモニタリングやアラート設計は「流出しない」ための対策です。また、自動フェイルオーバーや復旧プロセスの明文化は、ダウンタイムの短縮に貢献します。
すべてのインシデントが100%防げるわけではない以上、「起きる前提」での準備も組み合わせることが、信頼性の高いシステム運用に不可欠です。
4-5. ポストモーテム文化を根付かせる
ポストモーテムを単発のイベントで終わらせず、継続的な取り組みにしていくためには、「仕組み化」と「評価」がポイントです。テンプレートやチェックリストを用意して運用を定型化し、誰でも同じレベルで実施できるようにすることで、属人化を防げます。また、週次・月次で定例の振り返りを行うと、実施タイミングを逃さず、学びを日常化できます。
同時にポストモーテムの実施が評価される文化があれば、チームのモチベーション向上にもつながるでしょう。過去の事例をナレッジベースにまとめ、社内全体で共有することで、局所的な改善が全体の底上げへと広がります。
「失敗を責める」文化ではなく、「失敗から学びを得る」文化が根づくことで、組織は継続的に強化されます。
まとめ
ポストモーテムは、単なるトラブル対応の記録ではなく、組織が持続的に改善し続けるための手段です。インシデントの原因を分析するだけでなく、チーム全体で知見を共有し、再発防止策や業務改善に活かせる貴重な学習の機会となります。心理的安全性を確保しながら、形式知の蓄積や標準化を進めることで、ナレッジの資産化にもつながるでしょう。
また、ポストモーテムが継続的に運用される文化として根づけば、組織全体の信頼性と対応力を大きく高めることが可能です。起きた事象をその場限りで終わらせず、将来への投資として振り返りの仕組みを確立することが、強い組織づくりの第一歩となります。ポストモーテムを通じて得られる「気づき」を、次の成長の糧として活用しましょう。
業務改善やナレッジの共有をスムーズに行いたい場合は、社内のICT環境を整えるのもおすすめです。NTTドコモビジネスのMSPサービス X Managed®ではDXを進めるさまざまなソリューションを提供しています。
NTTドコモビジネスのMSPサービス X Managed® クロスマネージド
ICTシステムの運用に関しては、ぜひ下記の記事もご覧ください。