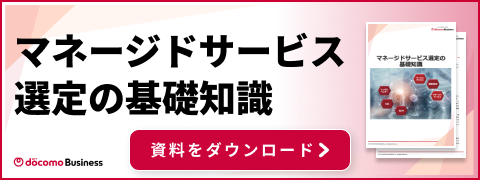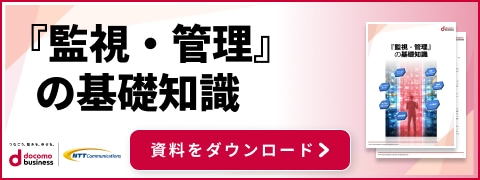クラウドマイグレーションとは?
クラウドへの移行の基礎知識、手順、ポイントまで
働き方改革やDX推進が加速する現代において、クラウドマイグレーションは企業の競争力を左右する重要なテーマとなっています。クラウドマイグレーションとは、端的にいえばクラウドへの移行です。テレワークの普及やサイバーセキュリティの重要性も増しているなかで、クラウド移行は業務効率化や事業継続の観点からも大きく注目されています。
この記事では、クラウドマイグレーションの基本的な知識からメリット・手法、課題まで、実践に役立つポイントについて詳しく解説します。

目次
クラウドマイグレーションとは
クラウドマイグレーションとは、企業が従来のオンプレミス環境で運用していたデータやアプリケーションを扱うシステムをクラウドサービスへ移行する戦略的な取り組みです。
近年では、テレワークの急速な普及と働き方改革の推進により、場所を問わないアクセス環境の構築が求められています。また、サイバーセキュリティ強化のほか、AI(人工知能)やIoTといった最新技術の導入がさまざまなビジネスの側面で急務となっています。
これらの方策を効果的に活用するために、クラウド基盤への需要が高まっています。さらに、多くの企業で長年稼働してきたレガシーシステムの老朽化が深刻化し、高い保守コストの支出やトラブルリスクの増加といった課題が顕在化しています。
クラウドマイグレーションはこれらの課題を解決し、現代ビジネスの変革と競争力強化を実現するためには不可欠な施策です。
クラウドマイグレーションのメリット

クラウドマイグレーションによって得られる主要なメリットについて、簡潔に紹介します。
コストの削減
クラウドマイグレーションにより、従来のオンプレミス環境では必要だったサーバーやネットワーク機器の購入・設置・維持費用などは不要になります。これらの費用の削減によって、大幅なコスト削減を実現することが可能です。
クラウドサービスは従量課金制が一般的であり、必要な分だけ料金が発生します。そのため、過剰なスペックや使用しない機能に対する無駄なコストを削減することもできます。
システム運用・保守の効率化
インフラの運用や保守作業の多くをクラウドベンダーが担うため、企業のIT担当者はメンテナンスに追われることなく、本来注力すべき戦略的な業務に集中できるようになります。システムトラブル時の対応や定期的なソフトウェアのアップデートも自動化されているケースも多く見られます。
企業のIT担当者はシステムの運用・保守にかかっていた多大な時間的コストを削減できるため、運用負担の大幅な軽減と業務効率化を実現することが可能です。
拡張性・柔軟性の向上
クラウド環境の大きな特徴の1つが、需要の変化に応じてリソースを柔軟に増減できるスケーラビリティ(拡張性)です。例えば、新規事業の立ち上げ時には最小限のリソースでスタートし、事業拡大に合わせて段階的に規模を拡張することも容易に実現できます。
また、繁忙期のアクセス増加や一時的な処理負荷の増大にも迅速に対応できる柔軟性の高さも特徴です。クラウド環境の拡張性・柔軟性を活用することにより、ビジネスの成長や市場環境の変化に柔軟に対応できるシステム・運用体制を構築できます。
BCP(事業継続計画)対策の強化
クラウド環境では、データの多重バックアップや複数のデータセンターを地理的に分散配置したリスク分散が標準的に提供されています。自然災害やシステムトラブル発生時にも、別の地域に設置されたデータセンターによりサービスを継続できます。
これらは災害時の迅速な復旧と事業継続を実現させるため、BCP対策の強化に役立てることが可能です。オンプレミス環境では困難だった高度なBCP対策を比較的低コストで導入できます。
クラウドマイグレーションを実現する手法
クラウドマイグレーションを実現するには、システムの特性や企業の要件に応じて適切な移行方法を選択することが重要です。ここでは、主要な4つの手法について簡潔に解説します。
リホスト(リフト&シフト)
既存システムのアプリケーションやデータ、設定内容をほとんど変更することなく、オンプレミス環境からクラウド環境へそのまま移行する手法です。「リフト&シフト」とも呼ばれます。
システムの構造や動作を維持しながら単純にプラットフォームを変更する方式のため、移行作業の技術的負担やリスクを最小限に抑えることができます。短期間かつ低コストでクラウド環境への移行を実現できる点がメリットです。
リプラットフォーム
既存システムの基本的な構造や機能は維持しながら、1部のコンポーネントやミドルウェアをクラウド環境に適したものへ置き換える手法です。
例えば、データベースをクラウド環境のマネージドサービスに変更したり、アプリケーションサーバーをクラウドネイティブなものに更新したりするなどの調整を行います。
リホストと比較すると、クラウドの機能やスケーラビリティを活かしやすい点が特徴です。リプラットフォームは、コストパフォーマンスと移行期間のバランスが取れた現実的なアプローチとして注目されています。
リビルド
既存システムのアーキテクチャやコード構成を全面的に見直し、クラウド環境向けにゼロから再構築する抜本的な手法です。
マイクロサービスアーキテクチャやコンテナ技術、サーバーレス機能など、クラウドネイティブな設計思想と最新技術を最大限取り入れることを目的とします。リビルドにより、スケーラビリティや可用性、保守性の大幅な向上が期待できます。
リライト
既存システムの機能や仕様はそのまま維持しながら、使用しているプログラミング言語やフレームワークを現代的なものに書き換えて移行する手法です。レガシーな言語やサポートが終了した古い技術から、現在主流となっている開発環境へ移行します。
リライトはシステムのパフォーマンス向上、セキュリティ強化、新技術への対応力向上を目的とします。機能改修を最小限に抑えながら、技術的負債を解消できる効果的なアプローチです。
クラウドマイグレーションの手順

クラウドマイグレーションを成功させるためには、体系的なアプローチが欠かせません。ここでは、実践的な6つのステップについて、おおまかな流れについて解説します。
1.現状分析と課題の洗い出し
現行システムや業務プロセスの詳細な調査を実施し、IT資産の棚卸しやシステム間の依存関係を正確に把握する段階です。
ハードウェア・ソフトウェアの構成、データベースの規模、ネットワーク接続、ライセンス情報などを体系的に整理し、移行の複雑さや技術的課題を事前に特定します。
この分析と洗い出し作業を通じて移行対象の選定や優先度の決定が可能となり、プロジェクトの全体像をつかむための基盤が整います。
2.移行目的・ゴール設定
コスト削減、運用効率化、セキュリティ強化、災害対策強化など、クラウドマイグレーションによって達成したい具体的な成果を明確に設定する段階です。
コスト削減率、処理性能向上率などの定量的な目標値も合わせて設定することで、移行による効果の測定が可能になります。目的が明確であれば経営層や関係者の理解と協力も得やすくなり、プロジェクト推進の原動力となります。
3.移行計画・スケジュール策定
どのシステムをいつ、どのような順序で移行するか、といった詳細なマイルストーンと担当者を明確に定める段階です。システム間の依存関係を考慮した移行順序の決定、予算やリソースの確保、想定されるリスクと対策についてもこの段階で綿密に検討します。
現実的かつ実行可能な計画を策定することにより、プロジェクトの成功確率は格段に向上するでしょう。
4.移行方式・手法の選択
移行方式を決定するためには、各システムの特性、技術的な制約、予算、スケジュールなどを総合的に評価することが重要です。そのうえで、リホスト、リプラットフォーム、リビルド、リライトなどの手法から最適な移行方式を選択します。
選択した方式に応じて必要となるクラウドサービス、移行ツール、技術支援パートナーも同時に決定し、クラウド移行の実行に向けた具体的な準備を進めます。
5.移行リハーサル・本番移行
本番移行の前には必ずテスト環境でリハーサルを実施し、移行作業の手順確認、所要時間の測定、潜在的な問題点の洗い出しを行います。多くの場合、想定どおりには進まず、リハーサルによって本番移行にともなう課題や問題点が見つかるでしょう。
本番移行時は業務への影響を最小限に抑えるため、作業日時や実施体制を関係者に事前周知します。規模の大きなシステムの場合は段階的に進められることが多いため、特に詳細な進捗管理とトラブル発生時の迅速な対応体制を整備することが重要です。
6.移行後の運用・最適化
移行後はクラウド環境の特性を最大限に活かすため、リソースの最適化、セキュリティ対策の強化、業務プロセスの見直しを継続的に実施する必要があります。
パフォーマンスチューニング、自動化の推進、コスト最適化などを通じて、クラウド活用効果の最大化を図ります。
クラウド移行における課題・問題点
クラウドマイグレーションでは、多くのメリットが期待できる一方で、企業が注意すべき課題や問題点も存在します。以下の課題・問題点を事前に理解し、対策を講じることが成功への近道です。
初期コスト・運用コストの正確な見積もりが難しい
クラウド移行ではデータ移行作業、システム再構築、新たなクラウドサービス導入にともなう初期投資が必要となります。特に大規模なレガシーシステムの場合、これらのコストが膨大になることがあるため、事前の正確な見積もりが困難でしょう。
クラウドサービスの多くは従量課金制を採用しているため、運用開始後のコストも実際の利用状況によって大きく変動する特性があります。これらは長期的な費用計画の立案が複雑になる要因であり、予算管理の難易度が高まります。
クラウドマイグレーションによるクラウド移行を成功させるためには、コストの正確な見積もりが困難な点を考慮しながらも、綿密な費用計画を立案することが重要です。
セキュリティリスクが高まる
クラウド環境では、企業の重要なデータがインターネット経由で管理されるため、情報漏えいや不正アクセスなどのセキュリティリスクが従来よりも高まる可能性があります。
クラウドプロバイダーと利用企業の間で、セキュリティ責任の分担を明確にすることが重要です。合わせて、継続的なセキュリティ評価と改善活動を実施することが求められます。
具体的なセキュリティ対策として、適切なアクセス制御、データの暗号化、監視体制の構築が欠かせません。
既存システムとの連携・互換性が難しい
長年にわたって運用してきたオンプレミス環境のシステムは、クラウド環境とはアーキテクチャや技術仕様が根本的に異なる場合が多いといえます。そのため、システム間の連携や互換性の確保が大きな技術的課題となります。
特定のハードウェアに依存した処理や独自開発のミドルウェアを使用しているシステムは、そのままの形ではクラウドに移行できないケースも少なくありません。
このような課題に対しては、データ連携のAPI化やコンテナ技術を活用したハイブリッドクラウドの運用により、段階的な移行を検討するとよいでしょう。
社内人材・スキル不足が発生する
クラウド技術に精通したIT人材は市場全体で不足しており、社内での計画的な人材育成や外部パートナーとの連携が不可欠です。
クラウド関連のスキル不足は、移行プロジェクトの遅延や運用開始後のトラブルを発生させるリスクを高める要因となります。そのため、事前の教育プログラムの実施や適切な体制の整備が、クラウド移行を成功させるための鍵です。
IT人材の不足に関するより詳細な説明については、こちらの記事をご覧ください。
「IT人材不足が深刻化する理由とは?ITエンジニア不足が企業に与える影響やとるべき対策について解説」
クラウド移行で見落とされがちな“隠れコスト”とは

クラウドマイグレーションでは、実際には見落とされやすい“隠れコスト”が存在し、これらが予算超過の要因となるケースが多発しています。
- データ転送料、ストレージ費用の隠れコスト
- セキュリティ対策関連費用の隠れコスト
- 継続的な最適化作業の費用の隠れコスト
- 人材育成、スキル習得費用の隠れコスト
まず、データ転送料やストレージ費用は、扱うデータの量によって大きく変動するため、予想以上にコストが膨らむケースが多くなっています。セキュリティ関連費用は、専門的なセキュリティツールや外部監査サービスの導入費用などです。
さらに、継続的な最適化作業にかかる費用は、クラウド環境の特性を最大限活かすための運用コストとして、長期的な負担として蓄積されます。加えて、クラウド技術に対応できる人材の確保や既存社員の教育訓練、外部専門家の招聘費用など、人材育成・スキル習得費用も隠れコストの一つです。
これらの隠れコストを事前に特定し、総合的なコスト管理と見える化を徹底することが重要となります。クラウド移行の真のROI(投資対効果)を正確に評価し、最大化することがクラウド移行の成功の証です。
クラウドマイグレーション推進におけるコツ・ポイント
クラウドマイグレーションの成功には、適切な計画と実行戦略が必要不可欠です。ここでは、実践的なコツやポイントについて簡潔に解説します。
小規模からの段階的移行
クラウド移行の際は、一度にシステム全体を移行するのではなく、小規模な範囲から段階的に進めることが推奨されます。段階的なアプローチにより、移行による業務への影響を最小限に抑えながら、問題点や課題を早期に発見して適切に対処することが可能です。
段階的な移行により、各段階で得られた知見を次の移行フェーズに活かすことができるため、プロジェクト全体のリスクを大幅に軽減できます。
既存システムとの連携強化
クラウド環境と既存システムの間では、アーキテクチャやデータ形式の違いから連携に関する課題が生じることが多くなっています。そのため、移行前にデータの互換性や連携方法について十分に検討することが重要です。
必要に応じてシステム改修やインターフェースの調整を実施することにより、業務の継続性を確保しながら、クラウド環境の利点を最大限に活かすことが可能になります。
社内教育・スキルアップ施策
効果的な教育プログラムの設計と実施により、組織全体のクラウド活用力を向上させることが成功の一助となります。eラーニングやハンズオン研修を組み合わせることにより、理論的な知識と実践的なスキルの両方を効率的に習得できます。
スキルマップを作成し、個人のレベルに応じて段階的に習得目標を設定することによって、組織全体のクラウド活用力を体系的に底上げすることが可能です。
移行後の運用・改善サイクルの構築
クラウド移行完了後も継続的な改善活動が不可欠です。リソースの最適化、セキュリティ対策の強化、パフォーマンスの監視を継続的に実施し、問題点を早期に発見・対処する仕組みと体制を整備する必要があります。
自動化ツールの積極的な活用や運用プロセスの見直しも合わせて進めることにより、運用負荷の軽減と全体的な効率化を同時に実現できます。
トラブル発生時のリカバリープラン策定
トラブルが発生する前に、包括的な対応手順と役割分担、緊急時の連絡体制を明確化し、データのバックアップや復旧手順を詳細に整備しておくことが重要です。
RTO(目標復旧時間)やRPO(目標復旧時点)を具体的に設定し、これらの目標値に基づいた災害復旧計画を策定・運用することで、事業継続性を確保できます。
クラウドへの移行を徹底サポートするNTTドコモビジネスの導入支援・マネージドサービス
クラウドマイグレーションにはさまざまな技術的課題や運用面の複雑さがあり、企業が自社のリソースだけで解決することが困難な場面も考えられます。
そこで、NTTドコモビジネスでは、AWS・Azureへのクラウド移行を包括的にサポートする導入支援サービスを提供しています。
AWS導入支援・運用サービス
NTTドコモビジネスのAWS導入支援・運用サービスは、AWS導入に必要な設計・構築・移行・運用といったメニューを一気通貫で提供する包括的なソリューションです。大規模なAWS導入実績を豊富に有しており、企業規模や業種を問わず最適な移行戦略を提案できる体制を整えています。
移行だけではなくその後の運用にも対応できるため、24時間365日有人対応の監視運用ソリューションも同時に提供します。専門技術者による高いサポート力により、AWSの機能を最大限活用した効率的なシステム運用を実現可能です。
AWS導入支援・運用サービスをご活用いただくことにより、移行のサポートだけではなく、クラウド移行後の運用負荷を大幅に軽減し、本来注力すべき戦略的業務に集中いただけます。
Azureマネージドサービス
Azureマネージドサービスは、Azure導入フェーズから運用フェーズまでの全工程を一気通貫で支援するサービスです。短納期での移行を可能にするメニューのほか、Open AIを活用した先進的なソリューションメニューも提供しています。
特に独自の閉域接続サービスにより、インターネットを経由しない安心安全なハイブリッドクラウド環境を構築できる点が大きな特長です。セキュリティ要件の厳しいお客さまでも安心してクラウド移行を進められます。
また、グローバル展開にも対応できる大規模なAzure導入実績を有しており、多国籍企業の複雑な要件にも柔軟に対応可能です。運用段階では、専門チームによる継続的な最適化支援により、コスト効率とパフォーマンスの両立を実現します。
まとめ
働き方改革とDXが進むいま、クラウドマイグレーションは企業競争力を左右する中核施策です。クラウド移行によりコストの削減、保守・運用の効率化、リソースの柔軟化、BCPの強化が期待できます。
一方で、セキュリティリスクや既存システムとの連携、人材・スキル不足などの課題もあるうえ、データ転送料やセキュリティ対策、人材育成など“隠れコスト”の存在も無視できません。自社だけで対応することが難しいと感じる場合には、外部サポートも検討するとよいでしょう。
この記事で解説したとおり、クラウドマイグレーションを実現する方法はさまざまです。自社の状況に合わせて、最適な移行方法を検討しましょう。リプラットフォームについては、こちらの記事でも詳しく解説しているため、合わせてご覧ください。