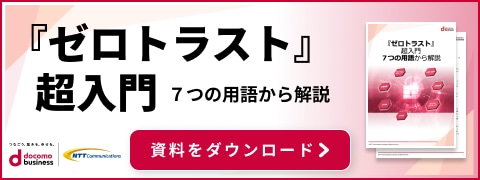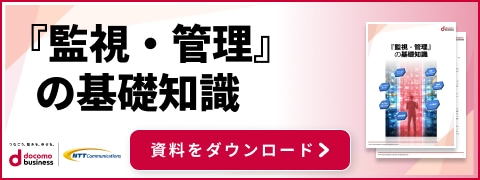キャパシティプランニングとは?
ICTシステムの安定稼働とコスト最適化を実現する戦略的アプローチ
ICTシステムの安定稼働を実現するためには、適切なリソース計画が必要です。
キャパシティプランニングは、「システムが遅い」「突然のアクセス増加によりダウンした」といった問題を未然に防ぐために欠かせないプロセスです。将来の需要を予測して適切なリソースを計画的に確保することによって、システムトラブルのリスクを低減できます。
この記事では、キャパシティプランニングの基本や実施手順とともに、ICTシステムの安定稼働とコスト最適化を実現する戦略的アプローチを解説します。

目次
キャパシティプランニングとは

はじめに、キャパシティプランニングについての基礎知識と合わせて、リソース管理・パフォーマンス管理との違いについて解説します。
ICTシステムを構成するためのリソースを予測・計測するプロセス
キャパシティプランニングとは、需要や負荷の変化に対応できるように、ICTシステムにとって必要なリソースの量や処理能力を予測し、計画的に確保するプロセスのことです。
対象となるリソースには、サーバーやストレージなどのハードウェア、オペレーティングシステムやアプリケーションなどのソフトウェア、ネットワーク帯域などが含まれます。適切なキャパシティプランニングを行うことにより、システムリソースが不足する状況を事前に防止し、常に一定のサービス品質を確保することができます。
リソース管理、パフォーマンス管理との違い
キャパシティプランニングは、リソース管理やパフォーマンス管理と関連していますが、それぞれ異なる目的と役割を持っています。
リソース管理とは、既存のリソースを効率良く活用して業務の生産性を向上させ、リソースを適切に配分することです。またパフォーマンス管理とは、サーバーやネットワーク機器などICTインフラの状態を継続的に監視し、必要に応じて最適化するプロセスを指します。
これらに対して、キャパシティプランニングは将来の需要予測に基づき、システムの安定稼働とコスト最適化の両立を目的として、必要なリソース量や能力を計画するプロセスです。
それぞれを連携させることによって、ICTシステムの効率的な運用と長期的な成長を支える基盤を構築できます。
キャパシティプランニングの重要性と役割

キャパシティプランニングは多くの重要な役割を担っています。なぜ重要とされているのか、その理由や役割について解説します。
システムの安定稼働とパフォーマンス維持
キャパシティプランニング最大の目標は、ITリソースの最適な活用を図りながら、将来的な負荷増大や需要変動にも耐えうるシステム環境を事前に準備することです。適切なプランニングにより、システムの負荷が増大しても安定したパフォーマンスを維持することが可能になります。
また、長期的な負荷データの観測と分析により、システムが過負荷となる状態を予測して事前に対策を講じることができるようになります。ユーザーに対して一貫した品質のサービスを提供し続けることが可能となり、ビジネスの信頼性向上にもつながるでしょう。
コストの最適化
キャパシティプランニングを適切に行なわないと、リソースの過剰投資(オーバースペック)や不足(アンダースペック)という問題が発生します。
オーバースペックな環境では、使用されないリソースに対しても維持管理スコストが必要です。反対にアンダースペックな環境では、システムの拡張や性能向上のために追加投資をすることになり、結果的には高いコストがかかります。
キャパシティプランニングを通じて現在から将来の需要を正確に予測し、必要十分なリソースを適切なタイミングで確保することによって、コストの最適化を実現可能です。
SLA(サービスレベルアグリーメント)の実現
SLAとは、サービス提供者とユーザーの間で締結される、サービス品質に関する合意事項です。この契約では、システムの可用性、応答時間、処理能力といった具体的な数値目標が設定されます。
キャパシティプランニングは、SLA目標を達成するための基盤です。キャパシティプランニングを通じて、現在のキャパシティと将来の需要を一致させることにより、SLAで定められたサービス品質を維持して顧客満足度の向上につなげることができます。
SLAについては、こちらの記事でSLO(サービスレベルオブジェクティブ)と合わせて詳しく解説しているため、合わせてご覧ください。
将来需要への対応
ビジネス環境は常に変化しており、システムに対する需要も時間とともに変動します。キャパシティプランニングは、過去のデータやユーザーの行動パターン、ビジネスの成長予測などを分析し、将来の需要に効果的に対応するためには欠かせないプロセスです。
例えば、小売業のオンラインショップでは、季節的な需要変動や特売イベント時におけるアクセス集中を予測し、それに備えたリソース計画を立てることが重要です。一時的なアクセス集中によってサービスが停止してしまうと、売上機会の損失だけでなく顧客からの信頼も失うことになります。
このような課題に対応するためにも、キャパシティプランニングが重要です。
リスク管理とシステムトラブルの予防
キャパシティプランニングは、システムトラブルのリスク管理においても重要な役割を果たします。リソース不足によるシステムダウンやパフォーマンス低下は、ビジネスに大きな影響を与える可能性があることが理由です。
また、サイバーセキュリティの観点でも、キャパシティプランニングは重要です。例えば、ファイアウォールやIDS/IPS(侵入検知・防止システム)、暗号化プロセスといったセキュリティ対策は、システムに対しさらなる負荷をかけます。
これらのセキュリティ対策を効果的に機能させるためには、十分なリソースを確保する必要があります。適切なキャパシティプランニングにより、セキュリティ対策のための処理能力を確保することによって、潜在的なセキュリティ上の脅威からシステムを保護することが可能です。
近年のサイバーセキュリティについて詳しく知りたい方には、こちらの記事もおすすめです。
ユーザー体験の向上
効果的なキャパシティプランニングは、最終的にユーザー体験の向上につながります。システムの応答時間が短く、安定したパフォーマンスが維持されることによって、ユーザーはストレスなくサービスを利用できるようになるためです。
また、リソースのムダや不足がなくなることによりシステム全体の効率が向上するため、新機能の追加や改善に対してリソースを振り分けられるようになります。
キャパシティプランニングはシステムの安定稼働を確保するだけでなく、優れたユーザー体験を提供するための基盤といえます。
キャパシティプランニングの手順

効果的にキャパシティプランニングを実施するためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、キャパシティプランニングの各ステップについて1つずつ解説します。
現状分析:ワークロード情報の収集
最初のステップは、システムが実行する処理の種類や量である「ワークロード(負荷情報)」を正確に収集することです。この段階では、IT担当者や関連部署へのヒアリングを通じて、現在の業務の種類・処理の量・実行頻度・解決すべき課題などを詳細に把握します。
具体的には次のような項目です。
- CPU情報(タイプ、個数、クロック数)
- メモリーサイズ
- ディスク情報(タイプ、容量)
- ネットワーク情報
- オペレーティングシステム(タイプ、バージョン)
- アプリケーション
など
収集したデータは可能な限り定量的に測定し、客観的な分析を行なえるようにすることが重要です。
需要予測:将来的な拡大計画の検討
収集したワークロード情報をもとに、システムやサービスの将来的なニーズを予測します。過去のデータパターンや予測されるビジネスの成長パターンを分析し、将来のシステム負荷と需要を推定するステップです。
需要予測はビジネス部門との密接な連携が重要であり、新規サービスの導入計画や事業拡大戦略といった情報を取り入れることで、より精度の高い予測が可能になります。
キャパシティ計画:必要なリソースの見積り
現状分析と需要予測の結果を踏まえ、必要なリソースの量や能力を具体的に見積る段階がキャパシティ計画のステップです。この段階では、通常時と最大時のシステム負荷に耐えうるシステム環境を設定し、十分なリソースを確保するための方法や手順を定めます。
また、将来の拡張性や冗長性を確保するためのバッファも計画に含めることが重要です。キャパシティ計画では、コスト効率も重要な要素であり、過剰投資を避けつつ必要十分なリソースを確保するバランスが求められます。
監視と評価:計画との差異分析
システムがリリースされたあとも、性能問題のリスクが常に存在するため、継続的な監視と評価が欠かせません。この段階では、実際のシステム負荷やパフォーマンスを継続して測定し、計画との差異について分析します。
時系列の変化は、次の3つの要素に分解して考えると効果的です。
- トレンド(長期的な変化)
- サイクル(日次・週次・月次などの周期的な変化)
- イベント(セールやキャンペーンなどによる突発的な変化)
計画段階の予測と実際の測定値との乖離を把握することにより、将来的なキャパシティ計画変更の必要性について検討する材料となります。
調整:リソースの追加・削除・設定変更
監視と評価の結果に基づき、必要に応じてリソースの追加や削除、設定の変更といった調整を行ないます。分析結果から明らかになった問題点や改善点に対して、具体的な対策を講じるチューニングを実施します。
チューニングの目的は、システムを最適化して求められる性能要件を達成することです。調整は段階的に行ない、調整実施後にはパフォーマンスへの影響を測定して、調整の効果を確認することが重要です。また、調整の履歴を記録しておくことにより、将来的な計画の参考になります。
目標設定:スループット・レスポンスタイム・リソース使用率
キャパシティ改善のための対策を立案する際には、具体的な目標を設定することが重要です。この段階では、主に次のような指標を軸として明確な目標値を定めます。
- スループット(単位時間当たりの処理量)
- レスポンスタイム(処理の要求から応答までの時間)
- リソース使用率(CPU、メモリー、ディスクなどの使用率)
目標設定は現実的かつ達成可能な値を設定することが重要であり、過去のパフォーマンスデータや業界標準などを参考にするとよいでしょう。定める目標はビジネス要件やSLAと関連付けることが重要です。
改善方法の選定:チューニング・スケールアップ・スケールアウト
キャパシティ改善の主要な方法としては、チューニング・スケールアップ、スケールアウトなどが挙げられます。まずはチューニングから実施し、対応が困難な部分は他の方法により改善させることを検討していく方法が一般的なアプローチです。
チューニングは、既存のリソースを最適化することによって性能を向上させる方法であり、コスト効率が高い点が特徴です。スケールアップは既存のサーバーやコンポーネントのリソースをより高性能なものに置き換える方法で、単一サーバーの処理能力を向上させられます。
対して、スケールアウトは複数のサーバーを増設して負荷を分散させる方法であり、水平方向のスケーラビリティとも呼ばれます。改善方法の選定では、コスト・実装の容易さ・将来の拡張性などを総合的に考慮し判断することが重要です。
キャパシティプランニングの課題と解決策
キャパシティプランニングを実施するうえでは、いくつかの課題に直面することがあります。これらの課題について理解し適切な解決策を講じることで、より効果的なリソース計画を実現してシステムの安定稼働とコストの最適化を両立することが可能です。
正確な需要予測の難しさ
キャパシティプランニングにおける主要な課題の1つは、将来の負荷需要に対し正確な予測が困難なことです。ビジネス環境やユーザーの行動パターンは常に変化しており、システムが処理する能力やデータ量を正確に予測することは容易ではありません。
この課題に対処するためには、過去のデータを活用したトレンド分析や、AI予測モデルを使用した高度な予測手法を導入することが効果的です。また、予測の精度を高めるためにビジネス部門との連携を図り、マーケティングキャンペーンや新製品の発売計画などのイベント情報を積極的に取得することも重要になります。
柔軟性の確保
予測が難しい需要の変動に対応するためには、キャパシティプランニングに柔軟性をもたせることが重要です。従来のオンプレミス環境では、リソースの増強に時間とコストがかかるため、ピーク時の需要に合わせてリソースを確保する傾向がありました。
しかし、この方法では平常時にリソースが過剰になり、コスト効率が悪くなります。この課題を解決するためには、クラウドサービスの活用が効果的です。クラウドサービスは必要に応じてリソースを迅速に増減できるため、需要の変動に対して柔軟な対応が可能です。
適切なツールの選択、活用
キャパシティプランニングを効率的に進めるためには、目的に合った分析・予測ツールを選定し、それらの機能を十分に理解して活用することが欠かせません。
理想的なキャパシティプランニングツールは、ビジネス要件に応じて容易にスケールアップ・スケールダウンできる柔軟性を持ち、作業負荷量とユーザー数の変動に対応可能な機能を備えています。
適切なツールを選択することにより、リソースの割当・作業負荷の配分・キャパシティプランニングに関する意思決定を十分な情報に基づいて行うことが可能です。
クラウド環境における動的キャパシティ管理
クラウド環境では、需要に応じてリソースを動的に追加・削減できるため、積極的に活用することが効果的なキャパシティ管理の鍵となります。
例えば、AWS Auto Scalingのようなサービスを利用することにより、アプリケーションの負荷に応じて自動的にリソースを増減させることが可能です。このサービスは特定のCloudWatchメトリクスを追跡し、設定したしきい値に基づいて自動的にスケーリングします。
動的なキャパシティ管理が実現できれば、運用負荷も大きく軽減できるでしょう。AWSにおける運用・メンテナンスについて知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
「X Managed」ならICTのデザインからオペレーションまでお任せいただけます
キャパシティプランニングを含むICTシステムの設計から運用まで、一貫したサポートが必要なお客さまには「X Managed」がおすすめです。
NTTドコモビジネスのMSPサービス「X Managed」は、運用業務のベストプラクティスを標準化した「セミオーダー型」のマネージドサービスであり、デザイン・デリバリー・オペレーションをワンストップで提供します。
1,000件以上の導入実績、1,000名を超えるSE体制でお客さまのICT環境を最適化します。トータルマネージドサービスのため、運用効率を意識したデザインからオペレーションに至るまで、一気通貫で対応可能です。
お客さまが必要とするサービスレベルに応じて自由に選択し組み合わせることが可能なサービス/メニューを用意しており、お客さまの要望や時代の先端技術・トレンドに応じて多彩なコンポーネントをご利用いただけます。
NTTドコモビジネスのMSPサービス「X Managed」
まとめ
キャパシティプランニングは、システムの安定稼働とコスト最適化の両立を目指し、必要なリソース量や処理能力について計画するプロセスです。安定稼働・コスト最適化だけではなく、リスク管理やシステムトラブルの予防、ユーザー体験の向上などの観点からも重要視されています。
キャパシティプランニングの実施には、正確な需要予測や適切なツールの選択・活用など、さまざまな面で課題があります。この記事で解説した手順を参考にして、キャパシティプランニングを1つずつ進めてみてください。