安否確認はSNSでも大丈夫?SNSが災害時に役立つ理由や利用時の注意点を解説
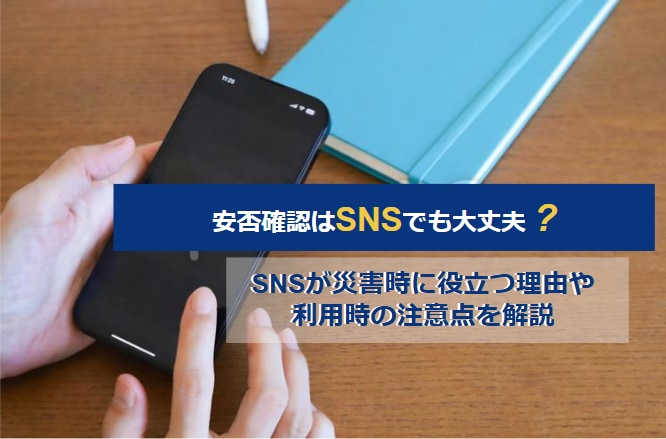
近年、頻発する地震や台風などによる自然災害が発生した際の安否確認の重要性がますます高まっています。災害時には電話回線が混雑し、連絡が取りづらくなることを踏まえ、SNSが安否確認の手段として注目を集めているところです。SNSの活用により、迅速かつ効率的に安否確認が可能ですが、SNSを利用する際には注意点も存在します。
SNSが災害時の安否確認にどのように役立つのか、気を付けるべきポイントについて詳しく解説します。
もくじ
災害時の安否確認にSNSが役立つ理由・メリット

SNSは、地震や台風などによる自然災害時において非常に有効なツールです。広範囲に情報を発信でき、日常的に使用しているため操作に戸惑うことがなく、既読表示機能を活用することでやり取りができない状況でも安否を確認できます。プライバシーの保護など、利用時には注意が必要ですが、SNSは安否確認に活用されています。
まずは、災害時におけるSNS活用のメリットを見ていきましょう。
広範囲に安否状況を発信できる
会社によって安否確認が行われる場合には、多くの人に対して連絡を取る必要があります。これまでのように電話であれば、すべての人に対して個別に連絡を取らなくてはなりません。
しかし、SNSはその特性上、広範囲に情報を迅速に発信することが可能であるため、一度に安否状況の情報を届けることができます。
またFacebookのセーフティボタン、Xのリポスト機能、LINEのグループメッセージを活用すれば、連絡のやり取りをせずに、安否情報をまとめて報告することも可能です。安否確認のような緊急的な場合には、迅速かつ効率的に情報を発信できるSNSはとても有効です。
日常的に使用しているため操作に戸惑うことがない
緊急時には、操作に戸惑うことなく、スムーズに情報を発信できることが大切です。災害時だけ使用するようなツールは、訓練が必要だったり、ストレスを感じたりする可能性があります。
一方、SNSであれば日常的に私用している人が多いため、万が一の際にも操作に戸惑うことは少ないでしょう。実際に、2016年に発生した熊本地震では、約9割の方が「LINEが問題なく利用できた」と回答しています。
総務省によると、日本のSNSの利用率は年々増加しており、2022年には1億200万人が利用していると報告されています。このように、SNSは多くの人が使い慣れている情報発信ツールであるため、災害時にも戸惑うことなく、安否状況の発信・確認が可能です。
やり取りができない状況でも既読表示機能を活用できる
災害時には、通信インフラが被害を受け、メッセージのやりとりができないことがあります。
そのような状況では、SNSの既読表示機能を活用しましょう。例えば、LINEの既読機能を使えば、相手がメッセージを読んだかどうかを把握することが可能です。また、SNSのプロフィールやアイコンに安否状況を記載することで、情報を発信することもできます。
このように、直接メッセージのやり取りが難しい場合でも、自分の不安を軽減できるとともに、相手にも安心感を与え、安否を確認・発信する手段として役に立ちます。
また、やり取りすることをなく、安否を伝えられるので、災害時に貴重なスマートフォンのバッテリー消費の抑制にも有効です。
災害時の安否確認にSNSを活用する際の注意点

SNSは災害時の安否確認において非常に有用なツールですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。
SNSを効果的かつスムーズに活用するためのルールを事前に確認し、信頼性を確保するための対策を講じておくことが重要です。
実際に、注意点を詳しく見ていきましょう。
個人のアカウントを会社に教える必要がある
災害時にSNSを利用して安否確認を行う場合には、個人のSNSアカウントを会社に教える必要があります。
会社が従業員の安否を迅速かつスムーズに確認できるようになりますが、「仕事とプライベートを分けたい」と考える従業員にとって、プライバシー保護の観点から問題とならないような取り組み方が大切です。
事前に会社と個人の間で合意を得るなど慎重に対応することが重要になります。
情報漏洩のリスクがある
SNSは、公開範囲を設定できるものの、公開性が高いツールであるため、情報漏洩のリスクはゼロではありません。
特に、安否確認の際には住所や連絡先などの個人情報が含まれることが多いため、情報の取り扱いには十分な注意が必要です。
また、退職した従業員がグループに残っていたり、誤って社外の人をグループに招待してしまったりすると、アカウントの乗っ取りや、外部への情報漏洩リスクなどが高まります。
安否確認時のSNSの使い方、アカウント情報の管理方法、知り得た情報の守秘義務等のルール設定を明確に定めておきましょう。
社内で共通のSNSを使う必要がある
SNSで従業員の安否確認を行う場合には、前提として、社内で共通のSNSを使用しなければなりません。
ただし、たとえ無料のSNSだったとしても、安否確認のためだけにアプリをインストールするのに抵抗がある従業員もいるかもしれません。
また、従業員の世代によっては、選定したSNSツールの操作に慣れていない可能性もあります。たとえば、LINEの利用率は10〜50代と幅広い層で90%を超えている一方、Facebookでは10〜20代の利用率が低くなっています。
なるべく幅広い層で利用されているSNSツールを選定のうえ、事前に従業員に対してSNSの導入についての同意を得たうえで、安否確認に活用するようにしましょう。
安否情報の収集に時間がかかる
SNSを活用した安否確認では、情報を適切に抜き出す作業が手間を要します。
災害時に担当者が従業員それぞれの安否情報を手作業で集計してまとめなければならないのに加え、組織の規模が大きいほど集計が煩雑になります。
特に、災害の状況は刻々と変わるため、個別に集まった情報を手作業で集計すると、ヒューマンエラーも起きやすい点には注意が必要です。
誤った情報・デマを収集する可能性がある
災害時には、何が真実なのか判断がつきにくくなるため、デマ情報が拡散されやすくなります。仮に安否状況とともにデマの情報を社内に拡散してしまった場合、多くの役員・従業員を混乱させてしまうでしょう。
そのため、SNSで安否確認を行う場合には、信頼性のあるアカウントからの情報であるかを確認し、デマ情報を収集しないように注意しましょう。
公式の発表や信頼できるニュースソースを参照し、正確な情報を共有することが重要です。また、デマ情報を見かけた場合には、冷静に対処し、正しい情報を広める努力をしましょう。
SNSだけで安否確認をするのは不安も多い

SNSは日常的に利用されているため、災害時にも手軽に安否確認ができる手段として有効です。
ただし、安否確認や情報共有にSNSに依存するのはリスクがあります。情報の信頼性やプライバシーの問題が懸念されるため、安否確認を行う際には他の手段との併用がおすすめです。
災害時に備えて安否確認システム導入がおすすめ
Biz安否確認/一斉通報システムでは、自動配信や自動再配信、自動集計など、安否確認に必要な機能が搭載されています。通信事業者だからこそ、災害時でも安定した通信を実現しており、安心して利用可能です。
災害におけるSNSに依存しない安否確認の手段として、「Biz安否確認/一斉通報」をぜひご活用ください。
