子宮筋腫について
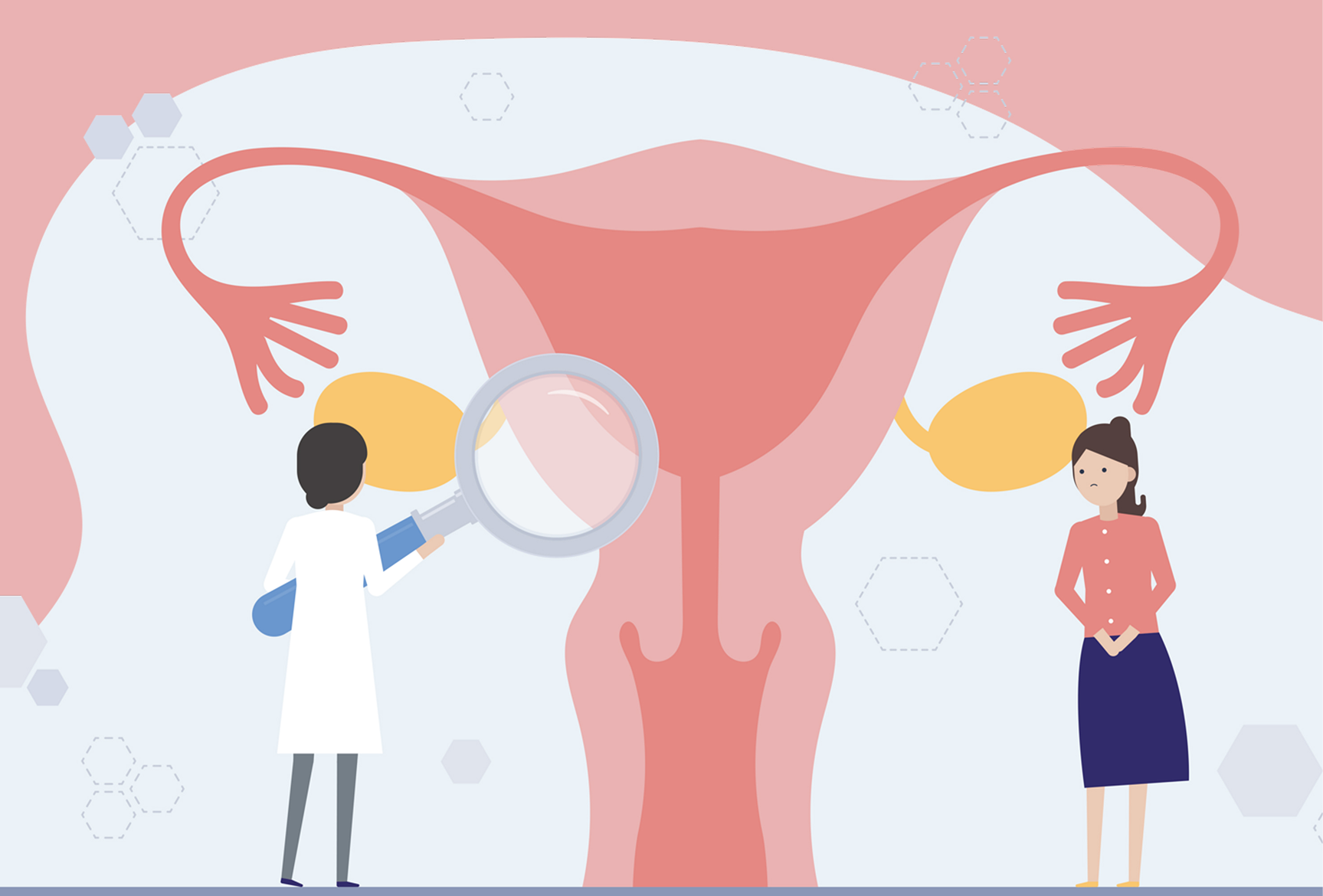
概要
子宮筋腫は、子宮の壁から発生する筋肉のかたまり(こぶ)です。多くの女性に起こる良性の疾患で、35歳以上の女性の約30%以上が子宮筋腫をもっているとされています。子宮筋腫は大きさや数がさまざまで、症状がない場合もあれば、生活に支障をきたすほどの症状を引き起こすこともあります。筋腫はエストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンの影響を受けやすく、閉経後には少し小さくなることが多いです。子宮筋腫の治療方法は、症状の有無や筋腫の大きさ、患者の年齢、妊娠希望の有無によって相談していきます。
原因
子宮筋腫ができる原因はまだ完全には分かっていません。これまでの研究から、遺伝、肥満、高血圧、エストロゲンの状態など、いくつかの原因があると考えられています。遺伝的要因では、家族(母親、祖母、姉など)に子宮筋腫の既往歴がある場合、その方も筋腫ができるリスクが高まることが知られています。また、エストロゲンとプロゲステロンのホルモンが筋腫の成長を促進するため、これらのホルモンのバランスが崩れることが一因とされています。さらに、肥満や高血圧などの生活習慣病も、子宮筋腫の発生リスクを高める要因となります。また、これらの原因がない方でも、筋腫が発生してしまうことはあります。
症状
子宮筋腫の症状は、筋腫の大きさや位置、数によって大きく異なります。ほとんど女性は無症状であることが多いですが、以下のような症状がでることもあります。
・過多月経
・不正出血
・月経痛(腹痛、腰痛)
・圧迫症状(頻尿、便秘)
・不妊症
・流産、早産
多く見られる症状は、過多月経(生理の出血量が異常に多いもの)や不正出血です。これは、筋腫が子宮内膜に影響を与えるためです。
また、下腹部の圧迫感や腹痛や腰痛も一般的な症状です。大きな筋腫が膀胱や直腸を圧迫すると、頻尿や便秘の症状が現れることもあります。さらに、筋腫の位置や大きさによって不妊や流産のリスクが高まることも報告されています。これらの症状が日常生活に影響を及ぼす場合は、手術やホルモン剤などの治療を相談します。
検査・診断
子宮筋腫の診断には、問診、内診、超音波検査、必要に応じて画像検査などを行います。
産婦人科での診察は以下のような流れで行います。
1. 問診
月経の状態(月経痛、月経量、不正出血の有無)や症状の有無、家族歴などを確認します。
2. 内診
超音波検査で子宮や卵巣の状態、子宮筋腫の大きさや位置を確認します。内診が難しい方では、お腹の上から経腹超音波検査で行うこともできます。
3. MRIやCTスキャン
画像検査は、超音波検査で子宮筋腫の位置や大きさが正確に分からないときや、癌などの悪い所見がないかを調べるときなどに行われることがあります。
4. 子宮鏡検査(ヒステロスコピーなど)
子宮筋腫が子宮内に出ているかを調べる場合、子宮鏡検査で直接観察することもあります。
これらの検査結果にもとづいて、治療の方針を相談していきます。
治療
子宮筋腫の治療法は、症状の有無、筋腫の大きさ、患者の年齢や妊娠希望などにもとづいて相談します。
1. 症状が軽度の場合
経過観察や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、ホルモン療法(低用量ピル、黄体ホルモン剤など)、鉄剤、止血剤、漢方などを使うことが多いです。
2. 症状が重い場合や筋腫が大きい場合
薬物療法に加えて手術療法が検討されます。
手術療法には、筋腫核出術や子宮摘出術があり、患者の希望や症状の重症度に応じて相談します。最近では、手術以外の治療法として、子宮動脈塞栓術(UAE)や集束超音波治療(FUS)なども利用されています。
月経痛が強い場合や、月経の量が多い場合には、子宮筋腫が隠れていることがあるので、産婦人科への受診をおすすめします。




