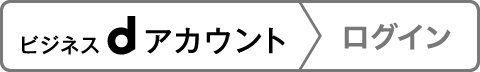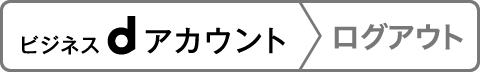Data & Opinion
想像を超える力強い変化がすべての子どもたちに
子どもたちの変化と創造
導入の効果子どもたちの変化と創造
導入の効果授業での実践授業に積極的に参加していますか?──。
この問いかけに、小学校3年生から6年生の実に95.6%が、「とてもそう思う」「そう思う」と回答しています。
これは、熊本市立小学校(全92校)に通う生徒のアンケート結果です(6月11日時点)。
熊本市では、2018年9月から大規模な教育ICTプロジェクトを始動させ、先行導入24校へのタブレット配備を皮切りに、小学校92校に対する配備も完了させました。
変化する子どもたち
高まる学びへの意欲
その全3年生から6年生を対象にしたアンケートによると、タブレットを「1週間に1日~3日ぐらい使っている」とした生徒が43.7%で、「毎日使っている」と答えた生徒は26.4%におよび、これに「1か月に1日~3日ぐらい」(22.4%)を足すと、全体の92.5%の生徒が、タブレットを使った教育ICTを体験している計算になります(いずれの数値も2019年6月11日時点/有効回答数1万4,755件)。
その効果が、授業に対する参加意欲や理解、発言の積極性、クラスメイトとの協働による問題・課題解決の風土形成へとつながり、いずれのアンケート結果も好結果がもたらされているといえそうです(図1~4参照)。

熊本市立楠小学校における授業風景。子どもたちがタブレットを活用し、課題に対して自分たちの考えをまとめ、率先して発表している。
実際、今回、『第3章/2.授業での実践』でお話をうかがった、先行導入校のひとつ、楠小学校の先生方も、タブレット導入の効果として、授業に対する参加意欲の劇的な向上を挙げています。併せて、子どもたちが、自分の考えや意見を進んで発表するようになり、主体的な学びが実現されつつあるとしています。
この観点からいうと、図3の「自分の考えや意見を進んで発表していますか?」の問いに対して、「とてもそう思う」「そう思う」とした生徒の割合が69.7%というのはやや低く感じられます。ただし、これから全小学校でのタブレット活用がさらに進展すれば、この数値がジャンプアップしていく可能性は高いといえます。

熊本市立楠小学校における授業風景。子どもたちがタブレットを活用し、課題に対して自分たちの考えをまとめ、率先して発表している。
楽しさが育む意欲と表現力
「未来に向けた学び」は
こうして生まれている


教育ICTプロジェクトによって、熊本市の中学校でも、学びに対する生徒たちの意欲は高まりを見せています。先行導入中学校のひとつ、北部中学校の上野 正直校長はこういいます。
「先生の誰にタブレット導入の効果を聞いても、学びに対する生徒たちの参加意欲や思考力、表現力の高まり方がスゴイと答えます。タブレットを使った学びはとにかく楽しい。それが子どもたちの意欲や表現力の向上にかなりきいているようです」
北部中学校は、8つの先行導入中学校のなかでも、教育ICTの活用に積極的な一校です。同校は、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)に向けた教育「ESD(Education for Sustainable Development:持続可能な開発のための教育)」の指定校であり、子どもたちに、『持続可能な社会の担い手になる資質・能力を身に付けてもらう』ということを大目標として掲げています。
「その資質・能力とはつまり、『知識・思考力』と『行動力』(論理的思考や批判的思考/コミュニケーション能力/リーダーシップ/協働力、など)です。これらの力を育むうえでは、友達同士で学ばせることや主体的に学ばせることがとても大切で、そのために有効なツールが、タブレットであり、ICTだということです」(上野校長)。
実際、タブレットの導入以降、授業はみるみる進化していき、子どもたちが主体的に課題に取組んだり、発表したりする機会も増え、子どもたちの表現力も機会あるごとに高まっていると、上野校長はいいます。

そうした変化をつぶさにとらえてきた熊本市教育センター教育情報室 指導主事の山本 英史氏は、次のように北部中学校の成功の要因について語ります。
「北部中学校のいいところは、教育ICTへの熱心な取組みが、子どもたちによるICT活用や表現力の向上にきちんと転換されている点です。先生の代りに生徒が教壇に立ち、クラスメイトたちに自分の得た知識を教える場面も多く見受けられます。このような状況がスピーティーに生まれたのは、校長先生のリーダーシップと、子どもたちにどんな力を身に付けさせたいかの目標が明確なおかげだと思います」

北部中学校では、ベテランの先生から若手まで、年齢を問わずICTを教育に取入れています。
「私にとって想定外だったのは、ベテランの先生が教育ICTに興味を抱き、率先して使いはじめたことです。ベテラン先生は、タブレットに精通しているわけではないですが、授業で使うポイントはこころえています。使い方が実にうまい。それに、タブレットには先生を熱くさせる何かがあって、ベテラン先生の熱が、どんどん周囲に伝搬していきます。もっと便利で効果的な使い方はないものかと、ほかの先生たちも授業づくりにかなり前向きになっています」(上野校長)。
授業の変革
ベテランを巻き込む
ICTの魅力
こうした先生たちのニーズを受け止めるために、教育委員会ではドコモと共同で、先生方に向けたワークショップ型の教育ICTリーダー研修も展開し、各校での事例の共有化も推進してきました。
「このような取組みを通じて、教育ICTを使い倒したいという先生同士のアイデアや事例の共有を促し、教育ICTの活用レベルを全市的に底上げするのが教育委員会の目標です。北部中学校は、教育ICTで授業を進化させるスピードが特に速いですが、事例・情報の共有で他校にも似たようなペースで活用を進めてもらいたいと考えています」(山本氏)。
その北部中学校では現在、ESD指定校として、社会的な課題に結び付いた学びの醸成にも力を注いでいます。
「日本は純粋な学力では世界トップクラスにありますが、『学校で学んだことが社会で役立っているか』という点については底辺という結果。つまり、学んだことと社会とが実感として結び付いていないわけです。ですから、当校では、学校の学びと社会をつなげる授業づくりを常に心がけています」(上野校長)
この方針のもと、北部中学校では、タブレットを使いながら現代的な諸課題に関する教科横断的な学びを推進しています。
「たとえば、タブレットを持って理科の実験で使う植物を撮影して、構造を学び、美術の授業でその花を描かせれば、理科で学んだ構造への理解が生きてきます。またそうした知識を、今度は花の栽培に活かしていく。このようにICTを使いながら、教科横断的な学びを進めると、子どもたちは、学問で得た知識が何につながっていくかを理解し、学ぶことの意味に気づいてくれます。そして、自分の学びが社会的な課題解決にどうつながっていくかも理解できるようになる。しかも、横断的な学びのなかでは、『もう少し、あのことを学んでおくべきだった』といった自分の課題発見につながるフィードバックも得られ、各教科での学力向上のモチベーションにつながっていくのです」(上野校長)。
子どもたちの創造
ICT活用で躍動する
子どもたちの創造性

北部中学校の生徒会委員会のプロモーションビデオを披露する上野校長。


北部中学校における技術の授業風景。技術の授業で撮影した植物の画像は、ほかの教科の学びにも活かされる。
北部中学校では、EDS指定校として各教科での学びに常にSDGsの視点を取入れていますが、それは生徒会の委員会活動についても同じです。その取組みの一環として、各委員会に自分たちの活動をアピールするプレゼンテーションをタブレットで作らせ、全校に向けて発表させたところ、目を見張るようなアウトプットが得られたといいます。
たとえば、自転車登下校の安全を確保する委員会のプロモーションビデオは、開発途上国の通学路がどうなっていて、どのような危険を冒しながら子どもたちが通学しているかを示し、全員の興味を喚起したうえで、自分たちの地域の自転車通学には、どういった危険があり、どうしなければならないか訴え、委員会活動への参加と協力を呼びかけるというものです。
「このビデオクリップにも驚かされましたが、ほかの委員会のプレゼンも素晴しいものばかりで、SDGsの視点を取込みながら、自分たちがすべきこと、学ばなければならないことを見事に表現していました。これらは、大人でも簡単には作れないようなものばかりです。子どもたちに、使いやすいツールを与えると、そうした表現力を瞬く間に身に付けてしまうんです」(上野校長)。
北部中学校では、ビデオクリップツールをさまざまなコンテンツ作りに活用しており、クラスの男女が、お互いの良さを語り合いながら、紹介ビデオを制作するという取組みも実践しました。
「それによって制作されたコンテンツも非常によくできたアウトプットでした。思春期の男女が見つめ合って互いのことを語り合うというのは、なかなかむずかしいシチュエーションのように思えますが、タブレットというメディアを介在させると、それが抵抗なくできてしまうようです。そのうえで他者を思いやるコミュニケーション力や課題発見・解決能力も養うことができ、自己肯定感の発揚にもつながります。いい試みでしたね」(上野校長)。
また、このようにしてビデオクリップでの表現を学ぶことで、子どもたちが自主的に教科での使い方を提案し、自分たちのアウトプットを発表する機会を増やしていったといいます。
結果として、問題の正解がいえる生徒たちだけが授業に参加し、いえない生徒が授業から置き去りにされるような状況もなくなりつつあるようです。
「最近の会議で、先生たちが『そういえば、最近は“みんな、正解がわかったか”と生徒に聞いていないな』と話しはじめたんです。それは授業のなかで、先生が、答えを教える唯一の人ではなくなったことの現れです。答えは生徒たちが探し、誰もがその取組みに参加しようとする。そんな学びが教育ICTのおかげで醸成してようとしています」

北部中学校の生徒会委員会のプロモーションビデオを披露する上野校長。


北部中学校における理科の授業風景。理科の授業で撮影した植物の画像は、ほかの教科の学びにも活かされる。
かつての大量生産・大量消費時代から産業構造が大きく変化し、物質的に豊かになることが、人生の価値ではなくなっています。そして、これからの世界を見据えたとき、気候変動、人口爆発、水不足、食糧危機などさまざまな課題があり、一方で、AI(人工知能)の発達によって、知的労働の本質的な意義すら問われはじめています。
今の小学生や中学性が社会人になる10年先、20年先、あるいは30年先に社会がどうなっているかは、私には予測できません。おそらく世界の誰にも予測できないでしょう。
そのなかで、子どもたちの教育に携わる私たちが、どのような能力を持った人材を育むべきなのか──。それは、自ら学び、社会の変革者になるモチベーションを持った人材だと私は考えます。つまり、社会全体の幸福を自分のこととして追求できるような志(こころざし)を持ち、そのために必要な技術と知識を自ら獲得できる人材です。
こうしたモチベーションは、今の日本人に最も欠けているものです。自ら変革者になり、新しい社会を作り上げようとする強い意志が、現代の日本人には明らかに足りていません。理由は「自己肯定感」が低いためです。従って、これからの教育は、『自分たちでも、大きな問題が解決できる』という自己肯定の意識を、子どもたちに強く持たせることが重要といえます。

これまでの教育は、唯一無二の正解を持った先生が、一方的に問題を出し、答えられる子どもだけが授業に参加して、テストをして、子どもたちをランク分けして、上に送り出すのがすべてでした。このような教育では自己肯定感は養われませんし、これから先はやってはならない教育です。答えがわからなくてもいい、何度失敗してもいい、試行錯誤の繰り返しのなかで自ら答えを見つけていけば、『社会の担い手になれる』という自己肯定感を育むことが必要です。
識者の眼:どうして今、教育ICTなのか
熊本大学大学院 准教授
前田 康裕氏


「教育ICTは、これから絶対必要な学びの環境です」と前田准教授はいい切る。
そのような自己肯定感を育む教育を行ううえで、とても有効なツールが教育ICTであり、タブレットです。タブレット上では何度も失敗できますし、自分の創造性を活かす道具として非常に扱いやすく、自分の考えやアイデアを豊かに表現できます。また、自分の学びやアイデア、知識を手軽に周囲と共有し、それによって新しい知識も獲得できます。このツールを教育にうまく活用することで、子どもたちは、自ら課題を見つけて、それを解決するための情報収集と活用の力を養うことができるようになります。
ときおり、教育ICTに力を入れ過ぎると、肝心の学力アップがおろそかになるといった意見が聞かれますが、それは誤解です。
もちろん、基礎的な学力を身に付けることは大切ですが、それと教育ICTは全く矛盾していません。ICTを使った学びによって、課題をみつけ、その解決を図ろうとしたときには、必ず基礎的な知識やスキルが必要とされ、それによって子どもたちは知識を習得する意味に気づき、学問に対するモチベーションを高めるからです。ですから、教育ICTの推進によって子どもたちの学力は間違いなく向上するはずです。逆に、モチベーションがなければ学力アップも創造性の発揚も望めないといえるでしょう。
ICTはこれからの教育に絶対に必要なものです。その考え方に沿って始動した熊本市の教育ICTプロジェクトは評価に値するものですし、私もその成功に向けて協力を惜しまないつもりです。教育ICTは、使う方向性さえ間違えなければ、個人の幸せと社会の幸せを同時に考える人材を育むことができるものです。

「教育ICTは、これから絶対必要な学びの環境です」と前田准教授はいい切る。
導入の効果子どもたちの変化と創造
導入の効果授業での実践お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
ドコモビジネスコンタクトセンター
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)